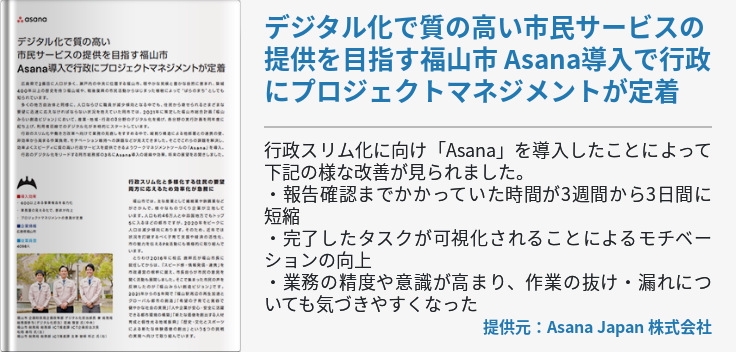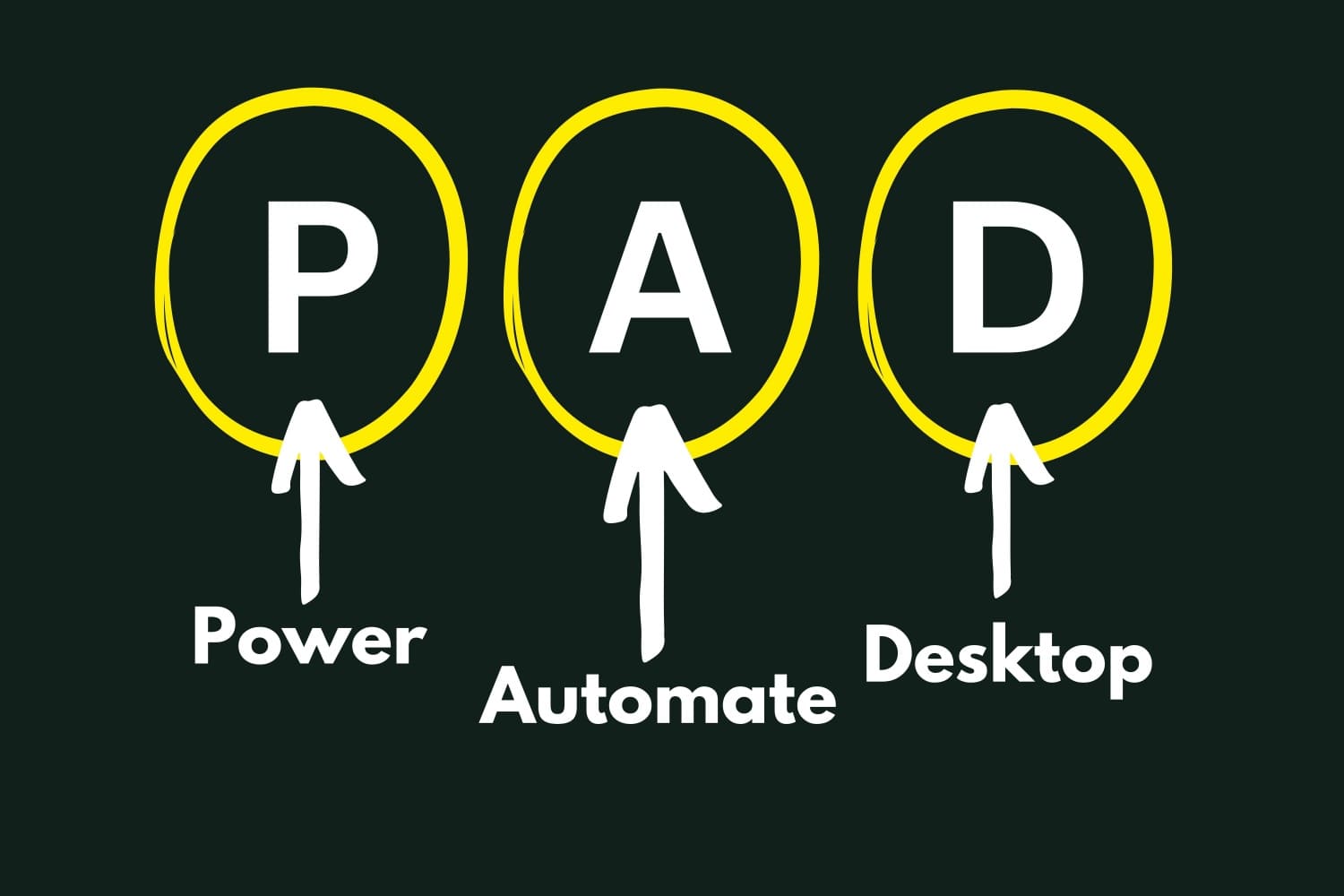仕事の効率化を図るために、さまざまな技術やアイデア、ツールなどが仕事の現場で取り入れられていますが、その1つに「
RPA
」というものがあります。
RPAとはどのようなものなのでしょうか。今回は、多くの企業が導入しているというRPAについてわかりやすく解説するとともに、RPAを用いる場面やメリット・デメリット、さらにAI(人工知能)やマクロとの違いについても詳しく紹介します。
仕事の現場で今後導入されるのが当たり前になるかもしれないRPAについて、理解を深めておきましょう。
RPAとは?
RPAとは、「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略です。ロボットの力で、これまで人の手によって行われていた作業を自動化するソフトウェアのことを指し、仕事における大幅な効率化を目指します。
例えば、RPAが大きな力を発揮しやすいのが、事務作業です。リスト作成やExcel上のコピー&ペーストによる入力、インターネット上にあるデータをコピーして入力するなど、「繰り返し行われる作業」に適しています。それまで作業を行っていた事務担当者の作業時間が大幅に削減できることがメリットです。
RPAはロボットのためミスもなく、人間の手で行われる作業に比べて何十倍ものスピードを持ちます。そのため、RPAは「仮想知的労働者(デジタルレイバー)」とも呼ばれ、人間と違って長時間機能させることも可能です。
RPAの仕組みを簡単に紹介
RPAが動作する仕組みは、以下のステップで構成されます。
- ソフトウェアロボットが人間が行う作業を学習
- ユーザーがRPAにタスクを指示
-
RPAが指示通りかつ、自動的に業務を実施
例:データの入力、データの処理、カーソル移動、ボタンのクリックなど
3のプロセスをRPAが行うことで、人間の慣れによる油断や、集中力低下によるエラーが回避されます。RPAは柔軟性を持ち、1,2のプロセスを行えば作業内容の更新が可能です。よって仮に組織の業務プロセスが変更となっても問題なく対応できます。
3つのクラスと特徴
RPAを用いて行う業務は以下の3つのクラスに分類されます。
- RPA(Robotic Process Automation)
- EPA(Enhanced Process Automation)
- CA(Cognitive Automation)
クラス1:RPA(Robotic Process Automation)
RPAは、ソフトウェアロボットを使用してルールベースのタスクを自動化する技術です。以下の特徴を持ちます。
- 単純な繰り返し作業やルールが決まっている作業の自動化に適している
- 人間の操作(クリックやスクロールなど)を記録し、記録したタスクを実行する
- プロセスの改変や柔軟な判断が必要な場面には使えない
一番下の特徴に対してはAIを組み合わせることで対応可能です。しかし、この場合は後述のEPAやCAとして見なされます。
クラス2:EPA(Enhanced Process Automation)
EPAはRPAよりも拡張されたプロセス自動化です。EPAは以下の特徴を持ちます。
EPAの最大の特徴はRPAやワークフローエンジン、データベースなど、複数の技術を組み合わせることです。EPAを導入、活用することのゴールはRPAと同じく「ビジネスプロセスを効率化し、組織の生産性を向上させる」こととなります。ただし、EPAは、単一の技術や手法に限定されません。複数技術で柔軟性を高めることで最適なプロセス自動化ソリューションを構築することを重視します。
クラス3:CA(Cognitive Automation)
CAは、人工知能(AI)と機械学習(ML)を活用して、複雑な判断や認識タスクを自動化する技術です。
AIや機械学習について詳しく解説した記事
もあわせてご覧ください。
CAは自然言語処理、画像認識、音声処理などのAI技術を使用して、非構造化データや判断タスクを処理する特徴があります。RPAとは異なり、高度なAIを用いて学習、認識、理解、判断をさせることで、人間に近い処理が可能です。
参考: AI学習の方法とは? AIの基礎から分かりやすく解説
RPAツールの種類

RPAツールは利用形態として以下の3つのタイプがあります。
- デスクトップ型
- サーバー型
- クラウド型
①デスクトップ型
デスクトップ型RPAは個々のデスクトップ環境で使用されるRPAです。個々のPC上で動作し、ユーザーインターフェースに基づいて操作を行います。あくまで1台のPCによる作業の自動化を扱うため、別のPCとの連携は基本的に考えていません。デスクトップ型RPAは、単純な繰り返し業務やルーティーンワークに適しています。例えば、データ入力やファイル処理、レポート作成、データの抽出や変換など、手順や内容に柔軟性がほとんど必要ない業務の自動化が可能です。
②サーバー型
サーバー型RPAはサーバーシステム上で動作する集中管理型のRPAです。デスクトップ型RPAとは異なり、中央のサーバーシステム(コントロールサーバー)が複数のPC間と通信をすることで集中管理を行います。
サーバー型はコントロールサーバーへの操作のみで、複数台の作業用サーバーを作業させられるため、サーバー間共有や集中管理が容易な特徴を持ちます。コントロールサーバーが複数の作業用サーバーと連携することで、複数台のPCに連続して自動化プロセスを実行することが可能です。またコントロールサーバーからのアクセスが可能であれば、作業PCが離れた場所にあってもプロセスを実行できます。これらの特徴からサーバー型RPAはより大規模なルーティーンワークや、リモートワーク時のプロセス自動化に利用可能です。
③クラウド型
クラウド型RPAは名前の通りクラウド上で提供されるRPAです。IaaSやPaaS上でRPAを用いることが可能で、①②どちらのタイプも存在します。①②はオンプレミス環境のRPA、③はクラウド環境のRPAと考えるとイメージがつきやすいでしょう。
オンプレミスとクラウドの違いを解説した記事 もありますので、あわせてご覧ください。
クラウド型ではクラウドを利用する以下のメリットを享受しながらRPAを運用できます。
- スケーラビリティが高いため、作業サーバーの数を増減できる
- オンプレミスで必須となるサーバーの導入や運用のコストを削減できる
- クラウド事業者の高度なセキュリティを利用したRPA運用が可能
RPAが求められる理由と背景とは
では、仕事の現場においてRPAがなぜ求められているのでしょうか。その理由や背景について、考えられる理由を1つずつ解説していきます。RPAの導入があちこちの企業で進められている理由を考えると、日本が抱える大きな課題が浮き彫りになっていました。
日本の慢性的な人材不足
まずRPA導入が進められる理由として挙げられるのが「人材不足」です。日本では深刻な少子高齢化が進んでおり、働き手となる世代の人口が減っています。
さらに、経済の不透明性から転職を余儀なくされる人も少なくないのが現状で、1つの仕事で長続きしづらくなっており、企業は人材育成にも大きな労力をかける必要があります。
生産年齢人口は今後も減り続けると考えられており、企業にとって有能な働き手がいないことが慢性的になっているのが大きな課題です。そのため、労働力の確保は急務といえるでしょう。
だからこそ、人材教育をする必要がなく、労働時間の上限も関係なく導入できるRPAは、人材不足を嘆く企業にとって強い味方といえます。
世界的に見て低い日本の労働生産性
RPA導入の理由として次に挙げられるのが、「日本の低い労働生産性」です。日本は先進国でありながらも、その労働生産性は最低レベルだということがわかっています。
労働生産性とは、働く人1人あたりが生み出せる結果(売上や生産量など)を数値化したもので、この数値が高ければ高いほどその企業は効率よく仕事を進めていることがわかります。
日本はこの労働生産性が低いことがわかっており、国際的な競争の中で今後生き残っていけるのかが懸念されます。企業の生き残りをかけ、労働生産性を引き上げていく取り組みが急務です。
RPAを導入し、人的作業の代替を行うことは労働生産性の引き上げに直結するため、RPAの導入が進められています。
働き方改革の実現
日本で2019年に厚生労働省から発表された「働き方改革」も背景の1つです。一人ひとりが柔軟な働き方ができるよう、国を挙げてさまざまな取り組みが行われています。
柔軟な働き方を実現することは、人材不足の解消や労働生産性の向上にも直結するでしょう。RPA導入により、ある程度作業を自動化すれば、人間は付加価値の高い業務に専念できるというメリットが得られます。付加価値の高い業務に取り組めるようになれば労働意欲もわきやすく、労働生産性のアップにもつながるでしょう。
マクロやAIによる業務効率化とは何が違う?
RPAはロボットによる作業の自動化を図るソフトウェアと紹介しましたが、似たようなイメージで用いられているのが「マクロ」や「AI」の存在です。
これらとRPAにはどのような違いがあるのでしょうか、RPAの特質を理解し、マクロやAIとどのような違いがあるのかを詳しく見てみましょう。
マクロ・VBAとの違い
まず、マクロやVBAとの違いについて見てみましょう。
パソコンでの作業を自動化する仕組みの1つとして知られているのが、「VBA(Visual Basic for Applications)」です。パソコンのアプリでおなじみ、MicrosoftのWord・Excelなどで、これらのアプリの作業を自動化するよう作られたプログラムのことをいいます。また、マクロはこうした「特定のアプリの操作を自動化できる」プログラムです。
一見、マクロもVBAも、RPAと同じように感じるかもしれませんが、RPAはMicrosoftのアプリに限定せず、その端末上(パソコンなど)で行う作業全般を自動化できるという違いがあります。
AIとの違い
次に、RPAと「AI」との違いについて見てみましょう。
AI(Artificial Intelligence)(アーティフィシャル・インテリジェンス)は「人工知能」と呼ばれており、繰り返し作業を行わせて(考えさせて)学習させることで、次回以降同じような作業内容だった場合に、
業務改善
の方法などを「考えて」判断できるのが特徴です。
RPAにはこうした「考える」という機能はなく、あらかじめインプットしておいた作業をただひたすら繰り返すのみです。AIはあくまで考える能力であり、RPAのように実際にコンピュータの中で作業を行うことはありません。
つまり、考えるAIと、実際に作業を行うRPAを組み合わせることで、高い作業効率化が期待されています。
RPAが得意なこと

以下の得意な作業をRPAで実施させることにより業務プロセス自動化、業務の効率化が期待できます。
- 単純作業
- ルール化された定型作業
- 膨大なデータ処理が必要な作業
単純作業
RPAは単純作業の効率的な処理が得意です。RPAは指示された手順に従って高速かつ正確な作業を自動で行います。例として、データの入力やコピー&ペーストの作業は、反復的かつルーティンなタスクです。人間が行う場合、疲労や慣れによる油断から長時間作業していると、どうしてもミスが発生してしまいます。一方でRPAは疲労せず、同じタスクに対して同じ成果を出し続けることが可能です。RPAは長時間の単純作業でもミスなく持続できるため、業務の効率化を実現します。
ルール化された定型作業
RPAは明確なルールや手順が存在する定型作業が得意です。定型作業とは、特定の手順や条件に基づいて行われる作業を指します。例えば、顧客情報の更新や請求書の作成などが定型作業です。RPAはルールベースの作業自動化により、定められた手順に従って作業を実行し、人間の操作を最小限に減らします。またRPAには柔軟性があり、定型作業の変更があった場合でも、ルールを変更することで容易に変更が可能です。
膨大なデータ処理が必要な作業
RPAは膨大なデータの効率的な処理が得意です。例としてデータの抽出、変換、データベースからの読み込み、データベースの更新など、さまざまなデータ処理作業をRPAによって自動化できます。昨今はビジネスにおける判断や収集できるデータの量が膨大になり、処理や分析には労力が必要です。人間によるデータ処理の作業時間が大幅に短縮されるので、効率的な意思決定を可能にし、ビジネスプロセスの最適化を実現します。
RPAが不得意なこと

RPAが得意な作業を解説しましたが、一方で以下のようにRPAが不得意な作業もあります。
- 画像や手書き書類などに関する作業
- 判断が必要な作業
画像や手書き書類などに関する作業
RPAは画像や手書き書類などを扱う作業が苦手です。RPAはテキストベースの情報に基づいて処理を行うため、画像や手書き文字の認識や解釈を得意としていません。手書き文字を認識する際には、精度や正確性に問題が生じることがあります。この問題は、手書き文字を読み取る技術であるOCR(Optical Character Recognition)を備えたRPAの活用である程度解消できます。しかし、画像や手書き書類などに関する作業では、RPAに加えて専門的な技術やツールが必要となると考えておきましょう。
判断が必要な作業
RPAは複雑な判断や意思決定が必要な作業は不得意です。RPAは単純作業やルールベースの自動化に適しており、特定の手順や条件に基づいてタスクを自動化します。この特徴は予め設定したルールに基づいて動作するためです。しかし、RPAはルール以外の柔軟な判断や状況への対応は苦手としています。例として、電話応対や顧客の要望に応えるカスタマーサービスの提供など、相手の要求や状況に応じた判断が必要な場面です。こうした場合には、人間の判断力や対話能力が必要となり、RPAだけでは対応できません。
RPAのメリットとデメリットについて
RPAと、AIやマクロなどそのほかのプログラムとの違いについて理解したところで、ここからはRPAを導入すると得られるメリットや、考えられるデメリットについて詳しく紹介します。
RPAの導入を検討している場合には、ぜひチェックしておきましょう。
RPA導入によるメリット
まず、RPAを導入することで得られるメリットについてです。
-
人的ミスの防止
RPAを導入する大きなメリットが、人の手によって起こり得る人的ミスの回避です。確認したつもりでも入力ミスがあったり、コピーを行う部分が違ったりするなど、人の手で起こるうっかりミスをRPAで回避できます。 -
人件費の抑制
RPAはプログラムのため、人間と違っていつでもどのようなときでも作業を進められます。つまり、人がオフィスから退社した後、通常なら残業代や深夜手当などの費用が必要になる場合でも、RPAなら人件費がかかりません。 -
より高度な業務に人的リソースを集中投下できる
RPAの導入によって、繰り返し行われる単調な作業をRPAに任せられるようになります。結果として、人的リソースを、RPAでは対応不可能な高度な作業に集中投下でき、作業の効率化が図れます。
RPA導入で懸念されるデメリット
続いて、RPA導入によって懸念されるデメリットを見てみましょう。
セキュリティ面でのリスク
RPAはプログラムのため、指示された業務を繰り返し忠実に実行します。作業内容の中には個人情報が含まれたデータを入力するなど、セキュリティやプライバシーに引っかかる情報を扱う可能性もあり、セキュリティ面でのリスクがあると考えられます。
-
万一の際に作業が滞ってしまう
RPAが何らかの原因で動作できなくなってしまうと、万一の際に作業が滞ってしまう可能性があります。 -
誤作動などで被害が生じる可能性がある
繰り返しますが、RPAは人ではなくプログラムです。うっかりとした人的ミスは防げるものの誤作動を起こす可能性もあるため、万一の際には対応できるようにしておく必要があります。
RPAツールの選定ポイント

RPAツールの選定ポイントは以下の通りです。
- 現場の人間が使いこなせるか
- 既存のシステムと適合するか
- セキュリティは堅牢か
- コストに見合っているか
上記を踏まえ、導入時には自社にとって総合的に最適なRPAツールを選定しましょう。
現場の人間が使いこなせるか
RPAツールの選定基準としては、現場の人間が使いこなせるかどうかです。使いやすいツールでなければ、実際に社員が使いこなせず、逆に効率が悪くなってしまうケースも考えられます。マウスによる操作がしやすいことや、使い方がわかるフローチャートなどがあると、使いこなすハードルが低くなるでしょう。またトレーニングやサポートリソースが提供されていることも重要です。適切なトレーニングやマニュアルが提供されているかどうかを確認しましょう。
既存のシステムと適合するか
既存のシステムとうまく適合するRPAツールであることも重要です。RPAでは全ての業務プロセスではなく、一部のプロセスのみに活用するケースが多くなります。そのため既存システムとの連携ができないと、思ったほどの効率化にならない可能性が高いです。こうした事態を防ぐためにもAPIやコネクタが提供されているか確認しましょう。多くのアプリケーションと容易に連携できるRPAツールであれば、業務効率化に大きく貢献します。
セキュリティは堅牢か
RPAツールには、堅牢なセキュリティが用意されていることも重要です。RPAツールで、機密性の高いデータや重要な業務プロセスを扱う場合もあるでしょう。よって堅牢なセキュリティでなければ、攻撃者の格好の攻撃対象となるリスクが高いです。安心してRPAを利用するためにもデータの暗号化やアクセス制御、認証機能など、セキュリティ機能を備えているか確認しましょう。またコンプライアンスやセキュリティパッチの提供状況も確認すべきです。
コストに見合っているか
RPAツールの選定にあたってはコストに見合っているかどうかも重要なポイントです。RPAツールには、ライセンス料、導入費用、従量課金、トレーニング費用、サポート費用など多くの費用が必要となる場合があります。機能や性能に対してコストが見合っているかを考慮し、複数のツールを比較検討してください。また将来的に対象となる業務範囲を拡げた場合にも対応できるのかを含め、長期的な費用対効果も検討すべきポイントとなります。拡張性やスケーラビリティなどを意識し、RPAが将来的なニーズに対応できるか判断しましょう。
RPAの導入手順
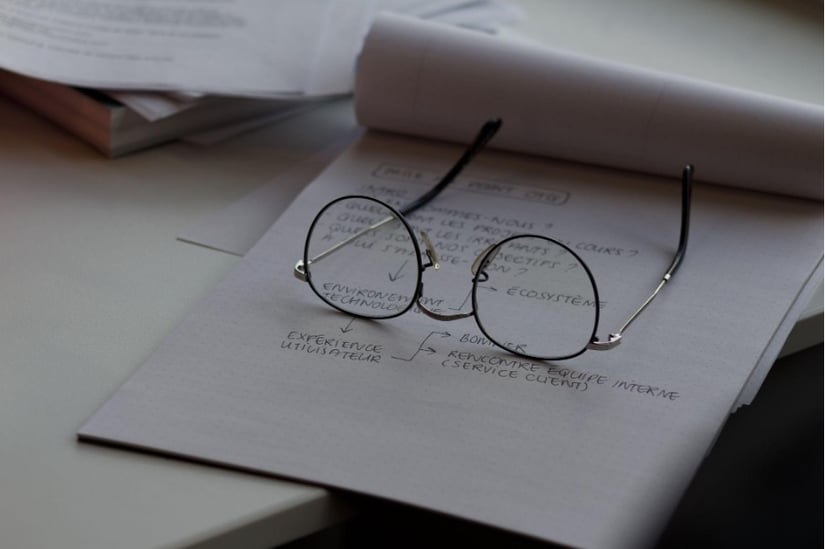
RPAを導入する手順は以下の通りです。
- 導入目的の明確化
- 現在の業務プロセスの見直しと対象業務の選定
- 製品の比較検討
- トライアルの実施
- 本格的な導入
導入目的の明確化
RPAを導入する際には、はじめに導入目的を明確化しましょう。RPAに限った話ではありませんが、解決したい課題に対する解決策としてRPAを導入すべきです。「他社がRPAを使って成果を上げていたから」と導入自体を目的とするべきではありません。目的と解決策が入れ替わらないようにしましょう。目的次第で、選定すべきRPAが異なりますので、目的の明確化は慎重に行うべきです。
現在の業務プロセスの見直しと対象業務の選定
導入目的を明確化したら、現在の業務プロセス見直しと、RPAを活用する業務の選定を行います。RPAの導入目的として課題となっている業務プロセスがあるはずです。該当する業務プロセスを精査して、プロセスのうちどの業務を改善すべきか確認してください。「RPAで自動化できそうな業務」を選ぶことも必要ですが、自動化・効率化したい業務に対しての対策を考えましょう。ここでも導入する目的と解決策が入れ替わることがないようにしてください。もちろん、RPA以外が解決策となるケースもあります。RPAの利用が最適だと判断したらに次に進みましょう。
製品の比較検討
自動化すべき業務が決まったところで、RPAツールの比較検討を行います。課題を解決できるツールの中から機能や操作性、費用、サポートなど総合的に判断して最適なツールを選定しましょう。RPAツールには多くの種類がありますので、次項で代表的なRPAツールの紹介もしています。ぜひRPAツール選定時の参考にしてください。
トライアルの実施
RPAツールの中には、無料トライアル期間が設けられているツールがあります。「百聞は一見にしかず」という言葉がある通り、実際に利用してみなければわからないことも数多くあります。特にRPAツールを利用して、どの程度の業務効率化ができるかがわかれば、社員のモチベーションも高くなります。またRPAツール自体を初めて使用する企業の場合、最初から活用イメージを持つのは難しいかも知れません。無料トライアルが可能なツールであれば、実際に利用してツール選定の判断材料としてください。
本格的な導入
トライアルまで終え、最適なRPAツールを判断できたら本格的な導入に進みましょう。サーバーの導入や、ツールのインストール、クラウドとの契約などやるべきことは多くあります。準備を終えたら、実際のプロセスに導入できるよう、プロセス設計や自動化業務を行います。完了すれば本番運用を開始しましょう。
【無料版もあり】代表的なRPAツール

代表的なRPAツールとして以下の6つを紹介します。
- Power Automate(パワーオートメイト)
- WinActor(ウインアクター)
- Automation Anywhere(オートメーションエニウェア)
- BluePrism(ブループリズム)
- BizRobo!(ビズロボ)
- UiPath(ユーアイパス)
Power Automate(旧・Microsoft Flow)
Power AutomateはMicrosoftが提供するRPAツールです。デスクトップ型、クラウド型が用意されており、無料のMicrosoftアカウントでも利用できます。無料版の場合は実行したい日時を設定した実行(○日○時○分に実行)や作成した業務フローの共有はできません。しかし、実際にRPAに業務を代替してもらうことは可能なため「どの程度の業務効率化が可能か」を確認できます。またモバイル版でも利用できる点や、他のMicrosoftサービスとの連携が容易なため、WordやExcelのファイルを利用した作業の自動化と相性がよいことがメリットです。ぜひ一度無料で利用してみてください。
WinActor(NTTグループ)
WinActorはNTTグループが開発したRPAツールです。デスクトップ型とサーバー型が用意されており、純日本産のRPAとして高いシェアを誇ります。純日本産RPAということもあり、日本語のドキュメントが充実していることがメリットです。また7,000社(2022年1月時点)以上に導入されている実績や、学習、サポートが充実していることもメリットと言えます。製品フルバージョンを30日間無料で利用できるため、ぜひ一度利用してみてはいかがでしょうか。
参考:
WinActor
Automation Anywhere(Automation Anywhere社)
Automation AnywhereはAutomation Anywhere社が提供するクラウド型のRPAツールです。クラウド型のため、場所やデバイスを問わずツールを利用できます。条件付きですが無料のトライアルが用意されているほか、トレーニングリソースや、ホワイトペーパーが用意されていることも嬉しいポイントです。本格導入する前の時点で、自社でどういった自動化が可能か、具体的なイメージを持ちやすいツールといえます。
BluePrism(Blue Prism社)
BluePrismはBluePrism社が提供するデスクトップ型、クラウド型のRPAツールです。特にクラウド型はBPC(BluePrism Cloud)と呼ばれるサービスで、クラウドのリソースと紐付けた大規模な運用が可能なRPAツールとなっています。またAIとの連携が可能で、CAクラスのRPAとして利用が可能です。デスクトップ版については無料評価版が用意されており、BPCと同じものを利用できます。イメージをつかむためにも、ぜひ一度利用してみてください。
BizRobo!(RPAテクノロジーズ社)
BizRobo!はRPAテクノロジーズ社が提供するRPAツールです。デスクトップ型、サーバー型が用意されています。充実したサポートや、オンラインコミュニティが設けられており、利用定着、成果向上に向けた学習環境が整っており、導入実績は2,500社(2023年2月時点)を超えています。またグループウェアやチャットツール、会計ツールなど多くのサービスとの連携が可能な点も嬉しいポイントです。1カ月間の無料トライアルが用意されているため、ぜひ利用してみてください。
参考:
RPA technologies
UiPath(UiPath社)
UiPathはUiPath社が提供するRPAツールです。開発、実行、管理の3つのツールに分かれているクラウド型のRPAです。組み込みリソースとして、OpenAI(ChatGPTなどのAI機能を利用可能)やOrchestrator Manager(管理者が実行ロボットに対して一括管理を行う)が用意されています。多数の導入実績や、サポート、コミュニティが用意されている点もメリットです。個人利用向けのFreeプランが用意されているため、導入前段階ではこちらを利用してみるとよいでしょう。
RPAの導入にかかる費用
RPAの導入にかかる費用としては以下があります。
- ライセンス費用(デスクトップ型、サーバー型)
- リソースの従量課金(クラウド型)
- サーバー購入費、構築費、運用費(デスクトップ、サーバー型)
- テクニカルサポート費用
- トレーニング費用
実際に導入する際に、複数人が利用する場合は数百万円単位となることも珍しくありません。よって大きな出費となります。「導入したのにほとんど意味がなかった」事態を避けるためにも、可能な限り課題の明確化や無料トライアルなど、導入前の事前準備を徹底しておきましょう。
RPA導入の成功事例

RPA導入による成功事例として以下の5つを紹介します。
- 業務時間の削減を実現「つくば市」
- 紙ベースの業務からの脱却「第一生命」
- 注文と請求手続きの合理化「コカ・コーラ」
- 事務業務を90%カット「慈恵大学」
業務時間の削減を実現「つくば市」
つくば市は住民税に対する窓口業務や事務作業に対して業務効率化のためにWinActorを導入しました。複数の業務に対し、それぞれに合う形で自動化シナリオを作成しています。例として、出退勤管理のExcelを読み取り、管理システムにデータ入力する業務を自動化しました。結果として手作業で行っていた40の業務を17にまで減らすことに成功しています。手作業の業務が減ったこともあり、WinActor導入前と比較して79.2%の稼働削減を実現できました。今後の展望として、ペーパーレスの推進によるデータのデジタル化や、職員のRPAスキル向上によって、より高い削減率を目指すとしています。
紙ベースの業務からの脱却「第一生命」
第一生命は紙ベースの業務をBluePrismを用いることで自動化し、2019年4月時点で13.2万時間の労働時間削減に成功しました。レコーディング機能のフル活用と、ディスプレイサイズが異なっても使えるようマウスの座標指定を利用しないことを徹底して、業務の効率化を目指しました。またシステムとは異なりBluePrismであれば、運用開始後の改修にも対応しやすい点を評価し、導入を決定しています。今後の展望については「最初からBluePrismの利用を前提とした業務」の創出を目指しています。
参考: BluePrism
注文と請求手続きの合理化「コカ・コーラ」
コカ・コーラ株式会社はPower Automateを用いて、注文管理業務の人員削減に成功しています。同社は配送先のデータ収集による大量のデータを管理する必要があり、新製品の販売や販売先拡大を躊躇してしまう状況でした。従来の方法では大量のデータをExcelにまとめ、CRMやSAPと連携管理しなければなりません。しかし、業務が追いつかなくなり、Power Automateを用いたデータ処理自動化を目指しました。結果として、多忙な業務プロセスからの解放につながったことで、より将来に向けた業務に取り組めるよう改善されました。
参考:
Microsoft
事務業務を90%カット「慈恵大学」
慈恵大学はBizRobo!を導入して、事務作業の時間を90%削減を実現しました。医療業界では、医師や看護師などは医療業務に集中し、受付や事務作業は別の従業員に任せる、という働き方が定着してきています。しかし、事務作業の担当者の状況次第では医師、看護師も事務作業を行わなければなりません。慈恵大学では、患者数のカウントなど事務作業の一部と、検査漏れ防止の取り組みをRPAによって自動化し、作業時間削減を実現しました。結果として、事務作業の削減は医療の質向上にもつながっています。今後の展望として、AIを組み合わせ、より効率的かつ高度な医療の提供を目指すことになりました。
参考: PR Times
まとめ
人材不足に悩む企業において、業務効率化を図る解決策であるRPAは有効な手段といえます。今後はAIツールの発展も続き、RPAと組み合わせることで単純作業やルールベースの作業以外も自動化を実現できる可能性が高まるでしょう。Microsoft製品と組み合わせることが容易で、企業活動におけるすべての業務をサポートしてくれるクラウドビジネスアプリ「Dynamics 365」の導入がおすすめです。AIが装備されたDynamics 365は、Microsoftのさまざまなアプリと連携し業務の効率化を図ることができます。
また、「Power Automate」も、反復作業を自動化できる便利なRPAです。これらのアプリを積極的に導入し、業務に追われる日々から解放されましょう。

![[Power Platform]RPA業務支援BPOサービスのご紹介 [Power Platform]RPA業務支援BPOサービスのご紹介](https://www.cloud-for-all.com/hubfs/bizapp/CTA/cta-middle-rpa-business-support-bpo-service.png)