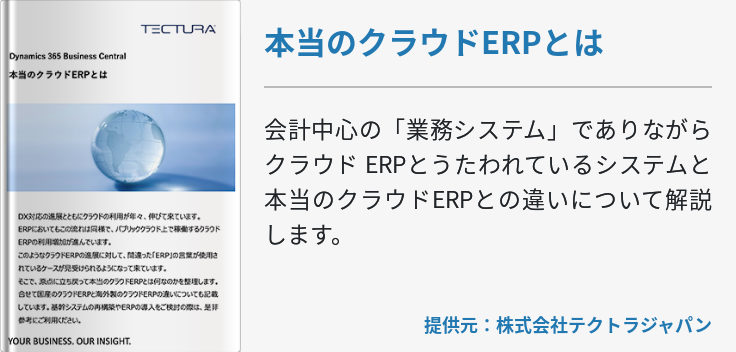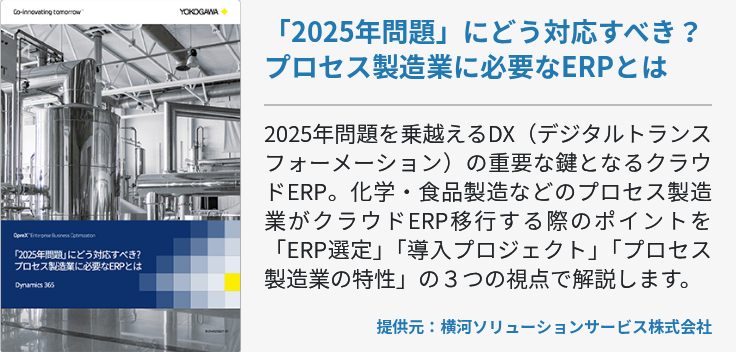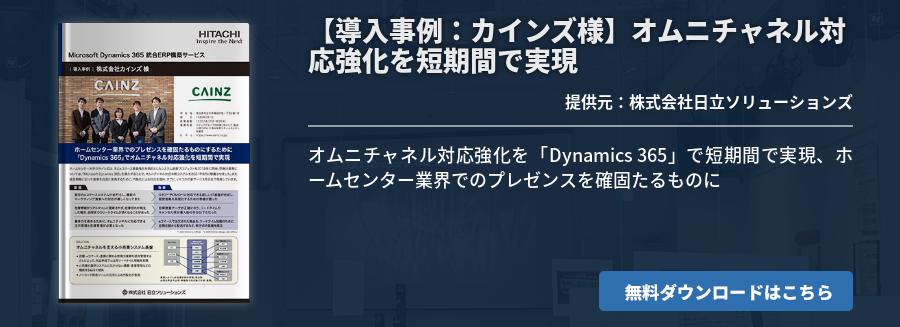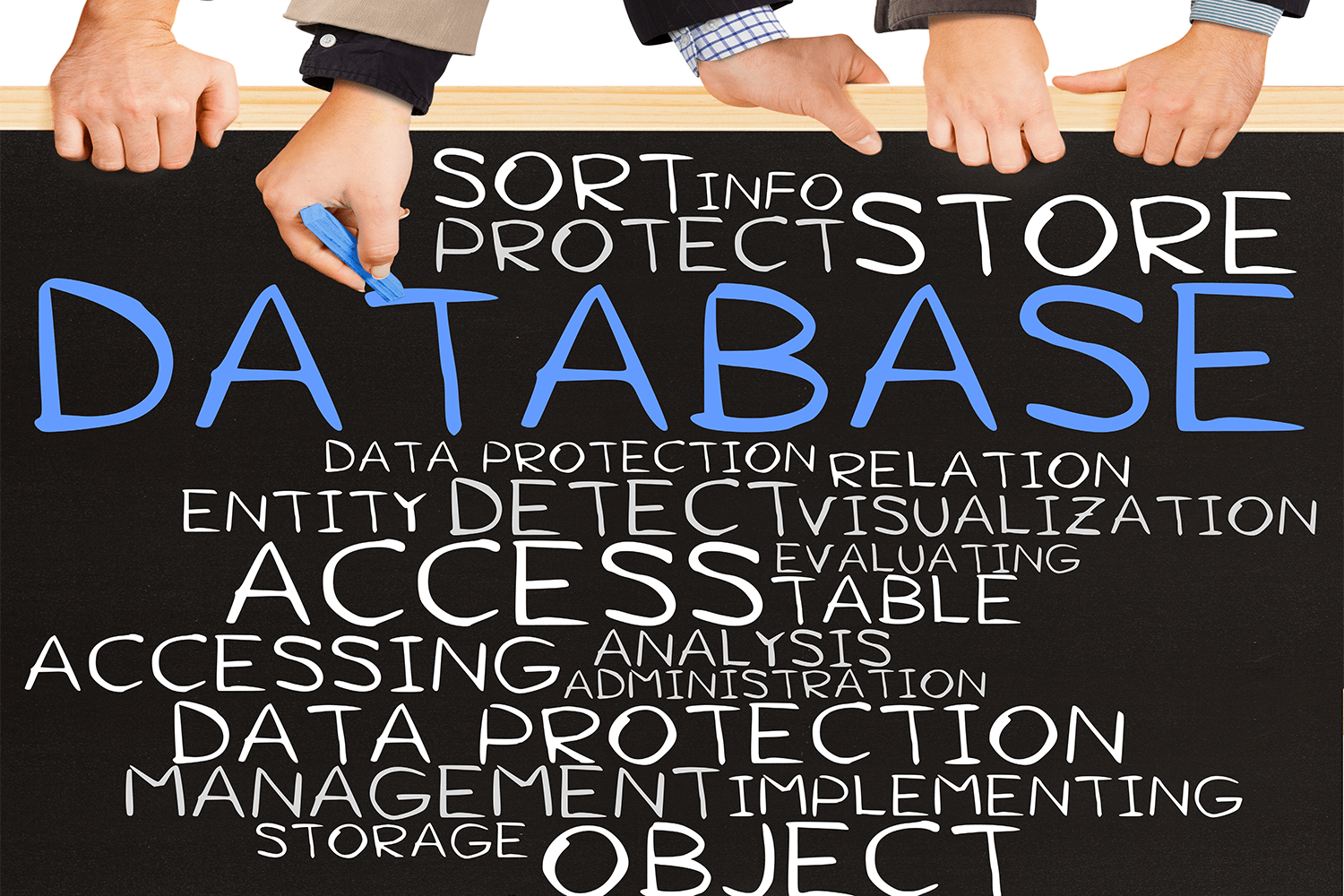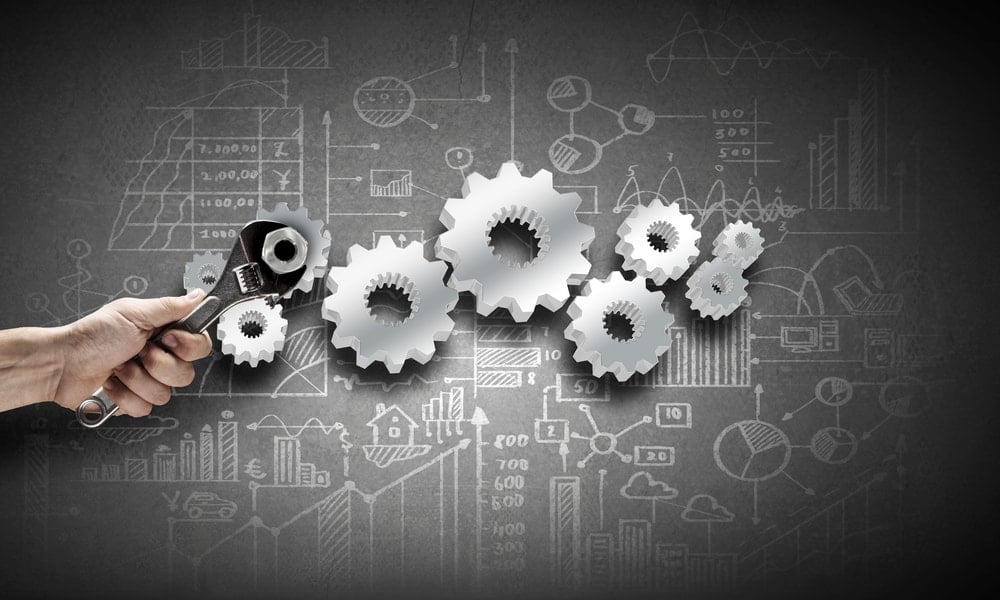近年、経営基盤の総合的な強化を目的として「ERP」を導入する企業が増加傾向にあります。そこで本記事では ERPの概要や基幹システムとの違い、近年主流となりつつあるクラウドERPについて解説します。 レガシーシステムの刷新やクラウドマイグレーションを検討している企業は、ぜひ参考にしてください。
ERPとは
ERPは「Enterprise Resource Planning」の略称で、人的資源・物的資源・資金・情報などの経営資源を一元管理する経営管理手法です。 組織の基盤となる経営資源を一元的に管理することで、事業活動の合理化を図ることを目的とします。本来、ERPはこのような経営管理手法の概念を指す意味合いでしたが、近年では企業の基幹業務を一元管理する「統合基幹業務システム」を指して「ERP」と呼称するのが一般化しています。
経営管理手法としてのERPは、1970年代に提唱された製造分野における 生産管理 手法の「MRP(Material Resource Planning)」をベースに発展させたものです。MRPは「資材所要量計画」とも呼ばれ、資材と在庫の総量に注目して生産計画を立案・策定する管理手法を指します。このMRPの管理領域を「生産工程」から「企業経営」へと発展させたものが経営管理手法としてのERPです。
ITシステムとしてのERPが誕生したのは約半世紀前のことであり、ドイツに本社を置くSAPが1973年にリリースした「SAP R/1」が世界初のERP製品といわれています。その後、1990年代に日本でもERPシステムの導入ブームが起きたものの、高額な導入費用や商習慣のミスマッチなどから大企業以外では普及するに至りませんでした。しかし、 近年になるとクラウドERPの誕生によって導入障壁が取り除かれつつあり、中小企業でもERPシステムの導入が加速しています。
日本にERPが広まった背景

ERPが日本で注目され始めた背景には主に3つの理由があります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
人的ミスを減らす
これまでの企業では、人的資源、物的資源、資金などの企業活動の根幹をなす経営資源が部門別に管理されており、人為的な手法でそれらのデータが共有されていました。こうした状況においては、部門間における情報共有に時間がかかるばかりではなく、共有すべき情報の抜け漏れが発生するなど、効率的な部門間連携を図ることが困難でした。
しかし、 ERPの導入によって部門別に管理していた経営資源が一元管理されることで、部門間における情報共有がスムーズになり人的ミスの削減を図ることができるようになりました。 例えば、経営者が売上データを確認したい場合、これまでは営業部門が個別に情報提供する必要がありましたが、その情報共有がERP上で直接できるようになります。
海外拠点との円滑な情報共有を図る
海外に支店を置いている企業にとって、最新の経営資源をリアルタイムで把握しておくことは重要です。国内本社と海外支店における情報共有を人的手法ばかりに頼ると、海外拠点の状況把握に遅延が発生します。リアルタイムで状況把握ができないと、経営における重要な意思決定の遅れや、国内本社と海外支店との間における円滑なコミュニケーションが阻害される事態が生じてしまいます。その結果として、経営を継続していく上での大きなダメージにもつながりかねません。
そのため、 グローバル市場に経営活動の拠点を設けている企業は、ERPの活用を通じて海外拠点における経営資源の状況をリアルタイムで把握することが重要な課題となってきました。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)の実現
DXとは既存業務のデジタル化を通じて業務の効率化を図るだけではなく、デジタルを活用しこれまでにない新しい付加価値や顧客体験を創出することを意味します。近年、 DXが新たな競争優位性を生み出すものとしてさまざまな企業で注目されており、DXを実現するための一環としてERPの導入が重要視されています。
例えば、ERPが導入されると、ECサイトである商品が売り切れになった場合、自動的にその商品の発注や生産を指示し在庫が補充され、ユーザーにメールなどの通知を自動発信することが効率的かつ迅速にできるようになります。ERPが導入されていない場合、在庫システムや発注管理システムが別々にデータを管理しているため、このような効率的な対応は難しいでしょう。
ERPの導入によって実現できること

ERPは企業が健全な経営を維持し利益を出し続けて行く上で大きな役割を果たします。ここではERPで実現できる大きな4つの側面について詳しく見ていくことにします。
情報の一元化
ERPは生産、在庫、販売、購買、会計などの経営資源を一元管理することによって情報を集約できます。 これによって部門間での情報格差を是正できるようになり、効率的な情報共有や迅速な意思決定が可能となります。
これらの経営資源が別々のシステムで構成されており、かつデータが孤立して管理されていると、アクセスできる情報が部門によって制限されていたりアクセス自体ができないことが発生します。そうすると、欲しい情報があっても他部門へ情報共有を依頼することになり、業務が非効率になるばかりではなく迅速な意思決定の障害要因となってしまいます。
生産性の向上
ERPの導入は労働者一人当たりが生産する付加価値を向上させることができます。 EPRがあれば他部門に依頼することなく自分で複数の情報を集約できるため、短時間で業務をこなすことが可能となります。
あるいは、ERPがあればそのような業務自体を自動化させ、従業員はより経営にとって重要な分析業務や意思決定に労働力を投下することも可能となります。これまで必要とされていた労力を節約し、更なる労働生産性を向上させることがERPの目的ともいえます。
スピーディーかつ的確な意思決定
ERPを導入することでさまざまな情報が一元管理されるため、情報の透明性が確保され部門間での情報の隔たりをなくすことができます。
欲しい情報の内容に応じて利用するツールが異なったり、そもそも情報へのアクセスが制限されたりする状態では、スピード感のある意思決定ができなくなります。例えば、情報が一元管理されていないケースでは、取得したい情報に応じて利用するツールが異なるため、担当者によって取得したデータに差分が生じやすくなります。また、情報へのアクセス制限が設けられているとデータ取得できる担当者にその都度依頼しなければならず、連携における抜け漏れが発生しやすくなるでしょう。こうしたことから、ERPは迅速に意思決定を行い他社より優位に立つ上で重要です。
内部統制の強化
従業員が取得できるデータが複数のツール間に分散していると、アクセス管理をツール毎にしなければなりません。これでは、効率的なセキュリティ管理を施すことができません。このような状況下では、新しい従業員が入社するとツール毎にアスセス権を設定し、退社するとそれぞれアクセス権の削除が発生します。当然、設定漏れが発生するリスクが起きやすくなり、必要のないアカウントの削除漏れも発生しやすくなります。
ERPの導入には注意点もある

ERPの導入時には最初の障壁としていくつかの注意点があります。ここでは多くの企業がERP導入時に直面する注意すべき点について2つピックアップします。
サービスが多く何を選んだらよいか分からない
ERPとして販売されている製品は数多くあります。ERPが提供する機能は多岐にわたるため、自社に最適な製品を選択する際には専門的な知識や経験が必要です。
また、業務のプロセスや課題点に対する深い理解が不可欠です。ERPをパッケージとして販売している製品の多くは初期費用に導入時の要件定義を含めたコンサルディングや技術的な支援も含まれているため、費用が高額になりがちです。導入後には運用保守のための費用やライセンスフィーも発生します。このようにERPの導入には製品の選択以外に費用も考慮しなければならないため、慎重な検討が必要なのはいうまでもありません。
セキュリティを強固にする必要がある
ERPを導入することによって情報が一元管理され業務の効率化など、大きなメリットがありますが、その一方でセキュリティを強固にしないと大きな損失を被るリスクも同時に発生します。ERPは1つのアカウントで顧客データ、原材料価格、売上データ、従業員に関する個人データなど、複数のデータにアクセスすることが可能です。そのアカウントが悪意のある第三者によって不正利用されると、機密情報の漏洩だけでなく顧客からの信頼を失い売上減少などの実質的な損失につながりかねません。
従業員の業務内容や職位に応じた適切なアクセス権の付与や不正アクセスを防止するための強固なネットワークセキュリティ対策を講じることが重要です。
基幹システムとは

基幹システムとは、財務会計や生産管理、 購買管理 、在庫管理、人事管理など、企業経営の土台となる基幹業務のデータを管理するシステムです。 代表的なものとしては、会計システムや人事給与システム、在庫管理システムなどが挙げられ、サーバーダウンやネットワーク障害が発生した際に、事業活動そのものに致命的な影響を及ぼすITシステムを基幹システムと呼びます。
たとえば、製造分野における生産管理では、実在庫に基づき資材の所要量を計算するMRP処理が行われます。MRPでは主に部品表と基準生産計画をもとに資材の所要量を算出し、在庫を引いて発注量などをコントロールします。こうしたMRP処理を効率的に実行するのが、生産管理システムや在庫管理システムといった基幹システムです。
基幹システムの導入によって実現できること

既に自社で基幹システムが導入されている企業もあるかと思います。ここでは基幹システムを導入することによって実現できることについて3つピックアップします。
業務効率化
基幹システムを導入することで 業務プロセス が簡略化され業務の一部は自動化されます。 これまで必要としていた工数の削減につながり業務の効率化を図ることができます。
例えば、店舗POSと連動した販売管理システムがあると、店舗POSで販売した商品内容や売上データがリアルタイムで販売管理システムに反映されます。このような販売管理システムがない場合、閉店後にExcelで売上情報を本社にメールで送るなどの業務が発生してしまいます。このような作業は非効率であり、状況に応じた迅速な意思決定も困難となります。
業務標準化(仕組み化)
基幹システムを通じた業務は一定の決まったプロセスを通じて実行されます。そのため、基幹システムがないときと比較して各業務のプロセスはより明確になり誰が担当しても同じアウトプットを期待することができます。
基幹システムがあるおかげで、担当者のスキルに依存することなく業務の実行が可能となり、担当者の変更や退社があっても別の担当者がすぐに対応できるメリットがあります。逆に基幹システムがなく手動作業が業務のメインとなるケースでは、業務プロセスを理解しているのは社内の限られた担当者のみとなってしまい、業務の属人化を招いてしまうリスクがあります。
人的ミスの削減
基幹システムの導入によって業務の一部が自動化されます。これによってデータの入力ミスや手順を間違ってしまうなどのヒューマンエラーを防ぐことが可能となります。 間違って入力したデータに基づいて意思決定をしてしまうと、誤った方針が示され取り返しのつかないことが発生することがあります。また、データを修正のために再入力するなど、二度手間になってしまうこともあり業務上効率的ではありません。
ERPと基幹システムの違い
ERPシステムと基幹システムの決定的な相違点は「データの管理領域」です。 基幹システムは基本的に財務会計や生産管理、人事管理といった企業経営の土台となる部門の業務データを管理します。一方で統合基幹業務システムとも呼ばれるERPは、その名の通り企業の基幹業務データを一元的に管理するソリューションです。つまり、基幹システムの管理領域は「部門」であり、ERPシステムの管理領域は「組織」であるという点が大きな違いといえるでしょう。
基幹システムをERP化するメリット
ERPシステムを導入する大きなメリットのひとつが「経営状況の可視化による意思決定の迅速化」です。 冒頭で述べたように、ERPは人的資源・物的資源・資金・情報といった経営資源の最適化を目指す経営管理手法であり、それを実現するためには財務会計・人事管理・購買管理・生産管理・在庫管理・販売管理といった基幹業務データを一元的に管理する必要があります。
基幹システムは基本的に各部門で個別管理されているため、部門を横断した情報共有が困難であると同時にデータのサイロ化を招き、組織の経営状況を的確に把握できません。ERPシステムは基幹業務のデータを1つのプラットフォームに集約するため、全社横断的な情報共有を可能にするとともに、経営状況を俯瞰的な視点から分析できます。そのため、経営状況の可視化による意思決定の迅速化に寄与し、変化が加速する市場に対応できる経営基盤を構築できます。
ERPの導入手順
ERPを導入する際は、一定の工程を経ると効率的です。「導入目的の明確化」から「運用開始」まで順を追って解説します。
1.ERPを導入する目的の明確化
何のためにERPを導入するのか、どの事業領域に活用するのかなど、経営ビジョンや事業目標に基づいて導入目的を明確化しましょう。 このプロセスを踏むことで、ソリューションの選定や導入ベンダーとの意思疎通が円滑になります。
2.導入ベンダーとERP製品の選定
ERPシステムは多種多様な製品がリリースされているため、自社に適したソリューションを選定するのは容易ではありません。また、システムの設計や実装を自社のリソースのみで賄うのは困難なため、導入から運用に至る全工程を総合的に支援するベンダーを選ぶ必要があります。
3.要件定義
ERPシステムに求める業務要件やシステム要件を具体化するステップです。 独自の機能を追加するアドオン開発は導入費用と開発期間の増大を招くため、自社の事業形態に必要な機能を見極める知見が求められます。
4.設計・開発
定義された要件に基づいてシステムを設計・開発します。 システムの設計や開発といった領域は基本的にベンダーの担当になるため、この間に操作マニュアルの作成や研修・トレーニングの実施、業務フローの再定義など、自社の運用体制を整えることが重要です。
5.テスト
システムのリリース前に全体のレスポンスやユーザビリティを検証するステップです。 一般的には機能単体の動作性を見る「単体テスト」、機能間連携における動作性を見る「結合テスト」、そして最後にシステム全体の動作性を検証する「総合テスト」という3ステップを実施します。
6.運用開始
ここまでのプロセスに問題がなければシステムの運用を開始します。 システムの構築はERPを最適化する手段であって目的ではないため、運用成果を最大化するためには継続的な運用プロセスの見直しや機器のメンテナンスなどが必要です。
近年はクラウドERPが主流に
近年、クラウドファーストの一般化に伴い、さまざまな分野で進展しているのがERPシステムのクラウド移行です。 経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」が差し迫るなか、さまざまな企業でレガシーシステムの刷新が重要課題となっています。しかし、オンプレミス環境にERPシステムを構築する場合は、数千万〜数億円の開発費用と年単位の開発期間を必要とするため、比較的コストと開発期間を抑えられるクラウド環境に移行する企業が増加傾向にあります。
ERPシステムは業務システムのなかでも非常に高度なセキュリティが求められるため、これまでクラウド移行を躊躇う企業が少なくありませんでした。しかし、 近年では「Microsoft Azure」や「Amazon Web Services」のように国際的なセキュリティ認証を得ているサービスもあり、金融機関のように厳格なセキュリティが求められる分野でもクラウドERPの導入が進みつつあります。
シームレスな業務改革を可能にする「Microsoft Dynamics 365」
ERPシステムのクラウド移行を検討している企業におすすめしたいのが「 Microsoft Dynamics 365 」です。Microsoft Dynamics 365はMicrosoftが提供するクラウドERPであり、顧客情報を統合管理する CRM 機能を有しているのが大きな特徴です。ERPとCRMのシームレスな連携による業務改革とビジネスの成長を実現したい企業は、Microsoft Dynamics 365の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
ERPは、人的資源・物的資源・資金・情報といった経営資源を一元管理する経営管理手法であり、その実現を支援するのが統合基幹業務システムとも呼ばれるERPシステムです。基幹システムが「部門」の業務データを管理するのに対し、ERPシステムは「組織」の経営データを管理領域とします。ERPシステムの刷新やクラウド移行を検討している企業は、ぜひMicrosoft Dynamics 365の導入をご検討ください。