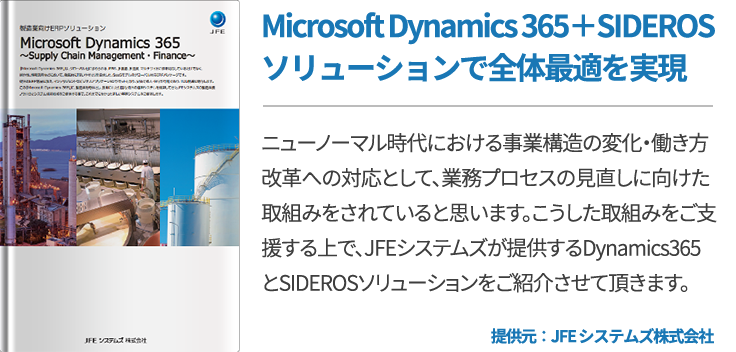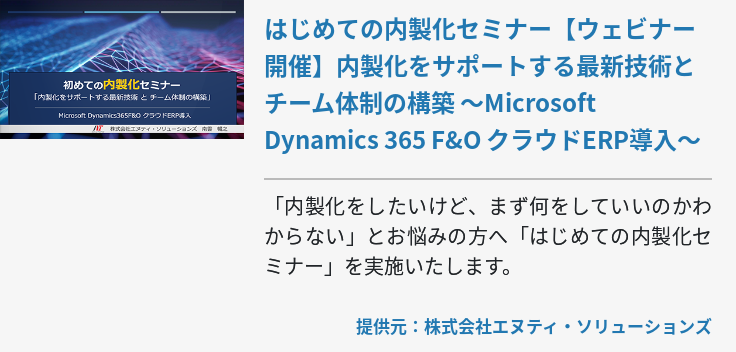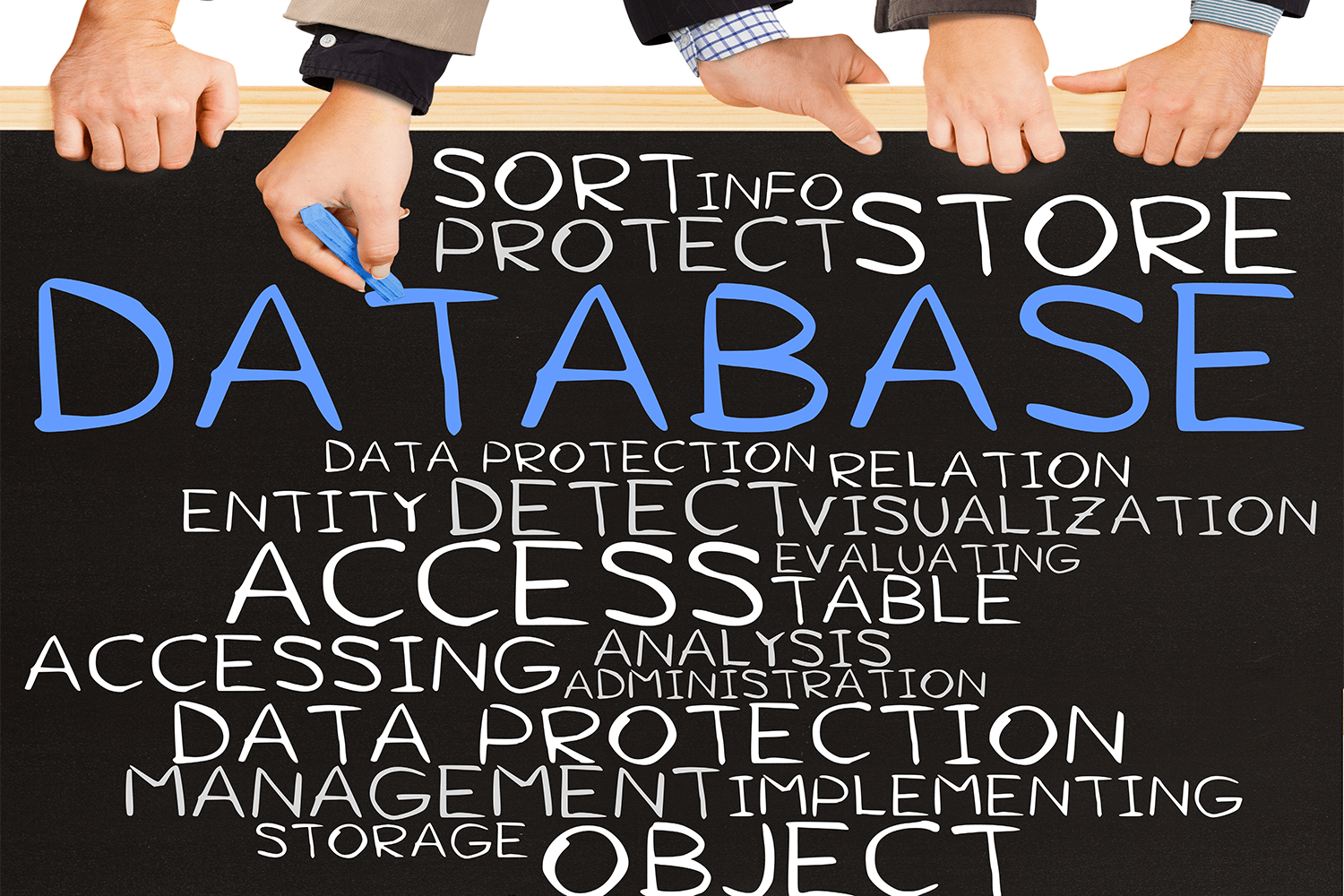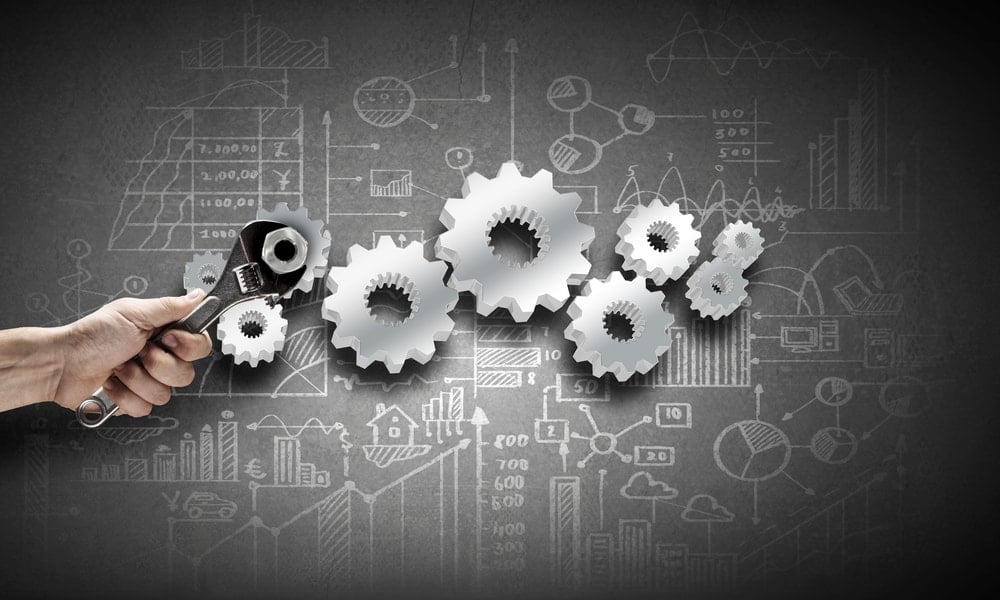ジャストインタイム、セル生産、パラメトリクス生産などなど、製造業では生産方式に関する用語が多く、その中の1つに「 MRP (Manufacturing Resource Planning) 」があります。 生産管理 手法として既に幅広く浸透している言葉ですので、改めて「MRP」と耳にする機会は少ないかと思います。
しかし一般用語として知っておきたい言葉の1つではあるので、本記事ではこの「MRP」について、よく間違えられるMRP2やERPとの違いも含めて詳しく解説していきます。MRPの管理手法を取り入れていない企業は、参考にしてください。
MRPとは?
MRPというのは「Material Resource Planning/資材所要量計画」の略です。日本語からその意味を読み解くと、 「生産活動に所要(必要)とする量の計画を立て、それにもとづいた仕入れ・生産を行う管理手法」 を意味します。考案されたのは1970年代の米国であり、当時は日本やドイツの輸出シェアが上昇する一方、米国のシェアが低下し日本や欧州の製造業が成長する中で米国製造業の国際雇用総力が低下する最中でした。
製造業において ビジネスを成功させる大前提ともいえるのは「在庫を持ちすぎないこと」 です。在庫は「現金化されていない資産」であり、極力在庫を持たないことでキャッシュフローを健全に保ち、管理コストの引き下げを手伝います。一方、在庫が不足している状態で調達や輸送に問題が生じた場合、欠品によって生産が停止し機会損失を招くため企業にとって大きなロスになります。在庫過剰や欠品を減らし、在庫管理の効率化を行うためにMRPが用いられます。
MRPの考え方は製造業の経営にかかせないもの
製造業ではしばしば「在庫とは経営そのもの」と表現されます。しかし在庫を過不足なく適正に管理することは、多くの企業において難しいことも事実です。特に経験と勘によって仕入れ量を決めているような企業においては、十中八九在庫は過剰もしくは不足の状態になってしまいます。
その際に活躍するのがMRPです。MRPはいうなれば 「BOM(Bill of Material/部品表)と基準生産計画をもとに資材調達を最適化するための計画」 であり、生産する部品や完成品それぞれの部品表を作成して、生産に必要な部品数と調達までにかかるリードタイムを明瞭にします。更に、部品ごとの原価や組み立て手順等を記載し、基準生産計画の基礎にすることで生産活動の効率化を図ったのです。
MRPを算出するために必要な要素
「必要なものを」「必要なときに」「必要なだけ」調達するための手法であるMRPを算出するためには、次の3つの要素が重要といわれています。
- 生産計画(MPS)
- 部品構成表(BOM)
- 在庫の情報
まずは、製品の生産個数や生産時期を計画します。生産計画はMPSとも呼ばれ、どの製品をいつまでに何個必要か計画を立てることで、次のBOMも作成できるという関係性です。
そして、製品をつくるためにどの部品がどのくらい必要か計算します。1つの製品をつくるのに必要な部品を一覧化したものをBOMと呼び、資材管理に使用します。そして、在庫数を管理し、在庫が少なくなると生産する流れが一般的です。
MRPとMRP2・ERPの関係

MRPは1970年代に米国で提唱され、現在も使用されている製品の管理手法です。1980年代にはMRP2が広まり、さらに1990年にはERPと呼ばれる進化した管理手法が登場します。
ここでは、MRPとMRP2、ERPの違いを解説します。
MRPとMRP2の違いは?
MRPは、製品の製造に必要な部品の個数を算出し、在庫状況を見ながら発注時期や数量を決定する手法です。
一方でMRP2は 製造資源計画 と呼ばれ、MRPに加えて 人員や設備などの生産資源も考慮して計画を立てる 手法です。
MRPでは、資材の調達や在庫管理の効率化を目指していたのに対し、MRP2では生産全体の効率化を考えて製品計画を立てています。
MRPとERPの違いは?
MRPは、生産管理、在庫管理を考える管理手法 ですが、 ERPは人・モノ・お金・情報を管理 する管理手法といった違いがあります。
ERPは、Enterprise Resource Planningの略で、日本語では 企業資源計画 と訳されます。これは、企業全体の基幹業務を統合的に管理するためのシステムです。
- 生産管理
- 在庫管理
- 人事管理
- 設備管理
MRP2では、これらの管理を行っていましたが、ERPではさらに、下記のお金に関する部分も含めて管理しようという管理手法です。
- 財務会計
- 販売管理
- 購買管理
MRPとジャストインタイムの関係
MRPは耳にしたことがなくても、「ジャストインタイム」と呼ばれる生産方式を耳にしたことがある方は多いでしょう。日本は世界的な製造業大国ですが、そうたらしめるきっかけになったのがジャストインタイムです。
これはトヨタ自動車創業者の豊田喜一郎が合理的経営の観点から導入した生産方式としてよく知られ、日本式の生産方式は米国製造業でも「JIT(ジット)」と呼ばれ取り入れられています。 ジャストインタイムの基本概念は「必要なものを、必要なときに、必要な分だけ調達する」 です。
1970年代の大量生産大量消費の時代では、単一製品を大量に生産することで数カ月先の生産計画も容易に見通すことができます。一方、多品種少量生産の時代が徐々に到来したことで、生産品目の増加によって資材の種類が増え、資材調達に関わる情報が膨大なものになります。それらの情報を全て人手で管理してしまうと計算や発注のミス・漏れによって企業に多大な損失を与えます。
一方、ジャストインタイムは情報の上流である顧客からの生産依頼をもとに基準生産計画を作成し、更に製品や部品ごとに必要となる資材量を割り出し、「何が、いつまでに、どれくらい必要なのか?」を明確にして調達の最適化を図ることで、効率的な生産活動を支援します。つまり、MRPは今では当たり前のジャストインタイムを実現するために欠かせない管理手法なのです。
MRPを導入するメリット

MRPは、生産計画にもとづいて必要な資材を必要なときに調達するシステムです。導入することで、以下の4つのメリットを得られます。
- 在庫リスクの軽減と適正管理
- 資材コストの削減
- 顧客サービスの向上
- 業務効率化・生産性の向上
この4つのメリットについて詳しく解説します。
在庫リスクを軽減して適正に管理できる
MRP導入の最大のメリットの1つは、 在庫リスクの軽減と在庫の適正な管理 です。従来の経験や勘に頼った在庫管理では、過剰在庫や欠品といった問題が発生しやすくなります。過剰在庫は、資金繰りの悪化や保管コストの増加、商品の陳腐化など、多くのリスクをもたらすでしょう。そして、欠品は 顧客満足度 の低下や売上機会の損失につながります。
またMRPは、過去の販売データや生産計画にもとづいて必要な資材を必要なときに調達するため、過剰在庫や欠品を最小限に抑えられます。 必要なものだけを必要なタイミングで調達することで、在庫コストを大幅に削減し、資金効率を向上 させることが可能です。
さらにMRP導入によって在庫状況が可視化され、在庫の異常な動きをいち早く察知し、適切な対応が取れます。
資材コストを削減できる
MRP導入のもう1つの大きなメリットは、 資材コストの削減 です。
MRPは、必要なものだけを必要なタイミングで調達するため、過剰在庫を大幅に削減可能です。在庫を管理するコストを削減することで、企業利益の向上につながります。
またMRPの手法により、必要な資材をまとめて発注できます。 大量発注による割引や、複数の仕入れ業者からの見積もり比較 などにより、資材をより安く調達ができるようになるでしょう。さらに、適切な在庫管理で廃棄コストの削減も可能です。
顧客サービスの質を向上できる
MRP導入は、 顧客対応の質を向上させられる というメリットもあります。MRPによって、製品の安定供給が可能になります。そして、顧客は必要な製品を必要なときに手に入れられるため、企業の信頼度が向上します。
また、部品の安定供給により、納入納期の短縮や品質を向上させることもできるでしょう。この改善は顧客満足度向上につながります。顧客満足度の高い企業は、顧客ロイヤルティを高め、リピーター獲得や新規顧客獲得に有利になります。
さらにMRPは、顧客からの受注情報をリアルタイムに反映することで、迅速な対応が可能です。顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応でき、さらなる満足度工場が期待できるでしょう。
業務効率化・生産性向上につながる
MRPの導入は、 業務効率化と生産性向上ができる点 もメリットです。MRPは生産に必要な資材や部品の適切な管理を可能にし、在庫の最適化を実現します。これにより、生産計画や調達プロセスが効率化され、生産ラインの停滞や欠品のリスクが軽減されます。
さらに、生産プロセス全体を見通しやすくし、リードタイムの短縮や生産計画の精度向上を促進します。その結果、企業は生産性を向上させるだけでなく、顧客サービスの向上や競争力の強化にも貢献するでしょう。
このように多くのメリットが有るため、MRPが多くの企業で有効な管理手法として活用されています。
MRPを導入する際のデメリット・課題

MRP導入は、生産計画の精度向上や在庫管理の効率化など、多くのメリットをもたらします。しかし、導入にはいくつかのデメリットや課題も存在します。
導入コストがかかる
MRPシステムの導入には、 ソフトウェアの購入費用や導入コンサルティング費用、システム運用のための設備投資 など、初期費用がかかります。また、システムの運用には、保守費用や運用管理のための人件費などのランニングコストも発生します。
これらのコストは、企業規模や導入するシステムの規模によって異なりますが、中小企業にとっては大きな負担となるでしょう。
現場の協力が必要になる
MRPシステムは、正確な情報にもとづいて動作するため、 現場からの正確なデータ入力が必要 です。また、生産計画や在庫管理の 業務プロセス をMRPシステムに合わせて変更する必要もあります。そのため、現場の従業員がシステムの使い方を理解し、積極的に協力することが重要です。しかし、現場の抵抗や理解不足によって、システムがうまく活用できないケースも少なくありません。
データの精度が低い場合、MRPシステムから算出される情報も不正確になります。そして、生産計画や市場環境の変化に迅速に対応できない場合、システムが機能しなくなる可能性があります。
これらの課題を克服するためには、導入前に十分な検討を行い、導入後の運用体制を整えることが重要です。
自社に合ったMRPシステムはどう選ぶ?
近年、製造業における効率化は必須課題となっており、その実現に役立つツールとしてMRPシステムが注目されています。しかし、MRPシステムといっても、機能や価格はさまざまです。自社に合わないシステムを選んでしまうと、期待通りの効果を得られず、無駄なコストを発生させてしまうでしょう。
そこで、ここからは自社に合ったMRPシステムを選ぶための5つのポイントをご紹介します。
導入目的に合っているか
まず、自社のMRPシステム導入目的を明確にすることが重要です。 目的が明確であれば、目的に合致した機能を持つシステムを選べます。
例えば、在庫管理の効率化が目的であれば、多様な在庫管理機能を備えたシステムを選び、生産計画の精度向上が目的であれば、高度な生産計画機能を備えたシステムを選ぶ必要があります。以下の代表的な機能が備わっているMRPシステムを選びましょう。
- 部品表(BOM)管理機能
- 在庫管理機能
- 生産計画機能
- スケジュール管理機能
- レポート機能
生産手法に合っているか
MRPシステムは、生産計画や在庫管理を効率化するツールですが、その効果は、 自社の生産手法と合致しているか どうかによって大きく左右されます。
例えば、自社が受注生産方式を採用している場合は、顧客からの受注に合わせた生産計画が必要です。受注情報をMRPシステムに連携し、リアルタイムで生産計画を更新できる機能が備わったシステムを選ぶとよいでしょう。
一方、自社が大量生産方式を採用している場合、安定した生産計画を立てることが重要です。そのため、過去の生産実績にもとづいて、最適な生産計画を立てられる機能が必要となります。
導入コストは予算内か
MRPシステム導入の前に、 コストが予算に収まっているか必ず確認 しましょう。導入コストは、システムの規模や機能、自社の規模によって大きく異なります。導入費用だけでなく、ランニングコスト(保守費用、運用費用)も考慮する必要があります。
無料トライアルや無料試用版を利用して、実際に使い勝手を確認しながら、予算内で導入できるシステムを選びましょう。
サポート体制が充実しているか
導入後のトラブルや運用に関する疑問を解消するために、充実したサポート体制が不可欠です。
- 導入後のサポート体制は充実しているか
- 問い合わせ窓口は複数用意されているか
- 迅速な対応が期待できるか
- ユーザーコミュニティやセミナーなどが開催されているか
上記のような点を事前に確認しましょう。
十分な導入実績があるか
導入実績が豊富なシステムは、導入後のトラブルが少なく、安定稼働が期待できます。また、自社と同業種での導入実績があれば、よりスムーズな導入ができるでしょう。
導入実績は、システムベンダーのWebサイトや導入事例集などで確認できます。導入企業の声なども参考にするとよいでしょう。
MRPシステム導入時のポイント
今では「MRPシステム」という名目でシステムが導入されることは少ないでしょう。ほとんどの場合「生産管理システム」として、MRPの役割に加えて生産の工程管理や品質管理、販売管理や出荷管理など幅広い業務をカバーするためのシステムとして導入・運用されています。では、製造業がMRPシステムないしは生産管理システムを導入するにあたり、注意すべきポイントとは何でしょうか?
ポイント1.BOMの整理
MRPではBOM(部品構成表)に従って生産に必要な部品と資材の数量を計算します。BOMはいわばMRPの生命線なので、MRPシステム導入以前にBOMがしっかりと整理されていなければMRPシステムも機能しません。 製造部門において各部品が「いつ、どれくらい必要なのか?」を明確化しましょう。
ポイント2.部門間コミュニケーション
MRPシステムを導入しても生産活動はいつも計画通りに進むわけではありません。特に顧客都合の仕様変更・発注変更・計画変更は常にイレギュラーで発生するものなので、それらへの緊急的な対応が必須です。MRPシステムは変更に弱いシステムと一部ではいわれていますが、その点は製造・設計・品質管理・在庫管理・資材購買・営業などの 部門間で綿密なコミュニケーションを取り、変更を即座に反映させるようにしてカバーしていく必要があります。
ポイント3.在庫管理体制の整備
MRPシステムは現時点の在庫量から、将来的に生産に必要となる在庫量を予測します。しかし、在庫管理体制自体に問題があり、在庫数などを正確に管理できていない状態ではMRPシステムがいくら優秀でも機能しません。それでは在庫に過不足が生じるので、MRPシステムを導入する意義も失われてしまいます。だからこそ、 MRPシステム導入時はしっかりとした在庫管理体制が重要です。
MRPの運用方法

MRPは、必要な資材を必要なときに必要な量だけ調達するための生産管理システムです。以下の3つのステップで運用されます。
- 生産計画の作成
- 総必要量の計算
- 在庫の発注
それぞれのステップについて詳しく解説します。
1.生産計画の作成
MRPの運用における最初のステップは、 販売予測に基づいて製品の生産量と生産スケジュールを決定する ことです。過去の販売データや市場動向などを分析し、将来の需要を予測します。
そして、販売予測にもとづいて、どのくらい製品をつくるのかを考え、必要な生産量を決定します。生産量が決定したら、生産量にもとづいて、具体的な生産スケジュールを作成します。
2.総必要量の計算
続いて、生産計画にもとづき、製品構成表(BOM)を用いて必要な部品や原材料の総必要量を計算します。総必要量は、以下の式で計算されます。
総必要量 = 必要生産量 × 部品使用量(+予備)
必要生産量は 生産計画で決定した生産量を表し、部品使用量:は、製品構成表(BOM)に記載されている部品の数を指します。この2つが分かれば、総必要量を求めることが可能です。製品の不備や廃棄分を考慮し、予備分も計算に含めましょう。
3.在庫の発注
最後に、現在の在庫量と総必要量を比較して、不足している部材や材料を発注します。発注するときには、以下の要素を考慮しましょう。
- 発注量:総必要量から現在の在庫量を引いた数量
- 発注時期:リードタイムを考慮して、必要な時期に発注する
- 発注先:価格、品質、納期などを考慮して、最適な発注先を選択
MRPからERPへの発展
通説として、MRPという生産管理手法は次に「MRP2」に発展し、最終的に「ERP」へ行き着いたといわれています。 MRP2は基準生産計画とBOMによって効率化される生産活動の管理項目を、資材だけでなく「人材・設備・製造リードタイム」など生産に関わる全ての能力に発展させ、より総合的観点から生産活動を管理します。
更に ERPとは、「Enterprise Resource Planning:エンタープライズ・リソース・プランニング」の略であり、MRP2の概念を更に発展させ、管理項目を経営全体に行き届かせるための管理手法です。 今ではERPといえば、「生産・財務・会計・人事・販売・調達など基幹業務と呼ばれるプロセスを効率化するための統合システム」と認識されています。
ERPで基幹系システムを統合することで、各システムで生成されるデータを統合し、分析することで経営の最適化を図ることが可能です。
まとめ
本記事ではMRPについて詳しく解説しました。MRPは現在の製造業でも欠かせない管理手法ですし、多くの生産管理システムやERPに機能として組み込まれています。MRPがなければ効率的な生産活動もあり得ません。この機会に、自社内においてどこでMRPが実施されているのか?を考えてみてください。
そして、MRPの管理手法を取り入れていない企業は、生産計画を作成し、1製品の作成に必要な部品数の把握、在庫を発注という3ステップを念頭に置いて実践してみてください。