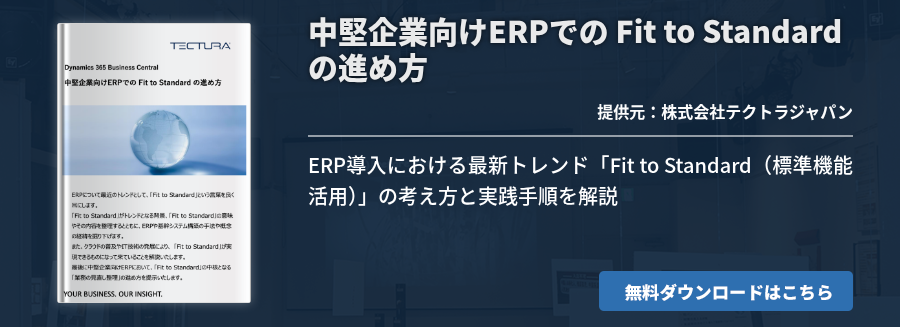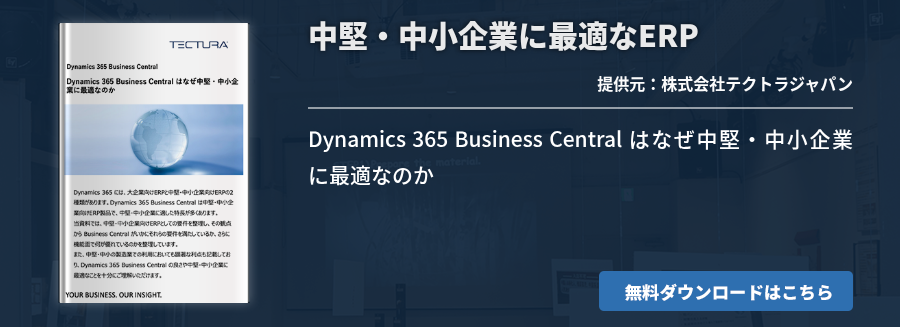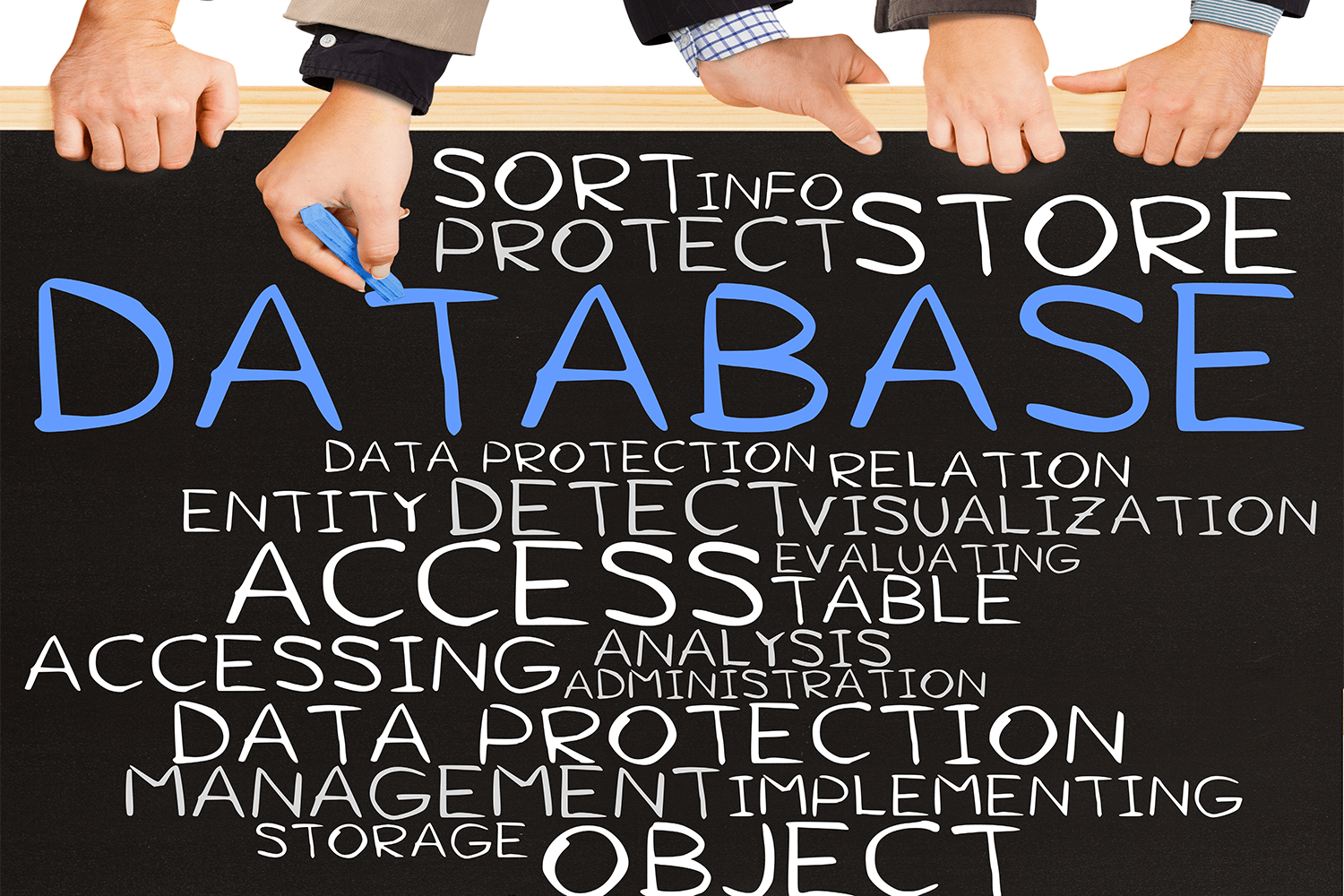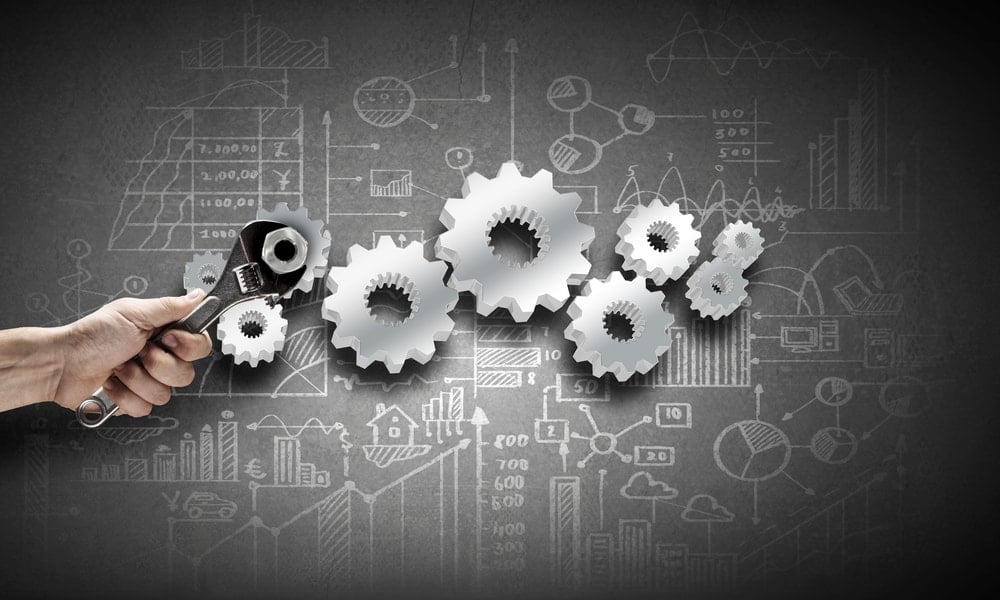Fit to Standardとは、ERPなどの導入にあたり、企業の業務プロセスをシステムの標準機能に合わせる形でアプローチする手法のことです。導入期間の短縮や開発コスト削減といったメリットがあり、近年注目を集めています。本記事では、この手法の概要や注目されている背景、メリット、注意点などについて解説します。
Fit to Standardとは?注目される理由と導入背景
「Fit to Standard(フィット・トゥ・スタンダード/F2S)」とは、システムやソフトウェアの導入手法のひとつで、企業の業務プロセスをシステムの標準機能に合わせるというアプローチをとります。この手法ではカスタマイズやアドオン開発を極力行わず、システムの標準機能を最大限活用することを理念としています。
近年、ERP導入を目指す企業のあいだで、この Fit to Standard が注目を集めています。その背景として、以下の2つの理由が挙げられます。
- ERP導入時にアドオン開発が増えると、費用や時間がかかってしまう
- ERPシステムが進化しており、デフォルトでも多様な業務に対応できるようになっている
日本企業の中には、ERP導入にあたり「既存の業務の進め方をできるだけ変えたくない」と考えるところも少なくありません。しかし、海外製のERPをそのまま自社業務に当てはめると無理が生じる可能性があり、新システム下でも既存の業務フローを維持したい場合、カスタマイズやアドオン開発での対応が求められます。
かといって、カスタマイズやアドオン開発が増えると、それだけ導入にかかるコスト・時間も増加します。柔軟なシステム変更やバージョンアップが難しくなる点も、アドオン開発に依存するデメリットです。
また、近年のERPシステムは汎用性の高い機能を標準で備えており、わざわざ独自の調整を加えずとも、さまざまな業務ニーズに応じられるようになっています。こうした事情から、従来の開発による調整を前提とするアプローチに限界が見え、より合理的な Fit to Standard の考え方にシフトしつつあります。
従来のFit & Gapとの違い
「Fit & Gap」では、システムの標準機能で現行業務に適応できる部分(Fit)と、乖離している部分(Gap)を洗い出し、自社要件に対するシステムの適合度を分析します。可能な範囲で業務プロセスをシステムに寄せることもありますが、基本は「システムを業務に合わせる」というスタンスであり、Gap部分を必要に応じてアドオン開発などで補完する点が、Fit to Standard との大きな違いです。
従来、ERPの導入シーンでは、この Fit & Gap の考え方が主流とされてきました。しかし、この手法は自社の業務要件に柔軟に対応しやすい一方で、開発によるコスト増や導入期間の長期化といったデメリットも抱えていました。また、カスタマイズを繰り返すことで、システムが複雑化・ブラックボックス化しやすい点も課題でした。
この点、Fit to Standard は上記のような課題が生じにくい手法といえます。
Fit to Standardの主なメリット
アドオン開発が少ないため、導入期間やコストを短縮できる
カスタマイズやアドオン開発を最小限に抑えることから、短期間・低コストでの導入が可能です。これにより、Fit & Gap と比較して大幅に導入プロジェクトを効率化できます。
最新機能の利用と拡張性の向上
Fit to Standard は、特にクラウドERPとの相性が良く、ベンダーが提供する最新機能をタイムリーに活用できます。大規模な改修に追われずにシステムを最新状態に保ちやすく、オンプレミスと比較して導入コストや運用面でも柔軟性が高まる点が特長です。
シンプルなシステムの導入による保守性の向上
アドオン開発を極力実施せず、システム本来の機能を最大限に活用するため、システムのシンプルさ・健全さが保たれます。これにより保守性の向上が期待でき、運用リスクを抑えられます。
業務改善につながる
システム導入にあたり、業務プロセスを見直す過程で業務が可視化されます。それをもとに分析を行い、業務プロセスの標準化や属人化の解消を図れます。
グローバル経営の促進とガバナンスの強化
Fit to Standard は、世界の主要ERPベンダーが推奨する導入手法です。標準機能を活用することで、海外拠点とのシステム連携やグローバル展開にも対応しやすくなります。導入コストや期間を抑えつつ、業務プロセスの一貫性を確保できる点は、柔軟な経営体制を目指す企業にとって大きな強みとなります。
Fit to Standardがなかなか進まない企業の特徴
- 従業員が既存の業務フローを変えたくないと考えている
- 従業員がシステムを使いこなせない
- 業務の性質上、ERP標準機能をベースにした業務プロセスに変更しにくい
特に、これまでの慣習に対するこだわりが強い企業や、各業務部門との合意形成に時間がかかる企業の場合、スムーズに新しいシステムを取り入れるのは困難でしょう。日本的な性格が強い企業では、新システムの導入に抵抗を覚える従業員も少なくありません。Fit to Standard を効率よく進めるためには、導入までの各フェーズの要点を押さえることが大切です。
Fit to Standard導入を成功させるための注意点
ERPの導入フェーズは、大まかに以下の流れを汲みます。各フェーズにおける注意点を意識することが、 Fit to Standard の成功の鍵です。
- 業務整理
- 要件定義
- 適合判断
- 調整
特に重要なのは、最初の業務整理です。既存の業務プロセスを変えずに新しいシステムを取り入れると、システムの機能と業務内容に齟齬が生じる可能性があります。とりわけ Fit to Standard では、機能を極力カスタマイズせず業務改革を行うため、まずはデフォルトのシステムに合わせた新しい業務フローを組み立てることが大切です。
中核業務はERP標準機能をそのまま使う
中核業務を可能な限りERP標準機能で回せるようにすることは、特に困難であり重要なポイントです。そのために必要なのが、業務整理です。企業内だけでなく、対顧客の課題も洗い出す必要があります。
標準機能ではどうしても難しいと思われる部分だけ、そのほかの手段を頼るようにしましょう。自社だけでERP導入に向けた業務整理が難しい場合は、ERPの導入や Fit to Standard に精通した支援企業を頼るのも手です。
クラウドERPやローコードツールを組み合わせるのも手
業務整理を実施した結果、プロセスの異なる部分が明らかになれば、その部分をベンダーに提示し協議を行うことになります。ベンダーの変更案でも採用が難しい場合、別のクラウドERPとの連携やローコードツールの活用を検討しましょう。
異なるクラウドERPとの連携は、必要に応じて連携を切ったり、より優れたサービスへ乗り換えたりできるメリットがあります。アドオン開発に頼ることなく機能を拡張できる点もポイントです。
一方、ローコード(またはノーコード)ツールは、開発業務が属人化しにくいメリットがあります。社外に発注せずスピーディーに開発しやすい点も、ローコードツールを活用するメリットのひとつです。システムが複雑化し、レガシー化してしまうことを予防するのにも寄与します。
業務整理を支援する「業務改善&RFP作成サービス」の活用
テクトラの「業務改善&RFP作成サービス」は、Fit to Standardに欠かせない業務整理を専門コンサルタントが支援するサービスです。クライアントのDX推進に向け、柔軟で将来性のあるシステム構築を支援できる点が特長です。
特に、「既存のERPシステムから新しいERPシステムへ移行させたい」「新事業を立ち上げるにあたり、新業務に対応できるシステムを構築したい」「導入費用・サポート費用をできるだけ抑えてERPシステムを導入したい」といった場面で役立ちます。このような課題を感じている方は、ぜひ「業務改善&RFP作成サービス」の活用をご検討ください。
まとめ
Fit to Standard は、企業の業務をシステムにフィットさせる手法を指しますが、単なる導入手法にはとどまりません。ローコストで業務改革や標準化、ガバナンス強化などを一気に推進する手段となり得ます。
導入前に業務整理を行い、導入システムと業務内容に隔たりを生じさせないようにすることが、効率的に業務プロセスを見直すポイントです。ERP標準機能のみで対応が難しい場合は、ローコードツールの活用やコンサルタントへの相談なども検討しましょう。