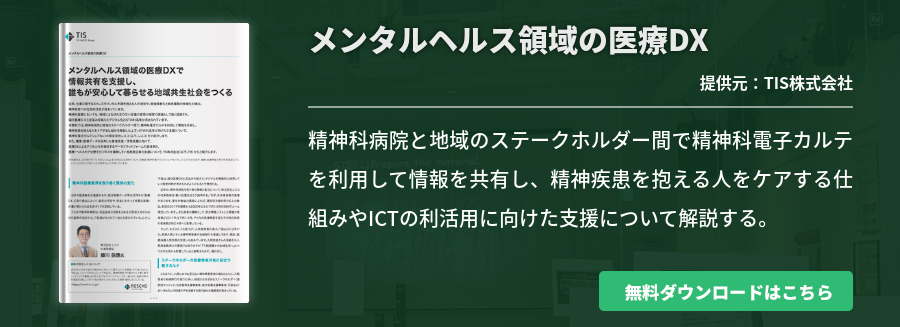メンタルヘルスケアとは?
メンタルヘルスケアとは、精神的な健康の維持・向上を目的とする包括的な取り組みを意味します。「Mental health」は「精神的健康」や「心理的健康」と和訳される概念であり、単に精神やこころの疾患がないことではありません。
現代日本はストレス社会と呼ばれて久しく、厚生労働省が公表した「令和6年版厚生労働白書」によると、「ストレスや不安感はまったくない」と回答した人はわずか10.7%で、「ストレスや不安感は時々ある」が46.2%、次いで「ストレスや不安感はある、またはかなりある」が23.1%となっています。さらに「何らかの対処をしている(服薬なし)」が12.2%、「市販薬を服薬している」が1.3%、そして6.5%は「病院にかかっている」と回答しています(※1)。
仕事や人間関係の悩み、あるいは将来への漠然とした不安など、さまざまな心理的負荷が積み重なることでメンタルヘルスに支障をきたす可能性があります。こうしたこころの問題を解消し、誰もが暮らしやすい社会を実現するために、厚生労働省では「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を進めています(※2)。
(※1)参照元:令和6年版 厚生労働白書(p.85)|厚生労働省
(※2)参照元:メンタルヘルスとは|厚生労働省
メンタルヘルスケアのポイント「4つのケア」
健康経営の一環としてメンタルヘルスケアを導入する企業も少なくありません。厚生労働省が策定した「職場における心の健康づくり」では、メンタルヘルスケアの重要な要素として以下の4つを挙げています(※3)。
(※3)参照元:職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~(p.7)|厚生労働省
セルフケア
セルフケアは、自分自身で心の健康状態を把握し、予防・対処するメンタルヘルスケアです。具体例として健康的な生活習慣を意識して精神疾患を予防する、内省によって感情や体調の機微を感じ取る、あるいは精神科医の書籍やカウンセラーの動画コンテンツなどでメンタルヘルスを学ぶといった方法が挙げられます。
ラインによるケア
ラインケアとは、組織のライン上にいる管理者が主体となって実施するメンタルヘルスケアです。ストレスや不安は可視化が困難で、自分自身で心の不調を認識できていない、あるいは何をするべきかわからないといったケースが少なくありません。管理者がいち早く異変を察知し、対策を講じることで従業員のメンタルヘルスを維持できる可能性が高まります。
事業場内産業保健スタッフ等によるケア
事業場内産業保健スタッフ等によるケアは、産業医や保健師、人事労務管理のスタッフなどが推進するメンタルヘルスケアです。メンタルヘルスケアに関する企画の立案、教育研修の実施、個人の健康情報の取扱い、職場環境の評価・改善、労働者・管理者からの相談対応、職場復帰の支援などを実施します。
事業場外資源によるケア
事業外資源によるケアは、外部の医療機関や保健機関のサービスを活用するメンタルヘルスケアです。たとえば精神科医や臨床心理士と連携し、従業員を支援するEAP(Employee Assistance Program)を構築できれば、メンタルヘルスに関する専門的な分野に柔軟かつ的確に対処できます。
メンタルヘルスケアにおける医療DXの必要性
DXは「デジタル技術の活用による変革」を意味し、医療分野でもクラウドサービスやAIなどの活用が加速しています。それにより、クラウド型のプラットフォームを活用した電子カルテの共有や遠隔カウンセリング、またはAIによるストレスチェックなど、先進的なメンタルヘルケアを実現できる点がメリットです。
とくに厚生労働省が提唱する「事業場外資源によるケア」では、医療機関や保健機関などのステークホルダーとの連携が欠かせません。外部の医療機関や保健機関とオンラインを介した情報共有や業務連携が可能になれば、地理的な制約に縛られることなく、高度なメンタルヘルスケアを多くの人々に提供できます。
メンタルヘルスケア領域での医療DX導入の課題
メンタルヘルスケアの分野で医療DXを推進するためには、乗り越えなくてはならない課題がいくつか存在します。なかでも重要度の高い課題が以下の3点です。
複数機関との連携のしやすさ
メンタルヘルスケアを進めるには、いかにして外部機関と円滑な連携を図るかが重要です。たとえば政府の医療DX推進本部が推進する「全国医療情報プラットフォーム」には、これまで各機関で個別に管理されていた電子カルテ情報や予防接種情報、レセプト情報などの医療データの一元化が進んでいます。メンタルヘルスケア領域においても、医療DXを実現するためには、こうした情報共有基盤の活用が不可欠です。
製品の使いやすさ
医療DXを推進する上で重要な課題となるのが製品の使いやすさです。国内では少子高齢化に伴って医療や福祉を必要とする人口が増加し続けるものの、医療現場は慢性的な人手不足に陥っています。医療現場の人々はITの専門家ではないため、操作が難しい製品では業務負荷の増大を招き、かえって効率化を妨げる要因になりかねません。そのため、システムの操作に高度なIT関連の知識を要求されず、なおかつサポート体制の充実した製品の導入が推奨されます。
高度なセキュリティ対策
数多くの機微な個人情報を取り扱う医療分野において、重要課題のひとつにセキュリティ対策への対応があります。たとえばクラウドサービスはパブリック環境でリソースを共有する性質から、セキュリティ上のリスクを危惧する声が少なくありません。従来の医療機関では、電子化を避けることでセキュリティリスクを低減していたという側面もあります。こうしたセキュリティ上の課題を解消するためには、厳格なセキュリティ要件に対応できるソリューションが必要です。
医療データ流通を推進するTISのヘルスケアプラットフォーム
医療DXを推進するためには、政府の施策と足並みを揃えた取り組みが必要になります。そこでおすすめしたいのが、TIS株式会社(以下、TIS)のヘルスケアプラットフォームです。TISのヘルスケアプラットフォームは、各医療機関に義務化されたセキュリティ要件に準拠しており、患者の医療データを安全に統合・共有できます。それらの医療データと、さまざまなサービスで個別に管理されている情報をさらに統合して管理する事ができます。それにより、メンタルヘルスケア領域の医療データを流通・活用する機能を補完し、医療DXの実現に貢献します。
まとめ
メンタルヘルスケアは、精神的な健康の維持・向上を目的とする取り組みです。健康経営の一環としてメンタルヘルスケアを導入する企業も多く、厚生労働省では「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」の4つが必要と示されています。
先進的なデジタル技術を駆使し、複数機関の医療データを統合的に管理できれば、地理的な制約のないメンタルヘルスケアを多くの人々に提供できます。そのためには医療DXの推進が不可欠であり、TISのヘルスケアプラットフォームのような情報共有基盤が必要です。