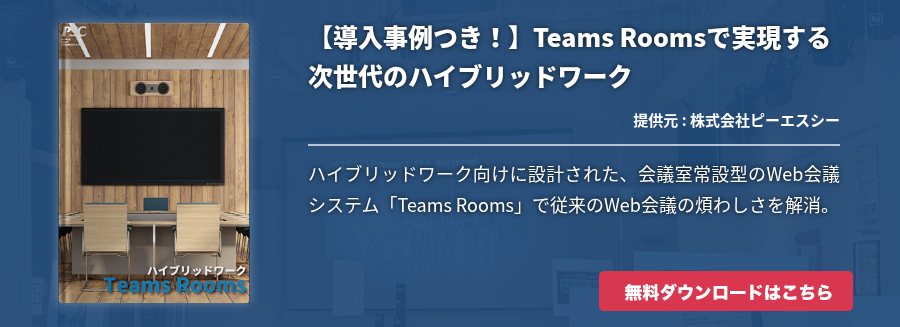コロナ禍での経験を通して、テレワークとオフィスワーク、それぞれに良し悪しがあることを実感した企業も多いのではないでしょうか。こうした中で、これら両方の働き方を取り入れたハイブリッドワークを導入する企業が増えています。そこで本記事では、ハイブリッドワークの特徴やメリット・デメリット、成功のポイントなどを紹介します。
ハイブリッドワークとは?
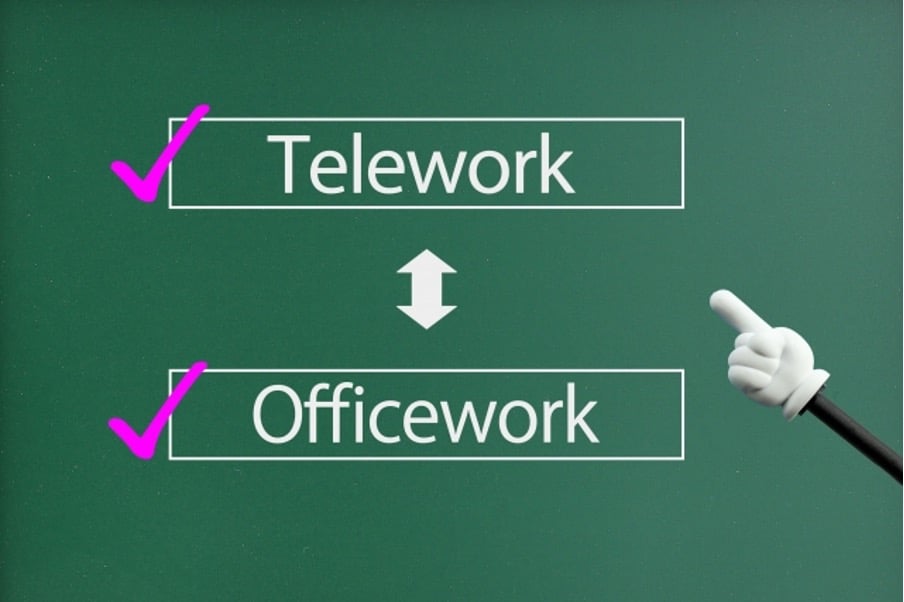
ハイブリッドワークとは、自宅などで働くテレワークと従来のオフィスワークを組み合わせた働き方を意味します。週3で在宅勤務、週2でオフィス勤務といった勤務形態が典型例です。
2023年8月に行われたハイブリッドワークに関する調査では、回答者のうち6割弱の企業がハイブリッドワークを導入しているという結果(※1)があります。これほどハイブリッドワークが普及したのは、新型コロナウイルスの感染防止策として、テレワークを導入する企業が増えたことが関係しています。
他方で、新型コロナウイルスの蔓延が落ち着き、オフィスワークが再び可能になる中で、テレワークの不便な点やオフィスワークならではの利点に目を向ける動きも出ています。
こうした流れから、テレワークとオフィスワークのどちらかだけを選ぶのではなく、両者のメリットをどちらも享受する働き方としてハイブリッドワークが注目を集めるようになりました。実際に、もっとも生産性が高い働き方としてハイブリッドワークを挙げる人の割合は8割弱にも及ぶという調査結果(※2)が出ています。
※1 参照元:
東洋経済 東洋経済オンライン読者にハイブリッドワークに関する調査を実施
※2 参照元:
ZDNET Japan 調査結果「最も生産性の高い働き方」はハイブリッドワーク
ハイブリッドワークのメリット・デメリット
ハイブリッドワークの最大のメリットは、社員のニーズに応じて働き方を調整できることです。
「同僚と直接コミュニケーションを取りたいからオフィスワークの方がいい」「一人で集中して働きたいからテレワークがいい」「普段はテレワークがいいけれど、週1程度は対面でミーティングをしたい」など、社員にはそれぞれ異なるニーズがあります。
ハイブリッドワークであれば、こうした多様なニーズへ柔軟に応えられ、モチベーションや生産性の向上、優秀人材の確保や定着率の改善などへつなげることが可能です。
他方で、ハイブリッドワークのデメリットとしては、特に急な業務への対応が難しいことが挙げられます。
ハイブリッドワークでは、誰が出社していて誰が在宅勤務しているのか、把握しにくい面があります。そのため、出社していると思った社員が実際にはいなかったり、急な会議が必要になってもチャットなどで連絡を回して調整することから始めなければいけなかったりと、不便なことも起きがちです。
また、テレワークにも共通することですが、社外からのアクセス増加に伴うセキュリティ対策や、勤怠管理・人事評価のしにくさなども課題として挙げられます。
ハイブリッドワークのメリット・デメリットや課題についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考にしてください。
関連記事: ハイブリッドワークとは?課題やメリット・デメリットを解説
ハイブリッドワークを成功させるためのポイント
ハイブリッドワークでは従業員同士の連携に難が生じやすくなります。また、情報漏洩などのセキュリティリスクは、企業にとって優先的に対策すべき課題です。こうした課題に対応し、ハイブリッドワークを成功させるには、以下の2つのポイントを意識することが大切です。
Power Platformを活用する
Microsoftが提供する Power Platform は、以下の3つのサービスから構成されるクラウドサービスプラットフォームです。
- Power Apps
- Power AutoMate
- Power BI
自動化処理やワークフロー作成、データ分析、ローコーディングのアプリケーション開発の機能を持ち、情報の共有や従業員同士の連携を高速化させます。
大手教育会社では、「業務の中断・終了における報告の作業負担が大きいこと」をテレワークならではの課題として捉え、早急に解決すべきこととして掲げていました。Power Platformでは、ローコーディングで勤怠管理システムを構築し、導入することが可能です。
プログラミングの工数が少ないため、短期間で開発でき、コロナ禍における働き方の課題に素早く対処できました。そして勤怠共有アプリケーション導入により、勤怠状況を逐一報告することなく、簡単な操作のみでテレワーク中の社員の勤怠状況が把握できるようになりました。
セキュリティ意識を高める
ハイブリッドワークを実施すると、ネット環境を通じたデータのやりとりや、自宅など上司の目が行き届かない環境で仕事をする機会が増えます。これに伴って増大するのが、情報漏洩などのセキュリティリスクです。
情報漏洩を防ぐには、オフィス以外でも安心して利用できるような、セキュリティ品質の高いツールの導入などが必要です。しかし情報漏洩は、悪意ある第三者からの攻撃以外に、社員が規則を守らずに機密情報を持ち出したり、うっかり記憶媒体を紛失したりすることでも起こります。不審なメールやWebサイトを不用意に開いてマルウェアに感染するといったこともよくある問題です。
そのため、ハイブリッドワークの導入に際しては、ツール面での対策と同時に、教育・研修を通して社員のセキュリティ意識向上に取り組みましょう。
ハイブリッドワークの成功にとって重要なその他のポイントについては、以下の記事をご参考ください。
参考ページ: ハイブリッドワークとは?課題やメリット・デメリットを解説
ハイブリッドワーク導入に向けたオフィス環境の構築方法

ハイブリッドワークの導入に向けて、オフィス環境やテレワーク用ツールの見直しをしてみてはいかがでしょうか。以下、3つの見直しポイントを解説します。
- フリーアドレスの導入
- コミュニケーション(雑談)スペースの設置
- ITツールの導入
フリーアドレスの導入
フリーアドレスとは、オフィスの座席を社員ごとに固定せずに、空いている好きな席で業務をするスタイルです。ハイブリッドワークの場合、出社するタイミングによっては「自分の周りには誰もいないけど、少し離れれば同僚が何名かいる」といった状況も考えられます。
孤立やコミュニケーション不足を避けるためにも、フリーアドレスを導入し、出社状況に合わせて席を選んでもらうといいでしょう。
コミュニケーション(雑談)スペースの設置
ハイブリッドワーク導入後は、コミュニケーションスペースの設置も有効です。テレワーク中はコミュニケーション不足に悩む社員が多く、業務やプライベートのことでも同僚に相談しにくい環境にあります。また、せっかく出社しても誰とも話さずに帰ってきてしまうのでは、「家で仕事をするのと変わらない」と出社した意味があまり感じられません。
こうしたコミュニケーション不足を解消するためには、会社側が専用スペースを用意して、コミュニケーションを促すことが大切です。
ITツールの導入
ハイブリッドワーク導入後は、テレワークをする社員のためにITツールを用意しましょう。コミュニケーション用のツールや勤怠管理用のツール、セキュリティ管理をするためのツールなどを必要に応じて導入する必要があります。
場所を選ばずとも問題なく勤務できるように、必要な環境を整えていきましょう。
ハイブリッドワークを円滑にするおすすめツール5選
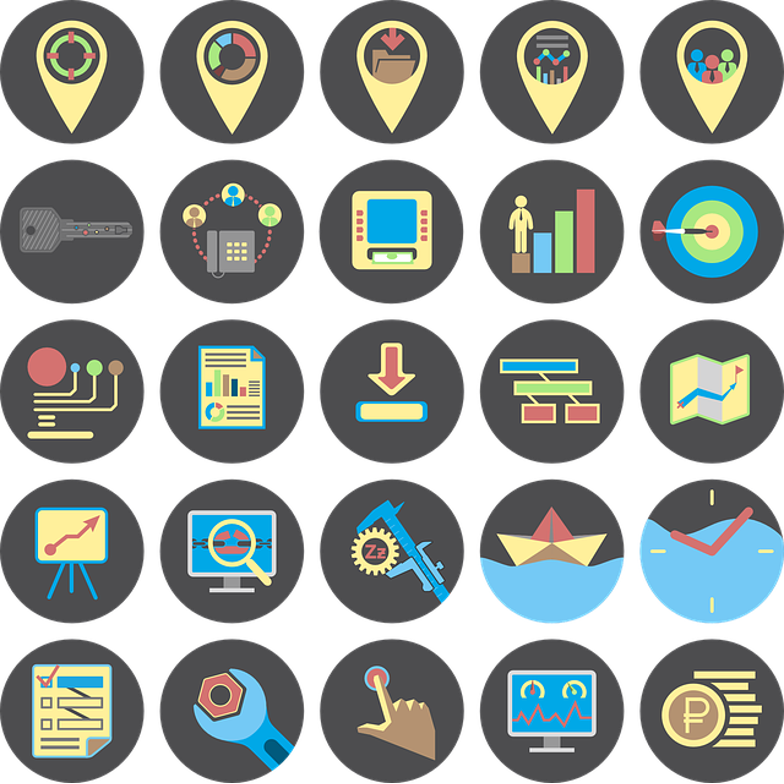
ハイブリッドワーク導入後、業務を円滑にするために役立つおすすめのツールを5つ紹介します。
- Teams /Teams Rooms
- Slack
- ジョブカン勤怠管理
- Trello
- NotePM
1.Teams/Teams Rooms|コミュニケーションツール
Microsoft社のコミュニケーションツールであるTeamsでは、チャットを通して、個人間やグループ間でのコミュニケーションを行えます。ビデオ通話や文字起こし、録画機能など、テレワーク環境に必須のオンライン会議に対応した機能も豊富です。そのほかの特徴として、PowerPointやOutlook、 SharePoint などMicrosoft製品との親和性が高く、同時にファイル編集なども行えることもメリットです。
ハイブリッドワークには、Teams Roomsも適しています。これは会議室に専用機器を設置し、よりスマートなTeams環境を構築できるサービスです。
通常、Teamsでオンライン会議に参加するには、参加者一人一人がPCやヘッドセットなどのデバイスを持ち込んで、事前準備をする手間がかかります。しかし、Teams Roomsを利用すれば、オフィス勤務の参加者は手ぶらで会議室を訪れ、卓上の操作端末をワンタップするだけで会議を開始できます。
これによって、事前準備の手間や設定ミスなど、個々のPCに起因するトラブルが減り、ストレスフリーに会議を開催できます。カメラとマイクは共に話者を自動認識できる高品質なものなので、リモートの参加者もその場にいるかのような臨場感で議論に参加できます。機器を設置するのに大型工事が不要なのもポイントです。
2.Slack|チャットツール
SlackはSlack Technology社が提供するチャットツールです。ビジネスチャットツールとして多くの企業に利用されており、さまざまなツールと連携させられます。先述したTeamsとも連携でき、Teams通話をSlackから行うことも可能です。ほかにも、連携用のAPIやプラグインが用意されているため、 チャットボット と連携させて、メッセージを自動出力させるなどの多彩な使い方が可能です。
3.ジョブカン勤怠管理|勤怠管理ツール
ジョブカン勤怠管理は株式会社DONUTSが提供する勤怠管理ツールです。ハイブリッドワーク導入の課題のひとつである勤怠管理の煩雑さを解消できます。
ジョブカン勤怠管理では、出勤、退勤はもちろん、休暇や残業、シフトの管理など、一連の勤怠管理をわかりやすい画面操作に従って行えます。また、入力したデータはクラウド上のデータベースに保管しておけるので、ペーパーレス化や長期保存も可能です。
4.Trello|タスク管理ツール
Trelloはアトラシアン株式会社が提供するタスク管理ツールです。Trelloを利用することで、プロジェクトの進捗やタスクの担当者などを一目で把握でき、勤怠状況把握やタスク管理を解消することが可能です。
また、タスク管理にとどまらず、ミーティングやブレーンストーミング用の機能も備わっているため、社員のコミュニケーション不足にも一役を担ってくれます。
5.NotePM|社内wikiツール
NotePMは株式会社Project Modeが提供する社内wikiツールです。主に、社内での情報共有に用います。ハイブリッドワークにおける課題のひとつである、情報伝達のスピードに生じるギャップを解消してくれます。
NotePM上に掲示板を作成し、共有事項を入力すると、アクセス許可がある社員全員が確認できます。これにより、勤務場所を問わず、同じタイミングでの情報伝達が可能です。また「ページを読んだ人」がわかるため、見落としを減らす効果も期待できます。
【参考事例】ハイブリッドワークを導入している企業3選

実際にハイブリッドワークを導入している以下の3企業の事例を紹介します。
- Microsoft社
- 富士通株式会社
- サイバーエージェント
Microsoft社
Microsoft社はテレワークを実施した結果、社員の働き方に対する意識や体制が以下の3グループに分かれることに気がつきました。
- オフィスワークをしたいと考えている人
- テレワークを続けたい人
- テレワークを続ける必要がある人
この調査結果を受けてハイブリッドワークを導入し、社員の性格や意識、業務内容から自身に合った働き方を選べるようになりました。
参考: ハイブリッドワークプレイスの理念と実践|Microsoft
富士通株式会社
富士通株式会社は2021年に「Work Life Shift 2.0」を発表し、ハイブリッドワークを導入しました。社員が主体となってそれぞれが働き方を選択することで、生産性や社員満足度の向上を実現しています。
今後はハイブリッドワークのさらなる進化に向けて、サテライトオフィスの社外開放や、自社オフィスでの最先端テクノロジー体験などを実施しています。
参考: 「Work Life Shift」の進化 |富士通株式会社
株式会社サイバーエージェント
株式会社サイバーエージェントは2020年6月より、全ての従業員が特定の曜日を リモートワーク とする「リモデイ」制度を導入しました。会議を行う際の移動時間や交通費の削減や、社員が心身をリフレッシュする機会を増やすなどテレワークのメリットを活かしたいと考えています。また、オフィスワーク時には社員同士がチームワークや活気のよさを活かせるような環境作りに努めています。
まとめ
テレワークとオフィスワーク双方の良さを活かす方法として、ハイブリッドワークは非常に有望な選択肢です。その一方で、ハイブリッドワークにはいくつかのデメリットや課題もあるため、取り入れる際にはツール導入などの工夫も求められます。
WindowsやAzureなど、Microsoftの製品をメインに利用しているならば、コミュニケーションツールとしてTeamsやTeams Roomsの導入をおすすめします。
またMicrosoftのPower Platformでは、Power Appsにより迅速なアプリケーション開発が可能となっており、現場業務のデジタル化をサポートします。その他自動化やデータ分析にも対応しているため、導入をご検討の際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。