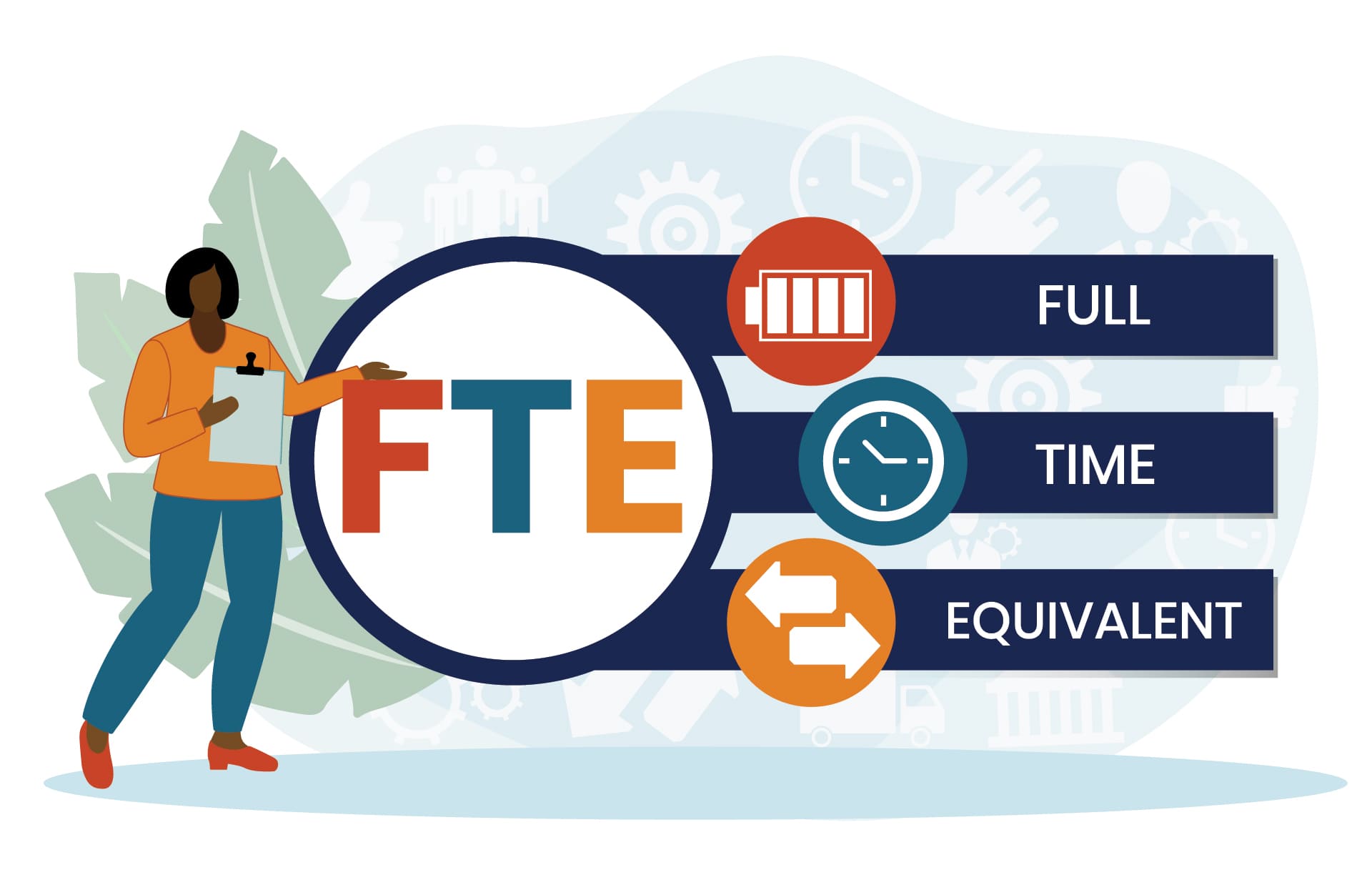「 営業力 とは何か?」この問いに対して、明確に回答できる方はどれ程いるでしょうか?「営業力とは売る力だ」「大口顧客をつかむ力だ」「売上に貢献することだ」と様々な意見があるかと思います。総じて言えることは、多くの方が「営業力=売る力」と認識していることです。
しかし、営業力とは本当に「売る力」なのでしょうか?営業力強化への取り組みは、売る力を強化することでいいのでしょうか?
今回は、結局のところ営業力とは何なのか?という、基本概念について紹介します。
営業力とは何か?
営業力が「売れる力」という回答自体は間違っていません。しかし、営業力という言葉を明確に理解するためには、あまりに不十分です。そこで、営業力をまず4つの能力に区分していきます。
その4つの区分とは「人間力」「スキル」「知識」「マネジメント力」です。
1.人間力
人間力とは顧客に好かれる能力であったり、目標達成に対し強い意志を持っていたりと、営業の人間性に関わる能力です。営業力の高さは、この人間力に大きく起因しています。
2.スキル
スキルは顧客との交渉を効率良く進めたり、自社製品の魅力を正しく伝えるためなど、営業活動を円滑に進めるための能力です。
3.知識
営業活動を円滑に遂行するためには、自社製品に対する知識や、顧客の業界特有の問題を理解していることが大切です。
4.マネジメント力
顧客からヒアリングを行い、顧客が持つ課題を理解し、解決策を提案し、施策を計画通りに遂行する。これらにはマネジメント力が重要であり、営業にとって必ず必要になる能力です。
このように、営業力を4つの区分に分けると、単なる「売る力」ではないことが分かります。営業力を「売る力」だけで片づけてしまうと、見落としも多くなり、結果として営業力強化は実現しません。
できる営業とダメな営業の違い
では、営業力を「できる営業」と「ダメな営業」の特徴から、さらに掘り下げて考えてみましょう。
≪できる営業の特徴≫
- 自社製品の説明を一方的にせず、顧客の課題に耳を傾ける
- 顧客の「こうしてほしいはず」を考え先回りする
- 顧客が「知っていて当たり前」だと思わず、専門用語の使用は避ける
- 常に身なりに気をつけ、清潔を保っている
- 話すことがいつも簡潔で分かりやすい(曖昧な表現を使わない)
- 顧客の課題から最適な解決策を見つけ出せる
- 分からないことを「分からない」と言える
- 顧客にとってデメリットになることもしっかりと伝える
≪ダメな営業≫
- 自社製品の説明ばかりで、顧客の話を一向に聞かない
- 対応は常に後手に回っている
- 専門用語を連発し、顧客の立場に立っていない
- よれよれのスーツで、どこか清潔感がない
- 接続詞や曖昧な表現の多様で、話が分かりづらい
- 顧客の課題を明確に理解せず、間違った解決策を提案する
- 知ったかぶりをする
- 顧客にとってメリットになる部分しか伝えない
できる営業は常に「顧客に立場に立って」物事を考えます。これは顧客優先で自社の利益を犠牲にすることではなく、自分ができることの範囲で、自社製品ができることの範囲で顧客のことを考え、それを自発的に行動に移すことです。
このため、できる営業ほど、ダメな営業よりも残業が少ない傾向にあります。
ダメな営業はというと常に「自分本位な」考え方で営業活動を行います。「売りたい」という一心で自社製品の説明ばかりしてしまったり、そのくせ顧客のために自発的に行動することはなかったりと、終始自分中心に営業を行います。
以上のことから、営業力とは「自分本位に考えず、顧客の立場に立って考え、行動する力」だとも言えます。
営業力強化のために実践したいこと
ここでは、営業力を強化するために、すぐに実践できる施策を紹介します。
1.自発的に行動する営業を育てる
営業力の高い営業が育たない環境の特徴として、「仕事を任されない」という状況が少なくありません。例えば、新人営業は何事も「できなくて当たり前」にもかかわらず、先輩営業や上司は「何でこんなこともできないんだ」と叱責し、自分で仕事を遂行してしまいます。これでは、いつまで経っても自発的に行動する営業が育ちません。
2.営業部内の情報共有を促進する
多くの営業部は、顧客情報や営業スキルに関する情報が属人化してしまっています。属人化とは個々が持つ情報が共有されていない状態です。「自分の営業スキルを公開するなんてとんでもない」と考える方も多いでしょう。
しかし実際は、情報を共有することの方が、公開した側にもされた側にとっても、高いリターンがあります。
例えばトップ営業のノウハウを部内全体で共有すれば、皆がトップ営業同等とまでいかなくとも、全体の営業スキル底上げになります。ノウハウを公開したトップ営業は部内での評価がさらに高くなり、公開したことで新たな発見もあるでしょう。
営業力の高い営業を多く抱える組織は、総じて営業部内での情報共有が進んでいます。
3.組織で営業活動に取り組む
「営業」と聞くと、営業一人が相手先企業に赴き、セールスを行うというイメージが一般的にあります。実際は複数人で営業に行くこともありますが、少人数であることには変わりません。しかし本来営業とは、部内全体で組織的に取り組むことが理想です。営業各人は相互に連携し、情報共有を行い、さらに上司を含めた部内全体で営業活動に取り組みます。
そうすれば、自然に営業ノウハウも蓄積していき、営業力強化に繋がります。
システム面の課題を解決すると、営業力が強化する
営業力強化とは、実は教育面だけの問題ではありません。システム面の課題を解決することでも、営業力強化に繋がります。その課題とは「分断化されたシステム環境の統合」です。
営業に限らず、社内の業務アプリケーションのほとんどは連携されていません。営業には 営業支援 システム、経理には 財務会計 システム、製造部には 生産管理 システムなど、すべての業務アプリケーションは「分断化」しています。
こうした環境下において、業務効率をアップする取り組みには限界があります。例えば、営業は在庫データを閲覧したくとも分断化したシステム環境によってシステム上のデータが信頼できません。そうなると、在庫管理担当者に連絡したり、時には自ら在庫置き場に行って確認します。
しかし、担当者がなかなか捕まらなかったり、在庫置き場の仕組みが分からないことで問題が発生することも多く、結果として悪循環を生みます。
そこで、分断化されたシステム環境を統合することで、こうした課題を一気に解決できます。
データの二重入力が無くなるのでシステム上のデータは信頼性が増し、営業は在庫管理システムのデータを確認しただけで納期回答ができます。このように、システム面の課題を解決することで、営業力強化に繋がるのです。
まとめ
営業力強化は多くの企業にとって重要な課題です。システム面のアプローチでは、 ERP 導入とシステム統合を視野に入れてください。ERPは複数の業務アプリケーションを統合提供し、相互連携の取れたシステム環境を構築できます。営業支援システムを備えたERPなら、情報共有も促進し、営業全体の底上げにもなります。営業力強化のために、システム環境の見直しから行いましょう。

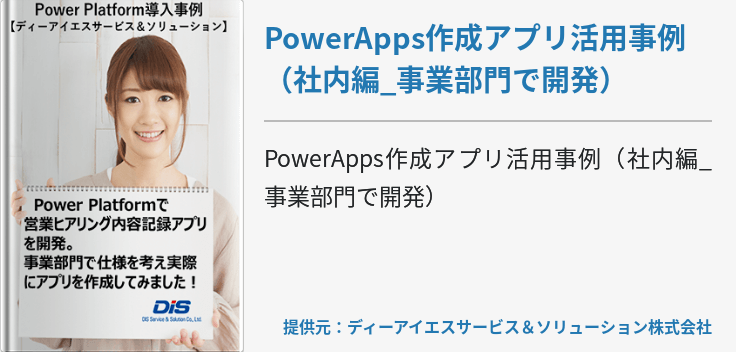
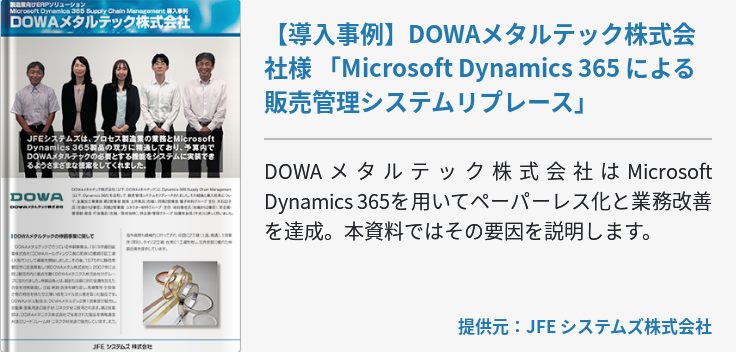
![[BizApp]目標管理におけるMBO課題と6つの成功ポイント [BizApp]目標管理におけるMBO課題と6つの成功ポイント](https://www.cloud-for-all.com/hubfs/bizapp/CTA/cta-footer-mbo-challenges.png)