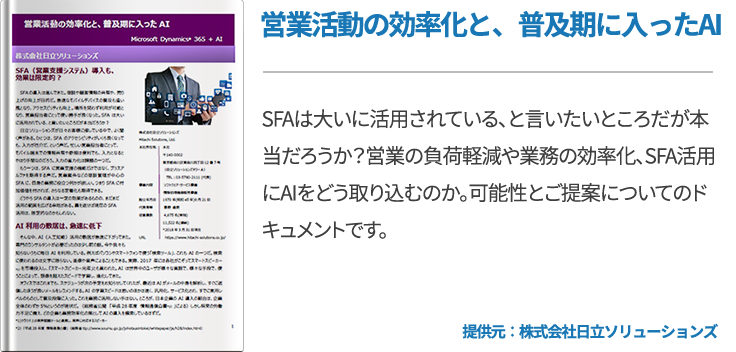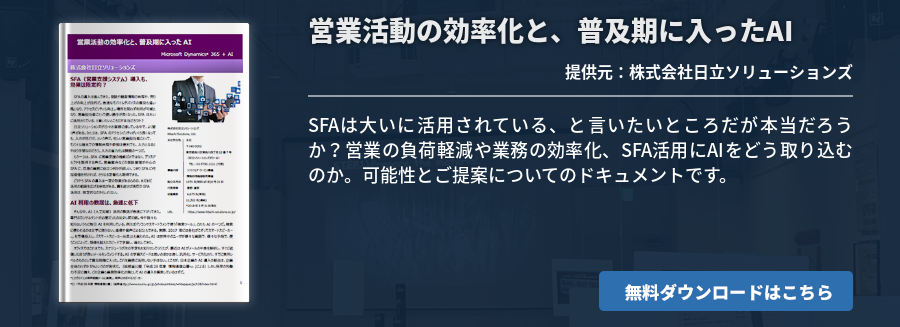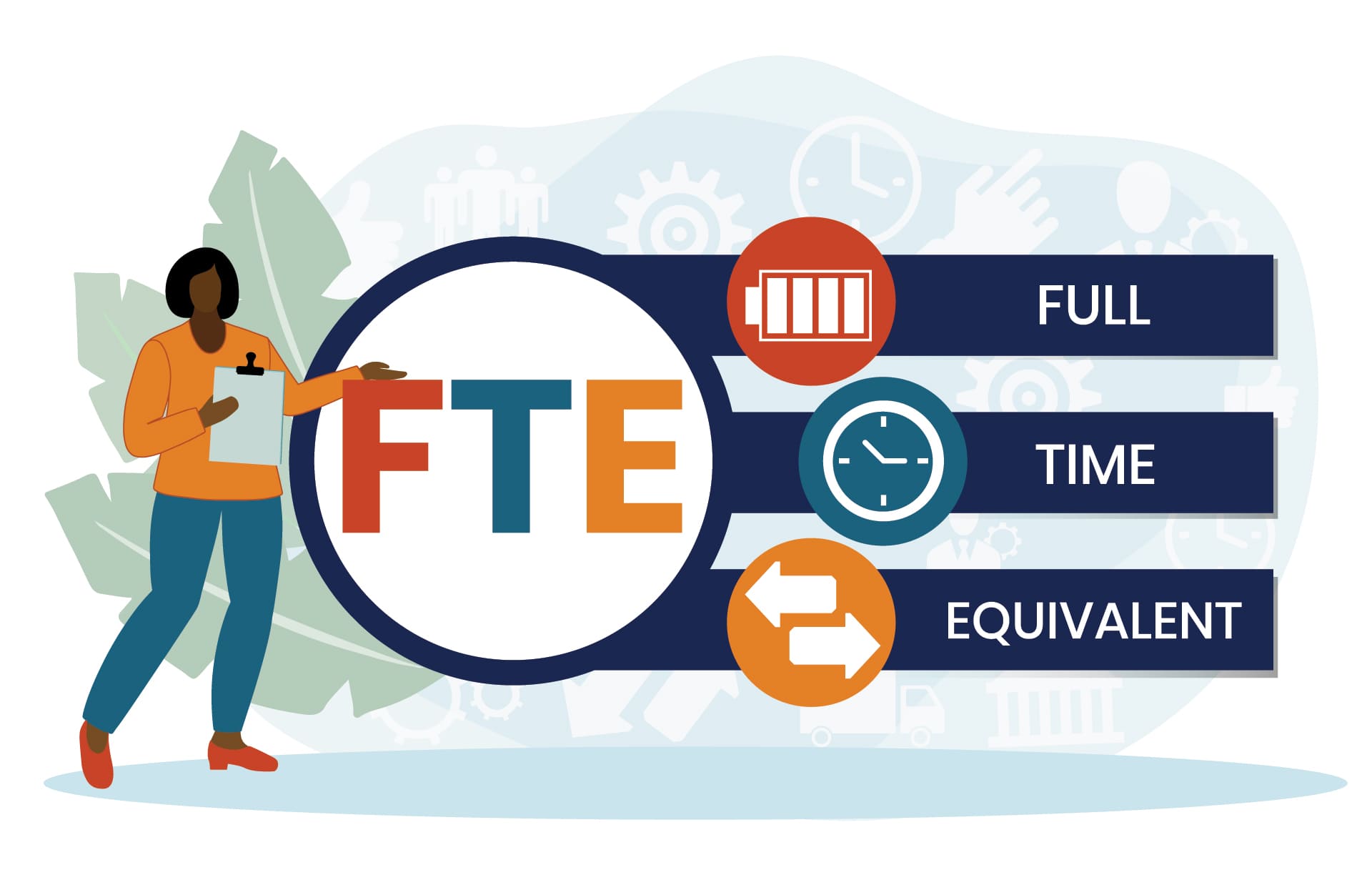以前に比べると、ここ数年で「 SFA って何?必要なものなの?」という企業は格段に少なくなっています。このことはSFA市場の成長率から読み取れます。調査会社ITRによると、国内SFA市場は2017年度に前年比20.0%増と高成長を遂げており、2018年度に関しても好調をキープしています。
SFAが人気を集めている理由の1つが、「従来の営業スタイルから脱却を試みる企業が増えている」ことです。日本が古くから続けてきた「足で稼ぐ営業」というのは、時代遅れの認識が強く、今ではデータに裏付けされた根拠から戦略的に行動パターンを考え、効率的な営業活動を実施していくことに重要性を感じる企業が増えています。
実際に、「営業担当者にコンタクトを取った時点では、顧客企業の購買プロセスが6割完了している」という時代ですから、「足で稼ぐ営業」というのが如何に非効率的なのかは明白でしょう。
SFAを導入すれば、営業担当個人で抱えていた案件情報を1つのシステムに集約し、情報分析を通じて顧客心理をより深く理解したり、成約率の高い顧客を抽出したり、あるいは単純に営業活動を今よりも効率的にするなどのメリットがあります。
しかし、成功ばかりではないのが実情です。特にSFAは「営業担当に嫌われる可能性が高い業務システム」なので、ひと工夫もふた工夫も加えないことには、SFA導入成功はありません。
そこで本稿では、「絶対成功するSFA導入ステップ」と題して、SFA導入のポイントを解説していきます。SFA導入を検討しているという方も、そうでない方も、どうすれば成功するのかのヒントを得ていただければ幸いです。

SFA導入のステップ
まずは、SFAを導入する際に、多くの企業が踏むであろう一般的なステップ(流れ)をご紹介します。
SFA検討
「SFAを自社に導入して、本当に効果を発揮するかどうか?」。おそらく、本稿を読まれている方の多くがこのステップにあります。SFAの概要やメリット/デメリットについて知り、想像の範囲内でSFA導入可否について検討する段階です。
要件定義
SFA導入を決意したら、「自社にとって必要なSFAは何か?」という要件を定義していきます。要件定義は非常に重要なステップであり、今後の導入プロジェクトの指針になります。ちなみに要件定義を導入パートナーと共に進める場合もあります。
RFP/RFI作成
RFP (提案依頼書)と RFI (情報提供依頼書)は、SFAを導入するにあたり、各社製品で何ができるかを知るのに欠かせない書類です。ホームページなどで得られる情報には限界があるので、あらかじめ定義した要件をもとに「貴社製品で何ができますか?」と、提案と情報提供を求めます。
製品比較
RFP/RFIの返答を参考にしながら、自社にとって必要なSFAを決定していきます。どの製品を選ぶかによってSFAの成否が分かれるポイントなので、製品比較は慎重性が欠かせません。
導入パートナー選定
導入するSFAが決定したら、次の導入パートナーを選定します。多くの場合、RFP/RFIの返答を受けた企業とそのままプロジェクトを進めますが、導入パートナーを改めて選定するのもよいでしょう。
契約
導入するSFAや導入パートナーが提供するサポートなどについての契約を結びます。契約事項に相違がないように、パートナーが提示する契約事項を細かくチェックしておきましょう。
導入
オンプレミスならSFAに必要なサーバーの調達やネットワーク構成、ソフトウェアインストールやパラメーター調整などが入ります。必要に応じてアドオン開発も加わりますので、事前のコスト試算が大切です。
運用
いざSFAの運用スタートとなります。運用段階に入れば安心というわけではなく、本当の勝負は運用開始時から始まります。
SFAを導入する規模、どのような製品や導入パートナーを選ぶかによっても違いますが、早ければ1ヵ月~3ヵ月、遅くとも6ヵ月程度で運用をスタートすることが多いのがSFAです。
SFA導入を成功させるポイント
SFA導入を絶対成功させるためにまず大切なのは、「SFA導入は難しい」という認識を捨てることです。冒頭で「営業担当者に嫌われる可能性が高い業務システム」と説明しましたし、これは紛れもない事実ですが、だからといって「難しい」と判断するのは早合点です。あくまで「可能性が高い」だけであり、SFA導入を戦略的に進めれば必ず成功させることができます。それでは、そのポイントを確認していきましょう。
営業責任者をプロジェクトに巻き込む
トップダウン指揮系統を持つ企業にありがちなのが、経営者の一存でSFA導入を決定し、プロジェクトのほとんどを情報システム単体で推進することです。そこには営業部門の意思が介入する隙が無く、最終的に何が起こるかというと、新しいシステムに対する「反発」です。
SFAを利用するのはあくまで営業部門であって、情報システムでも経営者でもありません。このことを十分に理解しながら、SFA導入のプロジェクトに営業責任者を巻き込む必要があります。
要するに、現場からの意見を積極的に吸い上げた上で、実態に即したSFA導入を目指すことが大切です。
営業担当者の理解をしっかりと得る
営業担当者の多くはSFA導入に際し、「面倒なことが増えないか?」と不安を抱えています。ただでさえ顧客とのコミュニケーションや資料作成などの事務作業に追われているのに、これ以上負担が増えるのは御免だと考えるのは当然のことです。
そこで、SFA導入担当側はSFAを導入することで、営業担当者にとってどのようなメリットが生じるのかを説明し、反対にSFAによって新しく負担になることを正直に説明することが求められます。
その上で営業担当者からの理解をしっかりと得ることが、運用開始後のSFA定着率に繋がるでしょう。
運用初期は使用する機能を限定的にする
営業担当者の負担を減らすことと、運用負担を軽減する意味で、SFAで使う機能を限定的にするのは有効な手段です。昨今のSFAは高性能なものばかりなので、いきなり使いこなせても無理があります。
ならばいっそ、運用初期は使う機能を限定的にして、SFAの定着率をアップすることに注力するのがセオリーです。
クラウド環境で利便性を向上する
SFAを導入するにあたり「オンプレミスとクラウド、どちらが最適か?」と聞かれれば、現代ビジネスにマッチしているのはやはりクラウドです。オンプレミスに比べて柔軟性は下がりますが、そもそも今までやってきたことを踏襲するのがSFAなのではなく、新しい営業スタイルを確立するのがSFAです。
従って、柔軟性は低くてもWebブラウザ経由でシステムを利用することで外出先からのアクセスも可能にして、SFAの利便性を高める方がよいでしょう。
以上4つのポイントを押さえるだけで、SFA導入成功に向けたプロジェクトを推進できます。もちろん、慎重な製品選定や信頼のおける導入パートナーを選ぶことなどもポイントのうちなので、それらを念頭に置きながらSFA導入を目指してきましょう。