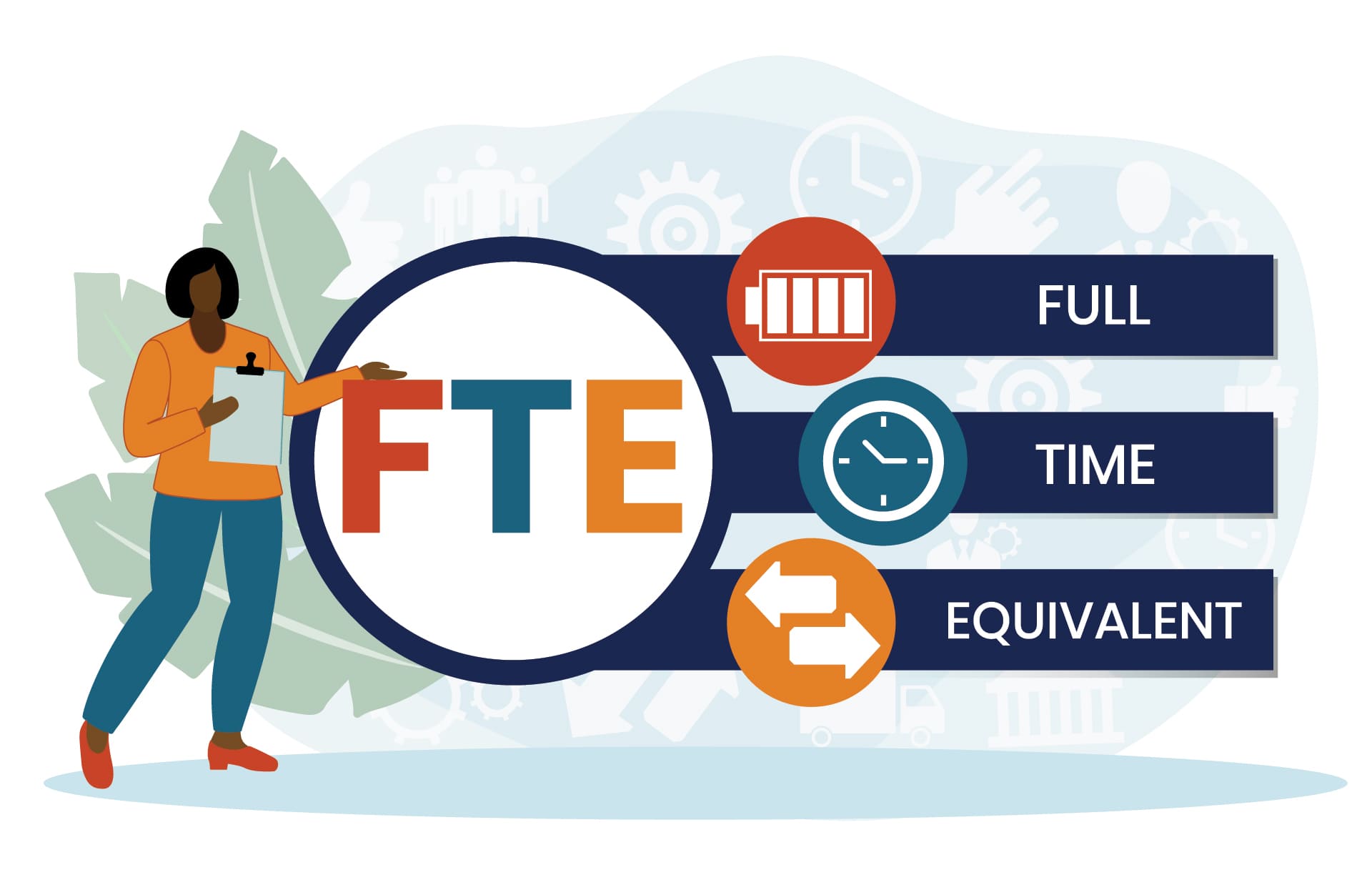SFA (Sales Force Automation: 営業支援 システム)及び CRM (Customer Relationship Management:顧客関係管理システム)の重要性は年々高まっています。市場は年々拡大傾向にあり、特にクラウド型のSFA/CRMが脚光を浴びており、社内にインフラを整備しなくてもシステムを利用できることから、高い人気を集めています。
しかし、SFA/CRMを実際に導入すると「上手く活用できない」という声をよく聞きます。特にBtoB企業における営業活動において活用が難しいとされており、SFA/CRMの力を十分に引き出せていないという企業は、実は多いのです。
本稿では、BtoB企業の営業活動において、SFA/CRMが上手く活用できていない理由と、その改善策について紹介しています。
SFA/CRMが活用できない理由、“アカウント型”と“エリア型”
BtoB企業の営業活動では大きく分類して2つの型があります。それが“アカウント型”と“エリア型”です。
アカウント型とは、特定の顧客との深い関係構築を図り、複数の商品を組み合わせてソリューションを提供し、パートナーとして長期的にかかわっていくような営業活動を指します。取引規模が大きく、案件ごとのリードタイムが長いのが特徴です。
営業部門における顧客別売上高を「顧客A・B・C…」と売上の高い順に並べていくと、全体の上位2割が売り上げの約8割を占めていることに気づきます。そうした上位2割は主要顧客としてリソースを集中させ、アカウント型の営業活動を展開していきます。
一方、エリア型とは主要顧客以外の顧客に対する営業活動を指し、顧客ごとの関係構築よりも案件が発生した順に対応していきます。取引規模は小さい代わりに、案件ごとのリードタイムが短いのが特徴です。
アカウント型とエリア型の特徴
|
|
アカウント型 |
エリア型 |
|
担当顧客数 |
少ない |
多い |
|
1社での発生案件数 |
多い |
少ない |
|
顧客の優先度 |
売上高(顧客規模) |
発生案件順 |
|
行動の基本原則 |
効果、適正、満足 |
効率、スピード、成約 |
|
行動の方向性 |
攻め、守り(関係性構築) |
攻め、開拓 |
|
案件の規模 |
大規模(包括的) |
小規模 |
|
案件のリードタイム |
長い |
短い |
|
意思決定関係者 |
多い(ボトムアップ) |
少ない(トップダウン) |
|
提案商品 |
複合、継続 |
単品、単発 |
では、営業活動のアカウント型とエリア型がなぜSFA/CRMを上手く活用できない理由になるのか?
それは、「2つの型の営業活動を混在している」ということです。多くの営業部門では、アカウント型とエリア型の営業活動を同時に展開しています。
成約の見込みは高いけれど小規模な商談を積み上げつつ、大規模で多くの顧客関係者と関り長期にわたる商談も追いかける状況になっているのです。営業部門内で、型ごとに別組織に分かれていれば問題ないのですが、1人のセールス・パーソンが2つの型の両方を担っているという状況が多いのです。
この場合、売上目標を達成するために前期実績等から見込める商談は効率的に活動をして実績を積み上げ、それだけでは目標に足りない部分はせめて成約するという難易度の高い業務を臨機応変に行うことが求められます。しかし、2つの型の実践を求められる営業や組織がパイプライン分析を行ったとしても、質の異なる商談や活動が混在しているため、役立つ気づきが得られません。
SFA/CRMを活用するキーポイント
BtoB企業の営業活動においては、目標達成のために“質”と“量”のバランスを取り、マネジメントを実施していく必要があります。ここでは、SFA/CRMを活用するためのキーポイントについてご紹介します。
①話し合うべき商談の抽出
目標に対するギャップを埋めるためには、攻めの商談を成功に導く必要があります。特に、新規開拓や拡販商談を成約するためには、セールス・パーソン任せにせず組織的に対応する必要があり、その仕組みとしてSFA/CRMを活用します。セールス・パーソンもマネージャーも多忙なため、すべての商談に時間をかけて話をする時間はありません。しかし、問題のある商談はしっかりと話し合い、戦略を練り、成約に繋げる必要があります。
そうした商談を抽出するためには“進度”と“確度”を把握することが大切です。ただしセールス・パーソンによって商談の進度と確度の判断基準がバラバラになっており、セールス・パーソンとマネージャーで同じ認識を持つことが難しくなっています。
そこで、確度はセールス・パーソンの主観と客観的数値を比較して差のある商談を抽出していきます。客観的数値とは商談に関する情報から算出するものです。セールス・パーソンが「確度が高い」と言っていても、意思決定者に会えているか、影響力はあるか、競合ではなく自社に依頼しそうかといった取引関係者情報及びBANT情報から、商談の確度をスコアリングし、セールス・パーソンが主観で記録した確度と差異があればマネージャーとしっかり話し合います。
進度に関しては、セールス・パーソンがフェイズごとに立てたスケジュール通りに進んでいれば、対話すべき商談として抽出します。フェイズの定義についても組織ごとに標準化していくことが需要であり、見積を出してもセールス・パーソン自ら提示した見積と顧客から請われて提示した見積とではわけが違います。顧客型の購買プロセスに沿ってフェイズを定義した上で、SFA/CRMでチェックすることで精緻に進度を管理できます。
「CRMとSFAの違いを解説!」の記事で詳しく調べてみましょう!
②商談レベル管理にメリハリを付ける
さらに、質と量のバランスを取るためには、メリハリを付けたマネジメントをすることが必要になります。そのためには、SFA/CRMを使う以前に商談をどのレベルで管理するかを社内で合意していくことが大切です。
新規開拓や拡販を目的とした商談と、継続的にとれる見込みの高い商談を画一的に管理するのは非常に非効率です。入力項目も進捗管理についても、各々に適した方法を営業現場と検討しつつ、納得の上でSFA/CRMを仕組み化しなければいけません。
その管理方法を整理しないままでSFA/CRMを導入すると、マネージャーもどうやってマネジメントに使えばよいかが分からず、業務負荷が上がっただけになります。
クラウド型SFA/CRMのメリット
いかがでしょうか?BtoB企業における営業活動では、上手く活用できない理由がいくつかあります。それを解消するためにクラウド型SFA/CRMを選択する企業も増えています。クラウド型SFA/CRMは、インターネット回線を利用することでいつでもどこでも好きな時にシステムを利用できるというメリットがあり、BtoB企業におけるSFA/CRM活用を促進します。
また、カスタマイズを加えることでアカウント型とエリア型の営業活動を分断することができ、組織ごとに営業活動を効率的に行うことができます。BtoB企業における営業活動を効率化し、SFA/CRMを上手く活用するために、クラウド型SFA/CRMをご検討ください。