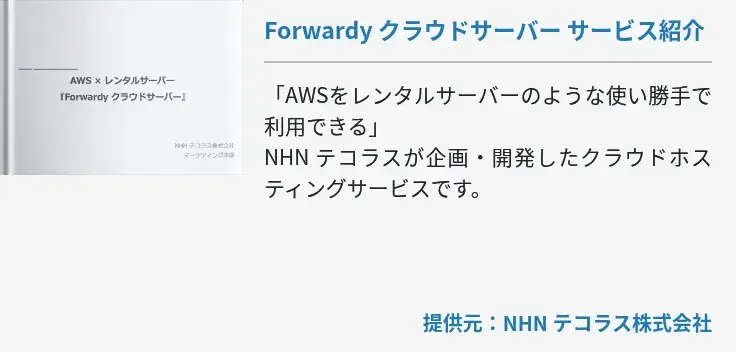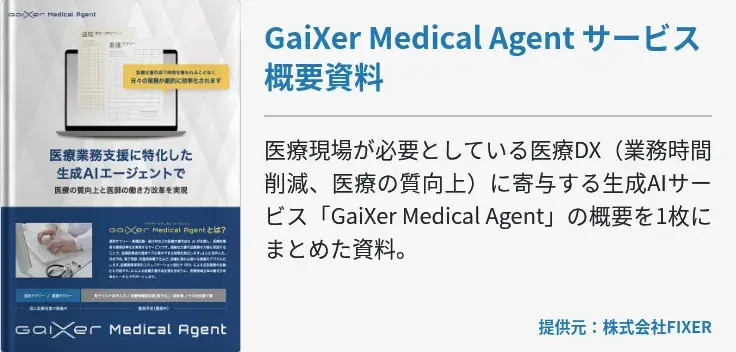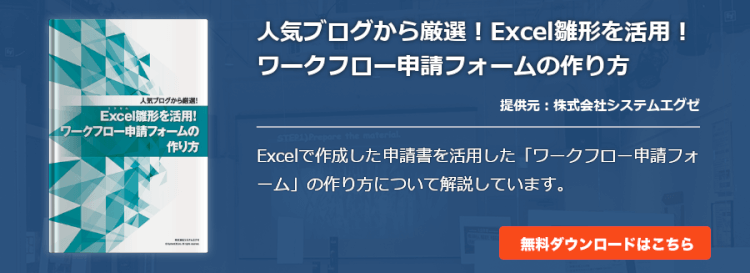「機械学習モデルの推論コストが想定以上にかかっている」「リアルタイム性が求められるサービスで、GPUのレイテンシーが課題になっている」といった悩みはありませんか?このような課題を解決するためにAWSが独自開発したのが、AI推論に特化したカスタムチップ「AWS Inferentia」です。結論として、AWS Inferentiaは、特定の推論ワークロードにおいて、GPUを大幅に上回るコストパフォーマンス(価格性能比)と、高いスループット・低レイテンシーを実現します。
この記事で分かること
- AWS Inferentiaがどのようなもので、なぜ注目されているのか
- GPUと比較した際のコスト・パフォーマンスの具体的な違い
- EC2 Inf1・Inf2インスタンスを使ったAWS Inferentiaの基本的な使い方
- 自社のユースケースでAWS Inferentiaを導入すべきかの判断基準
- 画像認識や自然言語処理など、実際のビジネスでの活用事例
この記事では、AWS Inferentiaの基礎知識から、GPUとの詳細な比較、具体的な使い方、料金体系、実際の活用事例まで、初心者の方にも理解できるよう網羅的に解説します。最後までお読みいただくことで、あなたのAI/機械学習プロジェクトにおける推論インフラの最適化に、AWS Inferentiaがどのように貢献できるかを明確に理解できるでしょう。
AWS Inferentiaとは?
AWS Inferentia(アマゾン ウェブ サービス インファレンシア)とは、Amazon Web Services(AWS)が独自に開発した、機械学習の「推論」処理に特化した専用チップです。 AIや機械学習のモデルは、大量のデータからパターンを学ぶ「学習」フェーズと、学習したモデルを使って新しいデータに対する予測や判断を行う「推論」フェーズに分かれます。 AWS Inferentiaは、この後者の「推論」を高速かつ低コストで実行することを目的に設計されています。
これまで、このような処理には高性能なGPU(Graphics Processing Unit)が広く利用されてきましたが、GPUは本来グラフィック処理のために設計されており、学習と推論の両方に使える汎用性を持つ一方で、特に推論処理においてはオーバースペックでコストが高くなるという課題がありました。 Inferentiaは推論に不要な機能を削ぎ落とし、必要な性能を追求することで、GPUと比較して優れたコストパフォーマンスを実現します。
なぜ今AWS Inferentiaが注目されるのか
近年、AI技術は目覚ましい進化を遂げ、画像認識、音声アシスタント、レコメンデーションエンジン、そして生成AIなど、私たちのビジネスや生活のあらゆる場面で活用が広がっています。 これに伴い、AIモデルがリアルタイムで膨大なデータに対して予測や判断を下す「推論」処理の重要性が飛躍的に高まっています。
しかし、サービスの規模が拡大するにつれて、推論処理にかかるコンピューティングコストが大きな課題となっていました。特に、高性能なGPUを多数利用する必要がある場合、その運用コストはビジネスの収益性を圧迫する要因となり得ます。
このような背景の中、AWS Inferentiaは推論処理のコストパフォーマンスを劇的に改善するソリューションとして大きな注目を集めています。 GPUを利用した場合と比較して、推論あたりのコストを大幅に削減し、高い処理性能(スループット)と低い遅延(レイテンシー)を実現します。 これにより、スタートアップから大企業まで、より多くの開発者がコストを気にすることなく、高度なAI機能をアプリケーションに組み込むことが可能になりました。 特に、最新世代の「Inferentia2」は、大規模言語モデル(LLM)のような、より複雑で要求の厳しい生成AIの推論にも対応しており、AI活用の新たな可能性を切り拓いています。
- AI/機械学習の社会実装が進み、リアルタイムでの「推論」需要が急増している。
- 従来のGPUによる推論は、高性能だがコストが高いという課題があった。
- Inferentiaは推論に特化することで、コストを抑えつつ高いパフォーマンスを実現する解決策として登場した。
- 生成AIのような大規模モデルの登場により、効率的な推論処理の必要性がさらに高まっている。
AWS Inferentiaの主なメリット
AWS Inferentiaは、Amazon Web Services(AWS)が機械学習の「推論」処理を高速化し、コストを最適化するために独自に開発したカスタムAIチップです。 AIモデルの学習(トレーニング)ではなく、学習済みモデルを使って予測や分析を行う推論ワークロードに特化している点が最大の特徴です。 これにより、従来のGPUを利用した推論に比べて、多くのアプリケーションで優れたメリットを提供します。
GPUと比較して圧倒的なコストパフォーマンス
AWS Inferentiaを利用する最大のメリットの一つは、その卓越したコストパフォーマンスにあります。GPUは学習と推論の両方に使用できる汎用性の高いパワフルなプロセッサですが、その分コストが高くなる傾向があります。一方、Inferentiaは推論処理に不要な機能を削ぎ落とし、必要な性能を最小限のコストと消費電力で実現するように設計されています。
実際に、AWS Inferentiaを搭載したAmazon EC2 Inf1インスタンスは、同等のGPU(NVIDIA T4)を搭載したG4dnインスタンスと比較して、最大70%低い推論あたりのコストを実現すると報告されています。 また、後継のInferentia2を搭載したInf2インスタンスも、同等のGPUベースインスタンス(G5インスタンス)と比較してワットあたりのパフォーマンスが50%優れており、コスト削減だけでなくサステナビリティ目標の達成にも貢献します。
このコスト効率の高さは、特に大規模な推論処理を常時行う必要があるサービスにとって、インフラコストを大幅に削減できる強力な要因となります。
高いスループットと低いレイテンシーの実現
AWS Inferentiaは、コストだけでなくパフォーマンス面でも大きなメリットをもたらします。特に、多くのリクエストを同時に処理する「スループット」と、リクエストから応答までの時間である「レイテンシー」において優れた性能を発揮します。
この高性能を支えているのが、Inferentiaチップに搭載された複数の「NeuronCore」と呼ばれるプロセッシングコアと、大容量のオンチップメモリです。 これにより、モデルを外部メモリから読み込む際のボトルネックを解消し、高速なデータアクセスを実現します。
具体的な性能として、最新のAWS Inferentia2は、第一世代のInferentiaと比較して最大4倍のスループットと最大10分の1のレイテンシーを達成しています。 さらに、同等のGPUベースインスタンスと比較しても、スループットは最大4倍、レイテンシーは最大10分の1という結果が報告されており、その性能の高さがうかがえます。
以下の表は、Inferentia2と他のインスタンスの性能比較の一例です。
| インスタンス/チップ | 比較対象 | スループット | レイテンシー |
|---|---|---|---|
| EC2 Inf2 (Inferentia2) | EC2 Inf1 (Inferentia1) | 最大4倍向上 | 最大10分の1に短縮 |
| EC2 Inf2 (Inferentia2) | EC2 G5 (NVIDIA A10G GPU) | 最大2.6倍向上 | 8.1分の1に短縮 |
このように、AWS Inferentiaはリアルタイムでの応答が求められるレコメンデーションエンジン、チャットボット、画像・動画解析といったアプリケーションにおいて、ユーザーエクスペリエンスを損なうことなく、高速かつ安定したサービスを提供することを可能にします。
AWS Inferentia VS GPUの性能比較
AWS InferentiaとGPUは、どちらも機械学習のワークロードを高速化するためのプロセッサですが、そのアーキテクチャと得意な処理が大きく異なります。Inferentiaは「推論」に特化して設計されているのに対し、GPUはより汎用性が高く「学習」と「推論」の両方に使用できます。この違いが、コストやパフォーマンスにどう影響するのかを詳しく見ていきましょう。
コスト面での違い
機械学習モデルを本番環境で運用する際、最も大きな割合を占めるのが推論コストです。AWS Inferentiaは、この推論処理に特化することで、GPUと比較して圧倒的なコストパフォーマンスを実現します。
AWSの発表によると、同等のGPUベースのインスタンスと比較して、推論あたりのコストを最大70%削減できるとされています。 これは、大量のリクエストを常に処理し続ける必要がある大規模なアプリケーションにおいて、サーバーコストの大幅な削減に直結します。
具体的なインスタンス料金を比較してみましょう。以下は、東京リージョンにおけるオンデマンドインスタンスの1時間あたりの料金比較です(料金は変動する可能性があるため、最新の情報は公式ページをご確認ください)。
| インスタンスファミリー | インスタンスタイプ | プロセッサ | 1時間あたりの料金(USD) |
|---|---|---|---|
| Inferentia搭載 | inf2.xlarge | AWS Inferentia2 | 約$1.137 |
| Inferentia搭載 | inf1.xlarge | AWS Inferentia | 約$0.308 |
| GPU搭載 | g5.xlarge | NVIDIA A10G | 約$1.459 |
| GPU搭載 | g4dn.xlarge | NVIDIA T4 | 約$0.71 |
単純な時間あたりの料金だけでなく、処理できるリクエスト数(スループット)も考慮すると、Inferentiaのコスト効率の高さがより明確になります。例えば、ByteDance社の事例では、GPUインスタンスと比較して最大60%のコスト削減を実現したと報告されています。
パフォーマンス面での違い
パフォーマンスを比較する上で重要な指標は「スループット(単位時間あたりの処理能力)」と「レイテンシー(処理にかかる遅延時間)」です。
AWS Inferentiaは、推論処理に不要な機能を削ぎ落とし、チップ内に大容量のキャッシュメモリを搭載することで、高いスループットと低いレイテンシーを実現します。 特に、リアルタイムでの応答が求められる音声認識やレコメンデーションエンジンなどのアプリケーションでその真価を発揮します。
第2世代のAWS Inferentia2を搭載したEC2 Inf2インスタンスは、第1世代のInf1インスタンスと比較してスループットが最大4倍、レイテンシーが最大10分の1に向上しています。 さらに、同等のGPU(G5インスタンス)と比較しても、ワットあたりのパフォーマンスが最大50%向上しており、エネルギー効率にも優れています。
| 指標 | AWS Inferentia | GPU |
|---|---|---|
| スループット | 非常に高い。特に大規模な推論ワークロードで効果を発揮。 | 高いが、モデルやバッチサイズによってはInferentiaに劣る場合がある。 |
| レイテンシー | 非常に低い。オンチップメモリにより高速なアクセスが可能。 | 低いが、Inferentiaの方がより低遅延を実現できるケースが多い。 |
| 得意な処理 | 機械学習モデルの「推論」に特化。 | 「学習」と「推論」の両方に対応可能。 |
ユースケースによる使い分け
これまでの比較を踏まえ、AWS InferentiaとGPUは、それぞれの特性を理解し、ユースケースに応じて使い分けることが重要です。
- AWS Inferentiaが適しているケース
- 大規模な推論処理: 検索エンジン、レコメンデーション、不正検知、自然言語処理など、大量のリクエストを低遅延で処理する必要がある本番環境。
- コスト削減が最優先事項: 推論コストを大幅に削減したい場合。
- リアルタイム性が重要なアプリケーション: 音声アシスタントやリアルタイム翻訳など、即時の応答が求められるサービス。
- GPUが適しているケース
- 学習と推論の両方: モデルのトレーニングからデプロイまで、同じ環境で一貫して行いたい場合。
- 開発・プロトタイピング段階: 様々なモデルやフレームワークを柔軟に試したい場合。
- 小規模なワークロード: 推論リクエストが少なく、Inferentiaのコストメリットを享受しにくい場合。
- 特殊なモデル: AWS Neuron SDKがまだサポートしていない最新のモデルや演算子を使用する場合。
結論として、本番環境での大規模な「推論」ワークロードにはAWS Inferentiaが、モデルの「学習」や柔軟性が求められる開発段階ではGPUが、それぞれ適していると言えるでしょう。プロジェクトの要件やフェーズに合わせて最適なプロセッサを選択することが、コスト効率とパフォーマンスを最大化する鍵となります。
AWS Inferentiaの使い方入門
AWS Inferentiaの強力な性能とコスト効率を引き出すための、具体的な利用手順を3つのステップに分けて解説します。GPUインスタンスでの推論とは異なり、Inferentiaでは「コンパイル」という一手間が必要になりますが、このプロセスこそが性能を最大化する鍵となります。一度流れを掴めば、誰でも簡単にその恩恵を受けられます。
ステップ1 対応するEC2インスタンスを選択する
AWS Inferentiaを利用するためには、Inferentiaチップが搭載された専用のAmazon EC2インスタンスを選択する必要があります。現在、用途や求める性能に応じて第1世代の「Inf1インスタンス」と第2世代の「Inf2インスタンス」が提供されています。
Amazon EC2 Inf1インスタンス
Inf1インスタンスは、AWSが独自に設計した最初の機械学習推論チップ「AWS Inferentia」を搭載しています。 画像認識、自然言語処理、レコメンデーションなど、様々な推論ワークロードにおいて、GPUインスタンスと比較して大幅なコスト削減を実現するために設計されました。 これからInferentiaを試してみたいという方や、コストを最優先事項とする場合に最適な選択肢です。
| インスタンスサイズ | Inferentiaチップ数 | vCPU | メモリ(GiB) | ネットワーク帯域幅(Gbps) |
|---|---|---|---|---|
| inf1.xlarge | 1 | 4 | 8 | 最大 25 |
| inf1.2xlarge | 1 | 8 | 16 | 最大 25 |
| inf1.6xlarge | 4 | 24 | 48 | 25 |
| inf1.24xlarge | 16 | 96 | 192 | 100 |
Amazon EC2 Inf2インスタンス
Inf2インスタンスは、より高性能な第2世代の「AWS Inferentia2」チップを搭載した最新のインスタンスです。 Inf1インスタンスと比較して最大4倍のスループットと最大10分の1のレイテンシーを実現し、特に大規模言語モデル(LLM)や画像生成AIといった、より複雑で大規模なモデルの推論に最適化されています。 最新の生成AIアプリケーションなどで最高のパフォーマンスを求める場合に推奨されます。
| インスタンスサイズ | Inferentia2チップ数 | vCPU | アクセラレータメモリ(GiB) | ネットワーク帯域幅(Gbps) |
|---|---|---|---|---|
| inf2.xlarge | 1 | 4 | 32 | 最大 25 |
| inf2.8xlarge | 1 | 32 | 32 | 最大 25 |
| inf2.24xlarge | 6 | 96 | 192 | 50 |
| inf2.48xlarge | 12 | 192 | 384 | 100 |
ステップ2 AWS Neuron SDKをセットアップする
インスタンスを選択したら、次はAWS Neuron SDKをセットアップします。Neuron SDKは、TensorFlowやPyTorchといった一般的な機械学習フレームワークとInferentiaチップの橋渡しをするためのソフトウェア開発キットです。 これには、モデルをInferentia向けに最適化するコンパイラ、推論を実行するためのランタイム、そしてパフォーマンス分析ツールが含まれています。
セットアップは非常に簡単です。AWSが提供している「Deep Learning AMI (DLAMI)」には、Neuron SDKと各種ドライバがプリインストールされているため、これを選択してEC2インスタンスを起動するだけで環境構築が完了します。 手動でセットアップする場合は、公式ドキュメントに従ってNeuronのリポジトリを追加し、必要なパッケージをインストールします。
- Inf1またはInf2インスタンスを起動します。その際、AWS Deep Learning AMI (DLAMI) を選択するのが最も簡単です。
- インスタンスにSSHで接続し、PyTorchやTensorFlowなど、利用したいフレームワークに対応したNeuronのPython仮想環境を有効化します。
neuron-lsコマンドを実行し、Inferentiaチップが正しく認識されていることを確認します。
ステップ3 機械学習モデルをコンパイルしてデプロイする
最後のステップは、学習済みモデルをInferentia向けに「コンパイル」し、デプロイすることです。GPUでは不要なこの工程こそが、Inferentiaの性能を最大限に引き出すための重要なプロセスです。
コンパイルとは、お使いのPyTorchやTensorFlowのモデルを、Inferentiaチップが最も効率的に実行できる専用のフォーマット(NEFF: Neuron Executable File Format)に変換・最適化する作業を指します。 この処理により、モデルの演算がInferentiaのNeuronコアに最適化され、劇的なパフォーマンス向上が実現されます。
コンパイルは、Neuron SDKが提供するAPIを使って行います。例えばPyTorchの場合、torch.neuron.trace という関数を数行コードに追加するだけで、既存のモデルを簡単にコンパイルできます。 TensorFlowでも同様に専用のAPIが用意されています。 このコンパイル作業は、推論を実行するInf1/Inf2インスタンス上だけでなく、別のCPUインスタンス上で行うことも可能です。
コンパイルが完了したら、生成されたNEFFモデルをデプロイします。デプロイ先としては、Amazon SageMakerのエンドポイント、Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)、Amazon Elastic Container Service (ECS)、あるいはEC2インスタンス上で直接アプリケーションを動かすなど、様々な選択肢があります。 これで、アプリケーションから推論リクエストを送信し、Inferentiaによる高速・低コストな推論を実行する準備が整いました。
より詳しい手順やサンプルコードについては、AWSが提供する公式ドキュメント「AWS Neuron SDK」に豊富なチュートリアルが用意されています。
AWS Inferentiaの料金体系
AWS Inferentiaを利用する際のコストは、主に選択するAmazon EC2インスタンスの利用料金によって決まります。GPUインスタンスと比較して高いコストパフォーマンスを実現するように設計されており、推論ワークロードのコストを大幅に削減できる可能性があります。料金体系は柔軟で、オンデマンドでの利用から、長期利用による割引プランまで、ニーズに合わせて選択可能です。
オンデマンドインスタンスの料金
オンデマンドインスタンスは、初期費用や長期契約なしに、秒単位の従量課金で利用できる最も柔軟な料金モデルです。 プロトタイピングや、需要が不規則なアプリケーション、短期間のプロジェクトに最適です。料金はインスタンスのスペックと利用するリージョンによって異なります。
以下は、東京リージョンにおけるInferentia搭載インスタンス(Inf1, Inf2)のオンデマンド料金の例です。最新の正確な料金については、Amazon EC2 Inf2 インスタンスの公式ページやオンデマンド料金ページをご確認ください。
| インスタンスタイプ | AWS Inferentiaチップ | vCPU | メモリ (GiB) | オンデマンド料金 (USD/時間) |
|---|---|---|---|---|
| inf1.xlarge | 1 | 4 | 8 | $0.308 |
| inf2.xlarge | 1 | 4 | 16 | $1.1373 |
| inf2.8xlarge | 1 | 32 | 128 | $2.95179 |
| inf2.24xlarge | 6 | 96 | 384 | $9.73595 |
| inf2.48xlarge | 12 | 192 | 768 | $19.4719 |
Savings Plansやリザーブドインスタンスでさらにコスト削減
継続的かつ予測可能な推論ワークロードをお持ちの場合、AWSが提供する割引料金モデルである Savings Plans および リザーブドインスタンス を活用することで、オンデマンド料金と比較してさらにコストを削減できます。これらのプランはAWS Inferentia搭載インスタンスにも適用可能で、長期的な運用コストの最適化に極めて有効です。
- Savings Plans
1年または3年の期間で一定量のコンピューティング使用量(例: 1時間あたり$XX)をコミットすることで、オンデマンド料金から大幅な割引を受けられる柔軟な料金モデルです。 特に「Compute Savings Plans」は、リージョンやインスタンスファミリーを問わずEC2インスタンスに自動的に適用されるため非常に柔軟性が高く、オンデマンド料金と比較して最大66%のコスト削減が可能です。 AWS Inferentiaインスタンスもこのプランの対象となります。 - リザーブドインスタンス (RI)
特定のインスタンスタイプとリージョンを1年または3年の期間で予約することで、Savings Plansと同様に大幅な割引が適用されます。特定のワークロードが長期間安定して稼働することが決まっている場合に適しています。EC2 Instance Savings Plansは、特定のリージョン内のインスタンスファミリーに対して適用され、最大で72%の割引が可能です。
これらのプランは、AWS Cost Explorerで過去の利用状況に基づいた推奨事項を確認できるため、組織の利用パターンに最適なプランを簡単に選択し、購入することが可能です。 継続的な推論ワークロードを実行する本番環境では、これらの割引プランを積極的に活用することで、TCO(総所有コスト)を大幅に最適化できます。
AWS Inferentiaの活用事例
AWS Inferentiaは、その卓越したコストパフォーマンスと高性能な推論処理能力により、既に多くの企業やサービスで導入が進んでいます。特に、リアルタイムでの応答が求められるサービスや、大規模なデータを扱うアプリケーションにおいて、その真価を発揮しています。ここでは、具体的なユースケースを交えながら、AWS Inferentiaがどのように活用されているかを見ていきましょう。
画像認識や自然言語処理での利用
画像認識や自然言語処理(NLP)は、機械学習の推論が多用される代表的な分野です。これらの分野では、ユーザーからのリクエストに対して迅速に結果を返す必要があるため、低レイテンシーかつ高スループットな推論環境が不可欠です。
例えば、AI校正サービス「Shodo」を提供するゼンプロダクツ社は、従来GPUインスタンスを利用していましたが、コストとパフォーマンスの課題を抱えていました。 そこで、AWS Inferentiaを搭載したAmazon EC2 Inf1インスタンス、さらには後継のInf2インスタンスへ移行することで、コストとレイテンシーを半減させることに成功しました。 これにより、数万文字の日本語文章をリアルタイムで校正するという、計算負荷の高い処理を、優れたコスト効率でユーザーに提供できるようになったのです。
また、AWS自身のサービスであるAmazon AlexaやAmazon Rekognition、Amazon Searchといった大規模サービスでもInferentiaは活用されています。 特にAmazon Searchでは、Inferentiaを用いることで機械学習の推論コストを85%も削減したと報告されており、その効果の大きさがうかがえます。 これらの事例は、AWS Inferentiaが、高精度なモデルを低コストで運用するための強力なソリューションであることを示しています。
レコメンデーションエンジンへの応用
Eコマースサイトや動画配信サービスなどで利用されるレコメンデーションエンジンも、AWS Inferentiaの有力な活用領域の一つです。これらのサービスでは、ユーザー一人ひとりの行動履歴や嗜好に合わせて、リアルタイムに最適な商品やコンテンツを推薦する必要があります。
推論処理に時間がかかってしまうと、ユーザー体験を損なうだけでなく、ビジネス機会の損失にも繋がりかねません。AWS Inferentiaは、高いスループットと低いレイテンシーを実現することで、この課題を解決します。 膨大なユーザーデータと商品情報から、瞬時に関連性の高いアイテムを算出し、表示することが可能になります。
顧客体験管理ソフトウェアを提供するQualtrics社や、AIを活用した顧客体験管理プラットフォームを提供するSprinklr社なども、AWS Inferentiaを採用している顧客の一例です。 これらの企業は、自然言語処理を含む複雑なモデルを活用し、顧客からのフィードバックや問い合わせをリアルタイムで分析しています。AWS Inferentiaを利用することで、GPUインスタンスと比較して大幅なコスト削減を実現しながら、顧客体験の向上に必要な高速なインサイトの抽出を可能にしています。
以下に、AWS Inferentiaを活用している企業の事例をまとめます。
| 企業名/サービス名 | ユースケース | 主な導入効果 |
|---|---|---|
| 株式会社ゼンプロダクツ (Shodo) | AIによる日本語文章のリアルタイム校正 | GPUからの移行により、コストとレイテンシーを半減 |
| Amazon Search | 検索クエリに対する機械学習モデルの推論 | 推論コストを85%削減 |
| Finch Computing | リアルタイム自然言語処理(NLP) | GPUと比較して80%のコスト削減を実現 |
| Qualtrics | テキスト分類、感情分析などの体験管理ソフトウェア | 複雑なモデルの推論処理における高いスループットと低レイテンシーを実現 |
| Leonardo.ai | 生成AIによるビジュアルアセット制作 | パフォーマンスを維持しつつ、コストを80%削減 |
このように、AWS Inferentiaは、スタートアップから大規模なエンタープライズまで、幅広い企業において機械学習推論のコスト効率とパフォーマンスを劇的に改善するキーテクノロジーとして活用されています。
AWS Inferentiaに関するよくある質問
ここでは、AWS Inferentiaに関して多く寄せられる質問とその回答をまとめました。導入を検討する際の疑問点や不安を解消するためにお役立てください。
AWS Inferentiaは学習にも使えますか?
いいえ、AWS Inferentiaは機械学習モデルの「推論」処理に特化したチップであり、モデルの「学習」には使用できません。 機械学習のプロセスは、大量のデータからモデルを構築する「学習」フェーズと、学習済みモデルを使って予測や分析を行う「推論」フェーズに大別されます。AWS Inferentiaは後者の推論処理を高速かつ低コストで実行することを目的に設計されています。 AWSには、機械学習の学習に特化したカスタムチップとして「AWS Trainium」が別途用意されており、用途に応じて使い分けることが推奨されています。
どの機械学習フレームワークをサポートしていますか?
AWS Inferentiaは、AWS Neuron SDKを介して、主要な機械学習フレームワークを幅広くサポートしています。 これにより、開発者は既存のコードやワークフローを大幅に変更することなく、Inferentiaのパフォーマンスを活用できます。 具体的には、以下のようなフレームワークに対応しています。
- TensorFlow
- PyTorch
- Apache MXNet
これらのフレームワークで開発されたモデルは、Neuron SDKによってInferentiaに最適化された形式にコンパイルされ、デプロイされます。
AWS Inferentiaを使うには特別なコード修正が必要ですか?
既存の機械学習モデルをAWS Inferentiaで実行するために、アプリケーションコードの大規模な修正は通常必要ありません。 ただし、モデルをInferentiaチップ上で効率的に動作させるために、AWS Neuron SDKを使用してモデルをコンパイルするというステップが必要になります。 このコンパイル処理により、TensorFlowやPyTorchなどで作成されたモデルが、Inferentiaのアーキテクチャに最適化された実行可能な形式に変換されます。Neuron SDKは各フレームワークとネイティブに統合されているため、数行のコード変更でコンパイルプロセスを組み込むことが可能です。
GPUと比較して、AWS Inferentiaは常に高性能ですか?
AWS Inferentiaは、特に大規模な推論ワークロードにおいて、GPUと比較して優れたコストパフォーマンスを発揮するように設計されていますが、「常に」高性能であるとは限りません。 Inferentiaは、推論処理に特化することで、特定の条件下(例えば、リアルタイム性が求められる大規模な自然言語処理や画像認識など)で高いスループットと低いレイテンシーを実現します。 しかし、モデルの種類、バッチサイズ、演算の複雑さによっては、汎用的な計算能力を持つGPUの方が適しているケースもあります。そのため、プロジェクトの要件や特性に応じて、GPUとInferentiaのどちらを選択するかを慎重に検討することが重要です。
AWS Inferentiaを利用できるAWSサービスは何ですか?
AWS Inferentiaチップは、主にAmazon EC2インスタンスを通じて提供されており、それを基盤として様々なAWSサービスから利用することが可能です。 これにより、柔軟なインフラ上で推論アプリケーションを構築・デプロイできます。Inferentiaを利用できる主要なサービスは以下の通りです。
| サービス名 | 概要 |
|---|---|
| Amazon EC2 | Inferentiaチップを搭載したEC2 Inf1およびInf2インスタンスを直接利用できます。 OSレベルからの柔軟な環境構築が可能です。 |
| Amazon SageMaker | フルマネージドな機械学習サービスであり、モデルのビルド、トレーニング、デプロイを効率化します。SageMakerのエンドポイントとしてInf1やInf2インスタンスを選択することで、簡単にInferentiaを活用した推論環境を構築できます。 |
| Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) | コンテナ化された推論アプリケーションをKubernetesで管理・デプロイする場合に、ワーカーノードとしてInf1/Inf2インスタンスを利用できます。 |
| Amazon Elastic Container Service (ECS) | AWS独自のコンテナオーケストレーションサービスです。EKSと同様に、タスクの実行基盤としてInf1/Inf2インスタンスを指定できます。 |
まとめ
本記事では、AWSが提供する機械学習推論チップ「AWS Inferentia」について、その概要からGPUとの違い、具体的な使い方、料金体系までを初心者向けに網羅的に解説しました。機械学習モデルを本番環境で運用する際の大きな課題である「推論コスト」と「パフォーマンス」を解決する強力なソリューションであることをご理解いただけたかと思います。
この記事の重要なポイントを以下にまとめます。
- 推論に特化したカスタムチップ: AWS Inferentiaは、学習済みモデルを実行する「推論」処理に特化して設計されており、学習には利用できません。
- 圧倒的なコストパフォーマンス: GPUと比較して、推論ワークロードにおけるコストパフォーマンスが非常に高く、特に大規模なアプリケーションでは大幅なコスト削減が期待できます。これがInferentiaを導入する最大の理由です。
- 高性能な推論処理: 高いスループット(秒間により多くの推論を処理)と低いレイテンシー(推論結果が返ってくるまでの時間が短い)を両立させます。
- GPUとの適切な使い分け: モデルの「学習」にはGPUを利用し、デプロイ後の「推論」にはInferentiaを利用するという使い分けが、コストとパフォーマンスを最適化する鍵となります。
- 導入のしやすさ: AWS Neuron SDKを利用することで、TensorFlowやPyTorchといった主要なフレームワークで構築したモデルを、比較的少ないコード変更でInferentia向けにコンパイル・デプロイできます。
機械学習サービスの運用コストに課題を感じている方や、より高速なレスポンスが求められるアプリケーションを開発している方にとって、AWS Inferentiaは非常に魅力的な選択肢です。現在GPUベースで推論環境を運用している場合は、そのコストとパフォーマンスをInferentiaと比較検討する価値は十分にあります。
まずは、お使いの機械学習モデルがInferentiaでどの程度の性能向上とコスト削減を実現できるのか、小規模なテストから始めてみてはいかがでしょうか。未来のサービス基盤を支える技術として、ぜひAWS Inferentiaの活用をご検討ください。