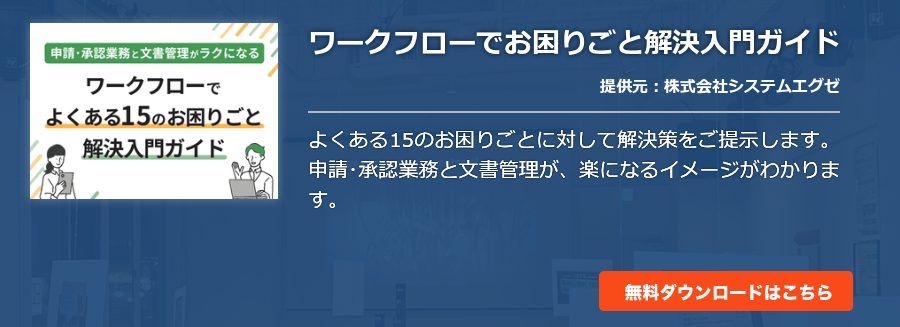Microsoftが提供するクラウドサービス「Azure」をご存知でしょうか。企業はもちろん消費者もクラウドを利用する時代です。しかし、今さら「クラウドって何?」と聞けない人がいるかもしれません。あるいは、Azureの費用が分からない、何ができるか知りたいなど、さまざまなレベルの疑問を持つ人々がいるのではないでしょうか。
この記事ではMicrosoft Azureに焦点を当て入門から応用まで幅広く解説します。Azureの特徴や主要サービス、導入に向けた注意点、導入事例などAzureの利用に向けた概要が分かりますので、ぜひ参考にしてください。
Azure(アジュール)とはMicrosoftが提供するクラウドサービス
「Azure」とはMicrosoftが提供しているクラウドのサービスです。読み方は「アジュール」となります。
Azureはインターネットを介してさまざまな開発者向けのサービスを中心に提供しており、世界中に利用ユーザーがいるクラウドサービスの集合体です。以下では、Azureの特徴やクラウドサービスの種類について解説します。
Azureの4つの特徴
Azureの特徴は以下の通りです。
- 全てのサービスがクラウド上で提供されている
- 使用した分だけ支払う従量課金制
- 無償で使用できる機能が多い
- 使用の際は日本の法律が適用される
全てのサービスがクラウド上で提供されている
Azureの特徴としてまず挙げられるのが、全てのサービスがクラウド上で提供されているという点です。先述の通り、クラウドサービスはインターネットを経由しクラウド環境にアクセスして利用します。Azureには多数のサービスが存在しますが、全てのサービスがクラウド上で提供されていることが特徴です。
使用した分だけ支払う従量課金制
Azureの2つめの特徴は、多くのサービスが使用した分だけ料金を支払う従量課金制であることです。オンプレミス環境の場合、ハードウェアやソフトウェアを自社で購入するため、サーバーの購入費用を「使用した分だけ支払う」ことはできません。一方でAzureではMicrosoftが提供するサーバーを利用したい量、時間分だけ使用する仕組みです。
無償で使用できる機能が多い
Azureの3つめの特徴として、無償で使用できる機能が多い点も挙げられます。先述の通り、Azureは従量課金制が採用されていますが、多くのサービスでは、従量課金が発生する前段階の無償枠が用意されています。また無料で利用できる、そもそも料金が発生しないサービスも多く取り揃えていることもAzureの特徴です。
使用の際は日本の法律が適用される
Azureの4つめの特徴は、日本で利用する際に日本の法律が適用される点です。Azureの管轄裁判所は東京地方裁判所であり、準拠法は日本の法律となっています。万一Azureの利用時にトラブルが発生しても、日本の法律が適用されるため、日本企業が安心して利用できるといえるでしょう。
クラウドとはなにか?
クラウドとは、インターネットを経由してクラウド事業者が提供しているサービスを利用する形態のことです。クラウド事業者が提供しているサービスより下のレイヤーはクラウド事業者の管轄となります。よってクラウドを利用することで、自社でハードウェア/ソフトウェアの購入や保守運用のコストから解放されるメリットがあります。
一方でクラウドを利用するデメリットは、社内システムとの連携が難しいことや、利用期間によってはオンプレミス環境よりもコストが高くなってしまう点です。
AzureとXaaSの関連性
Azureのサービスのうち、主な提供形態はIaaS(アイアース)とPaaS(パース)です。またAzureにはその他にもSaaSやXaaS(ザース)と呼ばれるサービスもあります。以下はクラウドサービスの提供形態についての解説です。
IaaS(Infrastructure as a Service)とは
IaaSが提供するのは、サーバーやストレージなどのハードウェア、ネットワーク環境のインフラ環境と仮想インフラ側のセキュリティです。いわばサービスの基盤(インフラストラクチャー)を提供します。
Azureでは、仮想マシン(VM)のインスタンスやデータベースを提供し、その容量と性能を自由に変えることが可能です。セキュリティ対策は事業者側と利用者側で責任範囲が決まっているため、利用者もOSやアプリケーションなど一定範囲のセキュリティ対策を実施する必要があります。
★詳しくはこちら:
IaaSの代表例を紹介! 意味やメリット・SaaS, PaaSとの違いとは
PaaS(Platform as a Service)とは
開発や実行環境を提供するサービスで、OSやミドルウェア、言語環境、分析ツール、ライブラリ、フレームワークを提供します。
Azureが主に提供しているのがこのPaaSで、OSなどの環境は自動的にアップデートされるため、メンテナンスの必要がありません。Windowsの他Linuxもサポートしています。また、ライブラリやフレームワークでは、多くの有名なオープンソースソフトウェア(OSS)を利用できることが特長です。
SaaS(Software as a Service)とは
Webブラウザでアプリケーションソフトウェアを実行するなど、クラウドでソフトウェアを提供するサービスです。一般的には、Webメールやオンラインストレージ、チャットやSNSなどのコミュニケーション系のソフトウェアがあり、昨今では財務会計アプリケーションもクラウドで運用されるようになりました。
Azureを使えば、開発したSaaSアプリケーションをすぐに利用できるため、ビジネスを迅速かつ効率的に展開することが可能です。
その他のXaaS
その他、Azureと関連するXaaSを挙げると、次のようなものがあります。
★詳しくはこちら:
XaaSとは?重要視される理由やメリットも解説
【徹底比較】AzureとAWSの違い
AzureとAWS(Amazon Web Services)は、どちらも世界中で利用されているクラウドサービスプロバイダーの1つです。AzureはMicrosoftが提供し、Windows環境との親和性が高く、既存のMicrosoft製品との統合がスムーズです。特に、企業のActive Directory環境やMicrosoft365製品とのシームレスな連携ができる点に強みを持っています。
一方、AWSはAmazonが提供し、多くのサービスと機能を備え、クラウド市場でのリーダーシップを誇っています。AWSは幅広いインスタンスタイプやサービスを提供し、特にスタートアップや開発者に支持されています。また、選択できるデータベースの種類の数も多く、幅広いユースケースで利用されています。料金体系では、両者とも使用量に応じた従量課金制を採用していますが、AWSは価格競争力が高い点が特徴です。
選択のポイントは、既存のIT環境やビジネスニーズ、求めるサポート内容によって異なりますが、Microsoft製品を多く利用していてクラウド化を進めたい企業はAzureを選択するとよいでしょう。
【徹底比較】AzureとGoogle Cloudの違い
AzureとGoogle Cloudは、クラウドサービス市場で急速にシェアを拡大しているサービスです。
AzureはMicrosoftのサービスであり、企業向けのサービスと既存のMicrosoftエコシステムとの統合が特徴です。一方、Google Cloudはビッグデータ解析や機械学習分野に強みを持っています。Googleの先進的なAI技術やデータ分析ツール(例えば、BigQueryやTensorFlow)を活用できます。
料金体系では、Google Cloudは柔軟な割引オプションや短期間の使用に適した価格モデルを提供しており、コスト効率を重視するユーザーに支持されています。Microsoft製品との連携を行いたい場合はAzure、AIや機械学習を業務に取り入れたい場合はGoogle Cloudを選択する場合が多いです。
| 項目 | Azure | AWS | Google Cloud |
| プロバイダー | Microsoft | Amazon | |
| 主要サービス | Azure Virtual Machines, Azure SQL Database, Azure App Services | EC2, RDS, S3, Lambda | Compute Engine, Cloud SQL, App Engine |
| リージョン数 | 60以上 | 33 | 40 |
| 強み | Microsoft製品とのシームレスな連携が可能 | データベースサービスの種類の豊富さ、開発環境の充実、豊富な実績 | AIや機械学習に強みを持つ |
Azureの主要なサービス一覧とできること
Microsoft Azureは、3大クラウドサービスの1つで、さまざまな企業ニーズに応じた多様なサービスを展開しています。以下ではAzureの主要なサービスを紹介します。紹介するサービスの一覧は以下の通りです。
- Azure Portal
- Azure Virtual Machines
- Azure Functions
- Azure DevOps
- Azure Virtual Network
- Azure Storage
- Azure SQL Database
- Azure Active Directory
- Azure Virtual Desktop
- Azure Information Protection
- Azure AI
Azureを統合的に管理「Azure Portal」
Azure Portalは Azureを統合的に管理するためのコンソール画面です。Azureにログインするのみで利用できます。
AzureはCLIなどコマンドベースの操作が可能です。しかし、Azure Portalの利用でGUIによるコマンドが不要で分かりやすい画面での操作も可能となっています。よって、プログラミングやコマンドの知識がなくても利用が可能というところがメリットです。Azure Portalの利用によって全てのリソースに対して操作が可能です。また自身が使いやすいようにカスタマイズすることもできます。
★詳しくはこちら:
Azure Portal(Azureポータル)とは?メリットや料金体系・使い方を解説
Azureの仮想マシンサービス「Azure Virtual Machines」
Azure Virtual MachinesとはAzureの仮想マシンを利用できるサービスです。Azure Virtual Machinesはさまざまな種類のCPU、メモリ、OSを選択し、利用したい環境を利用したい地域のデータセンターに構築できます。
代表的なIaaSのサービスであり、利用時にはAzureのポータル画面やSSH、RDP接続をすることによって、オンプレミス環境と同様に利用が可能です。
★詳しくはこちら:
Azure VMとは?メリットや種類、用途について解説
サーバーレスでコードを実行「Azure Functions」
Azure Functionsはサーバーレスでプログラムを実行できる実行環境です。通常、作成したプログラムを実行するためには実行環境となるサーバーや関連プログラムが必要となります。しかし、Azure Functionsでは仮想マシンをデプロイせず、ランタイムも事前に用意されているため、ソースコードのみでプログラムを実行可能です。
Azure Functionsによってプログラム実行環境の用意が不要となるため、開発者がコーディングに集中できるメリットがあります。
★詳しくはこちら:
Azure functionsとは?できることや構成図、AWS lambdaとの違いを解説
ソフトウェア開発・運用のためのツール群「Azure DevOps」
Azure DevOpsはプロジェクト管理のツール群です。プロジェクトの開発(Development)と運用(Operations)の両方を支援するためのツールが用意されています。
ツールの例として以下があります。
- Azure Pipelines(開発):実装したプログラムの実行環境デプロイやテストを行う
- Azure Monitor(運用):実行しているプログラムの監視を行う
★詳しくはこちら:
Azure DevOpsとは? アジャイル開発を実現するツール群の解説
ネットワーク基盤を構築できる「Azure Virtual Network」
「Azure Virtual Network(VNet)」は、Azureクラウド内で仮想ネットワークを作成し、管理するサービスです。これにより、オンプレミスのネットワークと同様に、クラウド上でもネットワーク分離、サブネットの作成、IPアドレスの管理が可能になります。
また、仮想マシンや他のAzureサービスとの安全な接続を確立できるため、セキュリティが強化され、ネットワーク全体のパフォーマンスも向上します。VPNゲートウェイを使えば、オンプレミスや他社クラウドのネットワークとAzureをシームレスに接続することもできるため、ハイブリッドクラウド環境の構築も容易です。「Azure Virtual Network」は、企業のITインフラをクラウドに拡張し、柔軟かつスケーラブルなネットワーク基盤を提供します。
Azure用のクラウドストレージサービス「Azure Storage」
Azure StorageはAzureのストレージサービスです。Azureが用意する大規模ストレージで、さまざまなデータを格納することができます。
またストレージに保存したデータは世界中のリージョンにコピーされるため、災害時などにもデータが消失する心配がありません。セキュリティ面においても、保存されたデータに暗号化が行われています。データ容量も無制限であるため、安全かつ大規模にデータの保存をすることが可能です。
★詳しくはこちら:
Azure Storageとは、概要と利用の流れ
フルマネージドなデータベースを実現「Azure SQL Database」
「Azure SQL Database」は、Microsoftが提供するフルマネージドなクラウドデータベースサービスです。このサービスは、ユーザーがデータベースのインフラ管理から解放され、データの挿入、アップデート、クエリなどに集中できるよう設計されています。高可用性とスケーラビリティを持ち、災害復旧機能も備えているため、重要なデータの安全性とパフォーマンスが保証されます。
さらに、自動バックアップ、パッチ適用、監視機能も提供されるため、管理コストを削減しつつ、効率的な運用が可能です。AIを活用した自動チューニング機能も備え、パフォーマンスの最適化を自動で行います。
IDの一元管理「Azure Active Directory」
Azure Active Directoryとは認証やアクセス許可などに利用するIDを管理するためのサービスです。Azure上で利用するAzure Portalに利用できることはもちろんですが、社内システムと連携することも可能です。連携させると社内で利用しているWindowsやOfficeのアカウントも管理をできるようになります。SSO(シングルサインオン)など、便利で安全な認証を利用でき、AzureとオンプレミスのWindows環境が相性がよいといわれる理由の1つです。
★詳しくはこちら:
Azure ADとは?機能やメリットを初心者にも分かりやすく解説!
安定したテレワーク環境を実現可能な「Azure Virtual Desktop」
「Azure Virtual Desktop(AVD)」は、リモートワーク環境を提供する仮想デスクトップサービスです。ユーザーはどこからでもクラウド上のデスクトップにアクセスでき、企業はセキュリティを確保しつつ、従業員に柔軟な働き方を提供できます。AVDは、Windows 10や11のマルチセッション機能をサポートし、複数のユーザーが同じ仮想マシンを効率的に共有できます。
さらに、Azure Active Directoryとの統合により、シングルサインオンや条件付きアクセスなどのセキュリティ機能も利用可能です。これにより、企業は従業員の生産性を高めつつ、管理の複雑さを軽減できます。AVDは、ハイブリッドワークやリモートワークのニーズに対応し、現代の柔軟な働き方を強力にサポートします。
情報漏洩を防ぐソリューション「Azure Information Protection」
Azure Information Protectionとは、Officeアプリ(Excelなど)で作成したドキュメントやメールの権限を操作するソリューションです。対象ファイルに対して閲覧や書き込みの権限編集ができるため、情報漏えいのリスクを下げることができます。
セキュリティを保持する1つの方法は、アクセス権限を付与する対象を最小限に設定することです。Azure Information Protectionでは必要なユーザーに必要な権限を設定できるため、セキュリティ強化につながります。
★詳しくはこちら:
Azure Information Protectionでメールや文書を保護
人工知能プラットフォーム「Azure AI」
Azure AIとは人工知能プラットフォームとして利用できるAIツールの集合体です。機械学習、ボット、スーパーコンピューティングなど、さまざまなツールが用意されています。
例として、機械学習サービスであるAzure Machine Learningを取り上げます。プログラミングによる開発はもちろんですが、GUIによる操作も可能なため、プログラミングに詳しくないユーザーでもAI開発が可能です。
OpenAI と提携してChatGPTなどをAzure上で動かせるようにする「Azure Open AI」といったサービスがあります。Azure AIはAzure Open AIとは別物であり、独自の AI モデルをトレーニング、デプロイ、管理できるサービスです。
★詳しくはこちら:
Azureで提供されるAIサービスの全体像・主なサービス9つを解説
企業にありがちなITに関する3つの課題
企業で抱えることが多い、ITに関する3つの課題を紹介します。3つの課題は以下の通りです。
- サーバーの設置場所がなく管理が大変
- データベースの容量がない
- サイバー攻撃や自然災害によるデータ消失のリスクがある
【課題1】サーバーの設置場所がなく管理が大変
自社で社内システムを開発および運用管理する場合、社内に広いサーバールームを確保して、開発運用環境をゼロから構築しなければなりません。ちなみに、社内で物理的にサーバーを構築して運用する方式を「オンプレミス」と呼びます。
また、社内サーバーの運用管理には専任の管理者が不可欠です。管理者の仕事は、機密データを保護するセキュリティ対策から社内の問い合わせ対応まで多岐にわたります。この他、自社でサーバー管理する場合、設備を置く物理スペースの確保も必要になります。
【課題2】データベースの容量がない
ビジネスで必要なファイルやデータベースシステムが保存するデータは、サーバーのHDDなどの物理的な記憶装置に保存されています。それらは保存容量が決まっているため、ファイルが増えたり、データベースが膨張したりした場合、HDDを増築するなどして容量を拡張する必要があります。また、実際に容量を拡張する際は、社内システム管理者に増設の旨を伝えて作業してもらう必要があり、機器を用意するコストや作業の時間がかかります。
【課題3】サイバー攻撃や自然災害によるデータ消失リスク
リモートワークが広く普及した近年、ますますセキュリティの問題が重要になってきています。これまでのセキュリティ対策といえば、社内データの保護が中心でした。しかし、社外における利用が以前よりも増加した現在では、重要情報が入ったパソコンの紛失や盗難、サイバー攻撃などによる情報漏えいのリスクが高まっています。
また、地震や津波などの自然災害と隣合わせの日本にいる以上、水没や物理的な破損によって企業の情報資産が脅かされるリスクについても考える必要があります。
課題解決に役立つAzureのメリット
Azureを導入することで、以下のようなメリットが得られます。日々発生しているコストを削減したい場合や、日常的にMicrosoft製品を使っている企業がクラウドで業務効率化を実現したい場合の候補として有力です。
また、IT設備の投資によって、機能の拡張や性能の向上を検討している場合は、Azureを利用することで簡単に実現できる可能性があります。Azureなら、その時々のビジネスニーズに応じたITリソースの提供が可能です。
コストを削減できる
Azureの料金体系は、使用した分だけ支払う形を取ります(従量課金制)。また、ITインフラの構築が必要な場合でも、Azureのリソースを利用することでハードウェアの初期投資が不要になります。これも、コスト削減ができる理由の1つです。
他には予約割引という仕組みがあり、リソースの使用状況を予測して1年か3年間の料金を先払いで予約することで、通常料金を割引価格で利用できます。基幹システムなど稼働状況の予測がつきやすい場合に利用すると、大幅なコスト削減効果が期待できます。
Microsoft製品との親和性が高い
OfficeやShare Pointなど、他のMicrosoft製品を利用している場合は、Azureのサービスと連携して運用できます。同じ会社の製品・サービスのため操作感が似ており、Azureを新たに導入する場合でも抵抗を感じにくいでしょう。
また、サーバーOSとしてよく採用されているWindowsとも連携しやすく好相性です。
柔軟な拡張と運用管理が可能
クラウドという性質上、利用者側でハードウェアを用意しなくても仮想環境のリソースが調達できる点と、スケーリングに対応している点もメリットです。
物理マシンと違い、仮想マシンは処理負荷の増減に応じてシステムの性能を柔軟に拡張・縮小できます。一例を挙げると、サーバーのアクセス負荷に応じて仮想マシンの台数やスペックを調整するといった使い方も可能です。
メンテナンスの際も、担当者はクラウドの管理画面で一元管理できるため、物理マシンを管理するよりも負担が小さくなります。
ハイブリッドクラウドの実現
Azureの利用によってハイブリッドクラウドの実現ができるメリットがあります。ハイブリッドクラウドとはAzureのようなパブリッククラウドを、プライベートクラウドやオンプレミスの環境と接続して利用する形態です。
ハイブリッドクラウドを利用することで多くのメリットを享受することが可能となります。例として、バックアップデータの分散やパブリッククラウドにはない機能の利用などを実現できます。
巨大なバックボーンネットワークの使用が可能
Azureを利用するメリットは、巨大なバックボーンネットワークが使用可能であることです。AzureはMicrosoftによって世界各国に拠点が展開されています。各拠点はバックボーンネットワークで接続されているため、ユーザーはこのネットワークを利用した通信が可能です。データの分散やシステムの連携など、多くのエリアで展開されたサービスを利用したい場面でも、少ないネットワーク遅延で利用が可能となっています。
堅牢なセキュリティ
Azureのメリットとして、堅牢なセキュリティが施されている点も挙げられます。世界各国のデータセンターは警備員や外壁によって厳重に管理されています。またサービスを提供するサーバーにもサイバー攻撃に対する防御や、トラフィック監視によって厳重な警戒、制御が行われています。
Azureはユーザーが利用するサービスより下のレイヤーはMicrosoftの管轄です。例としてSaaSであればハードウェアはMicrosoftの管轄となります。上記の厳重なセキュリティもMicrosoftの管轄であり、利用料金に含まれているため、ユーザーはセキュリティ対策を意識することなく安心してサービスを利用可能です。
多様なOS、DB、プログラミング言語に対応
Azureは多様なOS、DB、プログラミング言語に対応しているというメリットがあります。MicrosoftのOSといえばWindowsですが、Linuxも利用可能です。またDBもOracleやMySQL、PostgreSQLなどさまざまな製品に対応しています。
プログラミング言語についてもPython、JavaScript、Java、.NET、Goなど、多数の言語に対応しているため、多くのユーザーがv自身の得意な言語で開発を進めることが可能です。
Azureのデメリット

Azureは多機能で柔軟なクラウドサービスを提供しますが、いくつかのデメリットも存在します。例えば、ユーザーインターフェースが頻繁に変更されることや、仮想マシンスペックの自由度が低い点が挙げられます。これらの点について、詳しく見ていきます。
ユーザーインターフェースが頻繁に変更される
Azureのユーザーインターフェースは頻繁に更新され、改善されていますが、これがデメリットになる場合もあります。インターフェースが変更されると、ユーザーは新しいレイアウトや機能に慣れるための時間が必要です。特に、定期的にAzureを使用している管理者や開発者にとっては、作業フローの中断や生産性の低下を引き起こすことがあります。
また、ドキュメントやトレーニング資料がインターフェースの変更に追いついていない場合もあり、これが学習や問題解決の際の障壁になることがあります。頻繁なインターフェースの変更は、常に最新情報を追い続ける必要があるため、特に忙しいIT部門にとっては負担となり得るでしょう。
仮想マシンスペックの自由度が低い
Azureでは、提供されている仮想マシン(VM)のスペックを選択する際に、あらかじめ決められたサイズや構成から選ぶ必要があります。このため、特定の要件に合わせてVMをカスタマイズする柔軟性が制限されることがあります。
例えば、特定のCPUとメモリの組み合わせが必要な場合、Azureが提供するプリセットオプションでは適切な構成が見つからないことがあります。また、カスタムのスペックが必要な場合、他のクラウドサービスプロバイダーと比較してコストが高くなることも考えられます。
この制約により、一部の企業や開発者は、必要な性能を得るために複数のVMを使用するか、他のクラウドサービスを検討する必要が出てくるかもしれません。AzureのVMスペックの自由度が低い点は、特定のワークロードに対して最適なリソース配置を行いたいユーザーにとっては大きなデメリットとなります。
Azureのライセンス(料金)体系
先述したようにAzureは従量課金制を採用しており、使った分だけ料金が発生します。利用に必要な無料アカウントを取得すると、30日間の試用期間と、Azureのあらゆるサービスを利用できる200ドルのAzureクレジットが付与されます。このクレジットの範囲内で試したいサービスの利用が可能です。クレジットを使い切るか30日経過したら、サブスクリプション(従量課金制)に切り替えることで継続利用できるようになります。
Azureのサービスは、無料提供機能と従量課金制の機能で構成されています。各サービスでかかる具体的な費用については、「料金計算ツール」「TCO計算ツール」を使えばシミュレーションが可能です。また、オプションとして開発やテストで利用する場合は、長期的な割引料金が適用されます。
なお、オンプレミスのWindows ServerやSQL Serverの既存ライセンスがある場合、Azureハイブリッド特典としてAzureサービス上で利用可能です。オンプレミスのライセンスもムダなく利用でき、コスト削減に役立ちます。
Azureの導入手順
Azureの導入は、初心者でも簡単に行うことができます。初心者でもイメージしやすいAzureアカウントの作成から仮想マシンの作成までを以下の手順で進めてみましょう。
- Azureアカウントの作成
Azureの公式サイトにアクセスし、無料アカウントを作成します。名前やメールアドレス、支払い情報を入力します。 - Azureポータルにログイン
アカウント作成後、Azureポータルにログインします。Azureポータルは、クラウドリソースを管理するためのWebインターフェースです。 - リソースグループの作成
リソースを管理しやすくするために、関連するリソースをまとめる「リソースグループ」を作成します。 - リソースの作成
Azureポータルのダッシュボードから「リソースの作成」ボタンをクリックします。ここでは仮想マシン、データベース、ネットワークなど、さまざまなリソースを選択できます。 - 仮想マシンの設定
仮想マシンを例にとると、作成画面で名前、リージョン、サイズ(CPU、メモリ)、OSなどの設定を行います。 - 設定内容の確認と作成
設定が完了したら、内容を確認し、「作成」ボタンをクリックします。これで、Azureがリソースをデプロイし、使用可能になります。
Azureを導入する際の注意点
当記事をここまでお読みになり、Azureの導入を検討されている方もいるのではないでしょうか。ここでAzureを導入する際の4つの注意点を解説します。注意点は以下の通りです。
- 専門知識とスキルが必要
- 通信トラブルへの対策
- 認証機能の強化
- クォーター制限
専門知識とスキルが必要
Azureを導入する際には専門知識や利用スキルが必要になります。先述の通り、Azureにはさまざまなサービスが用意されており、この記事で取り上げていないサービスも多数あります。また日々アップデートされており、ユーザー側も知識やスキルをアップデートしないと使いこなすことができません。使いこなしてこそ、導入の意味があるため、日々学習する覚悟が必要です。
通信トラブルへの対策
Azureを導入する際には通信トラブル対策が必要になります。Azureの利用には基本的にインターネット接続が必要だからです。社内システムとは違い、社外と接続する必要があるため、通信にはセキュリティ対策を考えなければなりません。インターネット接続にトラブルが生じると、Azureとの通信ができなくなってしまうため、十分な帯域を確保しましょう。
認証機能の強化
Azureを安全に利用するためには、ユーザーの認証を強化しておく必要があります。Azureではユーザーごとにアクセス権限を設定できますが、強い権限を持ったユーザーになりすましたアクセスによる情報漏えいなど、セキュリティ面の懸念があります。生体認証を用いるなど、多段階認証によって認証機能を強化しておくことで、対策しておきましょう。
クォーター制限
Azure利用時の注意点としてクォーター制限があります。クォーター制限とは、利用できるリソースの制限のことです。例えば、Azureサブスクリプションのリソースグループ数は980が上限となっています。上限はオンラインカスタマーサポートへの申請で無料で引き上げてもらうことができます(ただし、無料サブスクリプションについては引き上げできません)。
引き上げを忘れなければ問題ありませんが、クォーター制限があることは頭に入れておきましょう。
Azureの管理方法
Azureの管理方法としては、先述したAzure Poralによる管理が一般的です。GUIで全てのリソースに対する操作を行うことができます。Azure Portalでできることとして、以下があります。
- リソースのデプロイや削除、編集
- インシデント確認、通知
- リソース、サービスの監視や診断
上記をGUIで全て行うことができるため、Azureへのログインさえできれば誰でも管理を担当することが可能です。
Azureへの移行方法
現在利用中のシステムをAzureへ移行する方法を解説します。移行方法は以下の手順です。
- Azureと現状の評価・検証
- Azureへの移行
- Azure環境の最適化
- Azure環境のセキュリティの保護と監視
Azureと現状の評価・検証
システム移行を実施する前に、移行で実現したいことの優先順位と目標を定めましょう。組織の各部署から関係者を集め、Azureとオンプレミスを比較した総保有コスト(TCO)を検討し、移行の必要があるアプリケーションを洗い出して評価します。
このとき、クラウド移行のための自動化ツールを利用すると、現在の環境とアプリケーションの依存関係が分析できます。迅速に作業を完了するためには、依存関係の少ないアプリケーションの移行から着手することが重要です。なお、SQL ServerをAzure に移行する際の互換性を確認するツールとして、「Data Migration Assistant」が用意されています。
Azureへの移行
Azureへの移行には、一般的に次の4つのレベルを考えておく必要があります。
- リホスト:コードを編集することなく移行します。IaaSとデータベースを移行し、最適化します。
- リファクター:アプリケーションに若干変更を加えて、クラウドに最適化します。その後、データベースを移行し、「Azure DevOps Services」で最適化します。
- リアーキテクト:アプリケーションのコードを変更もしくは拡張して、クラウド向けに最適化します。これまでのアプリケーション資産を活かしたいときに有効です。
- リビルド:アプリケーションをクラウド向けにゼロからビルドします。クラウドネイティブなアプリケーションに進化させることで、AIなど最新の技術に対応させることが可能です。
リビルドを選択する場合、企業にとって最も大きい開発負荷がかかりますが、クラウドネイティブなアプリケーションとして最先端の機能を活用できます。
Azure環境の最適化
「Azure Cost Management」を用いてクラウドアプリケーションの支出を管理し、仮想マシンのサイズの調整や、Azureの特典を利用したコスト削減など、移行したシステムの最適化を図ります。
Azure環境のセキュリティの保護と監視
Azureへの移行後は、Azureが仮想マシンやアプリケーション、データを保護します。「Azure Security Center」は業界最高水準のセキュリティを提供しており、「Azure Backup」でデータを保護し、「Azure Monitor」によって利用統計情報の監視を行い、正常かつ最大のパフォーマンスを発揮できるように分析します。
Azureの導入に向いている企業
Azureの導入に向いている企業の3つの特徴を以下で紹介します。
- Windows製品・MS製品と連携させたい企業
- オンプレミスとクラウドの両方を活用していきたい企業
- 機密情報を扱う企業
特に3つとも当てはまる企業は、ぜひ導入を検討しましょう。
Windows製品・MS製品と連携させたい企業
AzureはWindowsOSやOfficeといったMicrosoft製品と連携させたい企業に向いています。理由として、Azure Active DirectoryなどMicrosoft製品と連携させるためのサービスが充実しているためです。Azure Active Directoryを用いることで、SSOなど連携を便利かつ安全に行うことができます。Azure上だけでなく、オンプレミス環境の管理にも活かしやすいため、Azureの導入が向いているケースといえるでしょう。
オンプレミスとクラウドの両方を活用していきたい企業
オンプレミスとクラウドの両方を活用したい企業もAzureの導入が向いているといえます。Azureはハイブリッドクラウドを構成、管理するためのサービスが多く提供されているためです。例として、インターネット接続に限らずAzureと閉域網接続を行うAzure ExpressRouteやハイブリッドクラウドの管理を行うAzure Arcなどがあります。
Azure単体利用に比べ、ハイブリッドクラウドによるメリットもあるため、オンプレミス、クラウドの両方を活用したい企業にとってもAzureの導入が向いているといえるでしょう。
★詳しくはこちら:
ハイブリッドクラウドとは?メリット・デメリット・構成例も解説!
機密情報を扱う企業
機密情報を扱う企業にとってもAzure導入が向いているといえます。クラウド(外部環境)に機密データを保管することに抵抗がある企業も多いのではないでしょうか。しかし、Azureは高度なセキュリティを維持するために多くの対策が施されています。
またセキュリティ強化のサービスも多く用意されているため、安全なデータの保管が可能です。よって、機密情報を扱う企業にはAzureの導入が向いているといえます。
Azureを導入した企業の成功事例
Azureを導入した企業の成功事例を紹介します。紹介する企業は以下の通りです。
- シミックホールディングス株式会社
- コマツ産機株式会社
- 株式会社YEデジタル
シミックホールディングス株式会社
シミックホールディングス株式会社は、急速な医薬・ヘルスケア業界のビジネス進化に対応するためにAzureを導入しました。医薬・ヘルスケア業界もAI、DXが不可欠となってきています。クラウド導入にあたりAzureを採用した背景は以下の通りです。
- 同社では、すでにMicrosoftのシステムを利用していたこと
- Azureを利用する場合、リソース予約などコスト削減のためのサービスが用意されていること
- Azureへの移行には、Azure Migration Programにより移行が支援されていたこと
現在は徐々にAzureへの移行を進めており、2025年までに完全移行を目指しています。将来的には既存システムの移行に留まらず、新規ビジネスの挑戦に向け、Azureのさらなる有効活用の検討を進めているところです。
コマツ産機株式会社
コマツ産機株式会社はAzure Machine Learningを導入したことで、製造設備の「予知保全システム」を開発しました。従来、製造設備の故障は故障後に対応することが一般的でした。しかし、故障後の修理対応中は生産ラインの停止、売上低下に繋がってしまいます。よって、故障前に故障の予兆を知る工夫が必要でした。そこで機械学習によって故障する前に、故障の可能性がある設備の特定をすることになりました。
Azure Machine Learningを導入した背景には以下があります。
- 同社ではすでにAzureを利用していたこと
- Azure Machine Learningは、同等の製品と比較して、料金が安かったこと
- 製造ライン勤務者の知識が少なくてもノーコードで開発を進められること
コマツ産機株式会社は今後、予知保全システムに限らず、さらに業務効率化できるソリューションを生み出したいと考えています。
株式会社YEデジタル
株式会社YEデジタルはビジネスDX ソリューションのプラットフォーム基盤としてAzureを利用しています。背景として、顧客から既存システムの流用や他システムとの連携など、柔軟性、拡張性のある仕組みを要望されるケースが増えたことです。こうした背景の中、クラウド導入を検討し、Azureを採用した理由は以下の理由の通りです。
- セキュリティ面などクラウドプラットフォームとしての信頼性や安心度が高いこと
- Azureの今後の発展性があること
- 協業体制の充実度が高いこと
Azure導入後、ソリューションは他の業種業態にも応用できる内容になりました。今後はより幅広い業種業態の顧客への展開を目指しています。
まとめ
AzureはIaaS・PaaS・SaaSのサービスを提供しており、それらを組みあわせて小規模~大規模のシステム開発まで、さまざまなレベルの利用に応じてカスタマイズすることが可能です。無料体験もあるため始めるのは簡単ですが、「目的」が明確でなければ、どの機能を使えばよいのか途方に暮れることになりかねません。柔軟に機能を追加したり拡張したりできることがクラウドのメリットですが、使いこなすには目的を明確にして利用することが重要です。
また、Azureの提供している範囲は、PaaSを超えて拡がりつつあります。一方で、セキュリティに関するIDaaSをはじめ、HCIやエッジコンピューティング、DaaSなど最先端のテクノロジー分野を次々に取り込みつつあります。また近年のAIブームに対応するため、Azure AIのサービスの拡張も進んでいます。
「クラウドシフトには抵抗がある」という企業もあるかもしれません。しかし、少し先の未来を見通したときに、Azureのような新しい技術を試してみることは、企業の将来にとって意義があるのではないでしょうか。